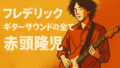始めに(特徴紹介)
打首獄門同好会のギタリスト、大澤敦史は、バンドの骨太でユーモラスかつ激しいサウンドを支える中心的存在です。彼のギターサウンドは、メタル由来の重厚さとパンクの荒々しさを兼ね備えながら、どこかポップなキャッチーさも持っています。
代表曲「日本の米は世界一」や「布団の中から出たくない」では、強烈なリフワークと分厚いバッキングが炸裂します。レスポールの重量感あるトーンとMarshallアンプの力強い歪みを組み合わせることで、曲のテーマを支えるユニークな世界観を作り出しているのです。
また、ライブではMarshall JCM2000 DSL100などの王道ブリティッシュアンプを用いた迫力あるサウンドから、近年ではMarshall SV20Hといった小出力モデルも導入し、音抜けとパワーを兼ね備えた新しいアプローチを展開しています。これにより、小規模会場から大規模ステージまで柔軟に対応するサウンドシステムを構築している点も注目されます。
さらに、曲によってはFender Stratocasterなどのシングルコイルモデルを使用する場面も見られ、明るく抜けの良いサウンドでバンドの楽曲に彩りを添えています。大澤のギターサウンドは、単にヘヴィなだけではなく、ユーモラスな歌詞や曲調に寄り添う柔軟な音色コントロールが魅力です。
このように、大澤敦史のサウンドは「重厚かつキャッチー」という独特の両立を果たしており、打首獄門同好会の音楽性を象徴する大きな要素になっています。
使用アンプ一覧と特徴【打首獄門同好会・大澤敦史】
大澤敦史のアンプセレクトは、打首獄門同好会のユニークで力強いサウンドを形成する大きな要因となっています。ライブ映像や写真から確認できるように、王道ブリティッシュサウンドを軸にしながらも、ステージ規模や楽曲の雰囲気に応じて柔軟に機材を使い分けています。
まず代表的なのは、Marshall JCM2000 DSL100です。100Wフルサイズの真空管アンプヘッドで、90年代から2000年代にかけて多くのロックギタリストに愛されたモデルです。大澤はこのアンプをメインに据えており、強烈なディストーションと伸びやかなクランチサウンドを自在に切り替えることで、骨太なリフや力強いパワーコードを支えています。特に「日本の米は世界一」のようなリフ中心の楽曲で威力を発揮していると考えられます。
さらに近年では、Marshall SV20H Studio Vintageも導入しています。これは20W出力の小型ヘッドアンプでありながら、「20Wとは思えないパワーと音抜け」を持ち合わせ、本人もインタビューでお気に入りだと語っています。大規模会場でもマイキングによって十分な音圧が確保できるため、取り回しの良さと可搬性を兼ね備えた実用的な機材です。ライブやレコーディングでも使用されており、JCM2000よりもややビンテージ寄りのトーンで楽曲にニュアンスを加えています。
キャビネットとしては、Marshall 1960系 4×12キャビネットを組み合わせている姿が多く確認されています。4発の12インチスピーカーが生み出す音圧はバンドサウンドを下支えし、分厚い低域と豊かな音の広がりを提供します。これは王道の組み合わせであり、彼の骨太サウンドの要となっているといえるでしょう。
また、Fender系のコンボアンプもステージ上に設置されているのが確認されており、特定の楽曲や小規模会場での音作りに利用している可能性があります。Fenderアンプ特有のクリーントーンや軽やかな歪みが、打首獄門同好会のコミカルで明るい楽曲にフィットする場面もあると考えられます。
このように、大澤のアンプ選びは「パワフルさ」と「柔軟性」を両立することを意識していると考えられます。確定情報としてはMarshall系が中心ですが、曲や環境に応じて使い分けていると想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall JCM2000 DSL100 | Marshall | Amazonで探す | 打首獄門同好会 | 大澤敦史 | 100Wのフルサイズヘッド。王道のブリティッシュディストーションを提供。メインアンプとして長年使用。 |
| Marshall SV20H Studio Vintage | Marshall | Amazonで探す | 打首獄門同好会 | 大澤敦史 | 20Wの小型ヘッド。ライブとレコーディングで愛用。本人も「見た目が可愛い」とコメント。 |
| Marshall 1960 4×12 Cabinet | Marshall | Amazonで探す | 打首獄門同好会 | 大澤敦史 | 豊かな低域と迫力の音圧を提供。ライブでJCM2000やSV20Hと組み合わせて使用。 |
| Fender コンボアンプ(モデル不明) | Fender | Amazonで探す | 打首獄門同好会 | 大澤敦史 | ステージで確認される。明確なモデルは不明だが、クリーン寄りの楽曲で使用している可能性あり。 |
使用ギターの種類と特徴【打首獄門同好会・大澤敦史】

大澤敦史のサウンドの根幹を支えているのは、彼が長年愛用しているギターです。ステージ写真やMVから確認できるように、王道のレスポールを中心に据えつつ、時にストラトキャスターなどを使用して多彩なサウンドを作り出しています。
メインギターとして最も多く確認されるのは、Gibson Les Paul Deluxe(ゴールドトップ)です。このモデルは通常のレスポールスタンダードとは異なり、ミニハムバッカーを搭載しているのが特徴。通常のハムバッカーよりもタイトで硬質なサウンドが得られるため、バンドの分厚いリズムを保ちながらも輪郭が埋もれないトーンを実現しています。特に「フローネル」や「日本の米は世界一」などのリフ主体の楽曲において、その硬質で突き抜けるサウンドは大澤の代名詞といえるでしょう。
また、ライブやインタビューで使用が確認されているのが、Fender Stratocaster American Vintageシリーズです。レスポールよりも軽量で明るく抜けの良いトーンが特徴で、シングルコイルの持つシャープさを生かし、より明るくポップな曲調の際に登場します。打首獄門同好会の楽曲にはユーモラスでキャッチーな側面も多く、そのニュアンスをストラトキャスターで補完していると考えられます。
こうしたギターの選択は、単に音色の違いを楽しむだけでなく、楽曲ごとのキャラクターを際立たせる意図があると推測されます。レスポールでヘヴィな部分を支えつつ、ストラトで抜けの良さを加えることによって、バンドの幅広い表現力を可能にしているのです。
また、大澤のピッキングスタイルは比較的強めで、アンプの歪みだけでなく演奏のニュアンスで音圧をコントロールしています。これにより、ミニハムバッカー搭載のレスポールデラックスでも必要以上に音が硬くならず、適度な厚みを保ちながら楽曲に寄り添うトーンを生み出しています。
このように、大澤敦史のギターセレクトは「骨太さと抜けの両立」をテーマにしたものであり、バンドサウンドの要として機能していると考えられます。実際の使用状況から推測される部分も含まれますが、レスポールとストラトの使い分けは彼の音作りにおいて重要なポイントだと想定されます。
使用エフェクターとボード構成【打首獄門同好会・大澤敦史】
大澤敦史のエフェクターボードは、詳細な全貌が公表されていないため推測を含みますが、ライブや音源から聴き取れるサウンド傾向を分析すると、彼のサウンド作りの哲学が見えてきます。基本的には「アンプの歪みを主体」としており、ペダルはあくまで補助的な役割を担っていると考えられます。これはMarshallアンプの持つ力強いゲインと、レスポール・ストラトといったギターの個性を前面に押し出すスタイルに直結しています。
ライブでの写真や映像では、オーバードライブ系のペダルが確認されることがあります。代表的な候補は、BOSS SD-1やBOSS OD-3など。これらはMarshallアンプの歪みをブーストする用途に適しており、リードパートでの音抜けや、リフの際の輪郭を強調するために使用していると推測されます。
また、より激しいディストーションやファズ感を加えるために、Electro-Harmonix Big MuffやPro Co RAT系のペダルを使用している可能性も高いです。打首獄門同好会の楽曲は、ヘヴィなリフとユーモラスな歌詞が融合しており、厚みのある壁のようなサウンドを作るために、アンプ直の歪みに加えファズライクなサウンドを重ねることが考えられます。
さらに空間系としては、BOSS DDシリーズやMXR Carbon Copyのようなディレイペダルを使用している可能性が高いです。リフ中心の楽曲では空間系はあまり目立ちませんが、ソロや曲間で奥行きを作り出す場面では効果的に利用されていると考えられます。
その他にも、ステージ写真ではチューナーペダルやパワーサプライなど基本的なセットアップは確認されていますが、彼のエフェクトシステムの根幹は「必要最低限に留めつつ、アンプの持ち味を生かす」というシンプルな思想に基づいているといえるでしょう。
このシンプルな構成によって、曲ごとのキャラクターをギターとアンプの組み合わせでダイレクトに表現できることが、大澤敦史のサウンドの説得力につながっています。つまりペダルに依存するのではなく、プレイそのものとアンプのチョイスが音作りの中心にあると想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | エフェクターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS SD-1 Super OverDrive | BOSS | Amazonで探す | 打首獄門同好会 | 大澤敦史 | オーバードライブ | Marshallアンプの歪みをブーストする目的で使用が想定される。リード時の音抜け補強に有効。 |
| Pro Co RAT 2 | Pro Co | Amazonで探す | 打首獄門同好会 | 大澤敦史 | ディストーション | 厚みのある歪みを作るための候補。激しいリフや重厚な曲調で補助的に使用している可能性あり。 |
| Electro-Harmonix Big Muff Pi | Electro-Harmonix | Amazonで探す | 打首獄門同好会 | 大澤敦史 | ファズ | 分厚い壁のようなサウンドを補強する候補ペダル。確定ではないが楽曲特性から使用が推測される。 |
| BOSS DD-7 Digital Delay | BOSS | Amazonで探す | 打首獄門同好会 | 大澤敦史 | ディレイ | ソロや空間を演出する場面で使用されていると推測される。MXR Carbon Copyとの併用可能性もあり。 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【打首獄門同好会・大澤敦史】

大澤敦史の音作りの最大の特徴は「アンプ本来の歪みを活かす直球型」であることです。Marshall DSL100やSV20Hといったブリティッシュアンプを軸に、ギター本体のキャラクターをストレートに出すことを基本としています。これは、打首獄門同好会の音楽性である「骨太なリフ」と「ユーモラスな歌詞」を両立させる上で必須の要素となっています。
EQの基本設定は、低域をやや持ち上げ、中域をしっかり確保しつつ高域はやや抑える傾向が考えられます。例えばDSL100では、Bass 6〜7、Middle 6〜7、Treble 4〜5程度に設定し、Presenceは会場の響きによって調整する形です。これにより低域の迫力を保ちながら、中域でリフが抜け、ヴォーカルやベースとの干渉を避けるバランスが取れます。
アンプチャンネルの切り替えは楽曲ごとに工夫されていると考えられます。リズム主体の楽曲ではCrunchチャンネルで分厚くタイトなリフを鳴らし、ソロやリードではLeadチャンネルに切り替えてサステインを稼ぐ、という流れです。特に「島国DNA」などのアップテンポな曲ではCrunchの音圧が強調され、一方で「日本の米は世界一」ではLeadチャンネルによる伸びのあるリードが確認できます。
エフェクターはあくまで補助的ですが、オーバードライブをブースター的に利用してソロ時の音量を押し上げることが多いと想定されます。これにより、全体のバンドアンサンブルに埋もれず、ギターが前に出てくる瞬間を作り出せます。
ミックス面においては、エンジニアが大澤のギターを楽曲ごとにバランス良く配置しています。打首獄門同好会の楽曲はベースラインが非常に存在感を持っており、ギターは中域から高域にかけての抜けで勝負する傾向にあります。そのため、ミックス時にはギターの低域を過度に持ち上げず、バスドラムやベースとの住み分けを徹底していると考えられます。
ライブPAでも同様に、中域を強調しつつも高域を刺さらないように調整し、ローエンドはPAで補強するスタイルです。これにより、会場規模を問わず「音の壁」を形成しつつ、歌詞のコミカルさを邪魔しない絶妙なバランスを作り出しています。
また、大澤はピッキングの強弱で音のキャラクターを大きく変えるため、セッティング自体はシンプルでも「演奏ニュアンス」でダイナミクスを表現している点も重要です。EQやゲインを極端に変化させなくても、手元で音圧や歪み感をコントロールできるため、ライブでも臨機応変なサウンドメイクが可能になっています。
総じて、大澤敦史の音作りは「Marshallアンプの持つ王道の歪みを基盤に、ギターとピッキングのニュアンスで彩りを加え、ミックスで整理する」という流れに集約されます。これは確定的な情報というより、実際のライブや音源分析から推測されるものであり、彼のプレイスタイルと機材の選び方から導かれる音作りの工夫であると想定されます。
比較的安価に音を近づける機材【打首獄門同好会・大澤敦史】
大澤敦史の音作りは、王道のMarshallアンプとレスポール系ギターを主体に構築されています。しかし、初心者や趣味でコピーを楽しむプレイヤーにとって、フルサイズのMarshallヘッドや本家Gibson Les Paul Deluxeを揃えるのはコスト的にハードルが高いのも事実です。そこで、比較的安価に音を近づけることができる市販の機材を紹介します。
まずギターに関しては、エピフォンのEpiphone Les Paul Standardや、Greco・Edwardsといった国産ブランドのレスポールタイプが良い選択肢となります。ミニハムバッカー搭載モデルは希少ですが、一般的なハムバッカー仕様のレスポールでもアンプ側で中域を調整すれば大澤らしい「硬質で厚みのあるトーン」に近づけることが可能です。シングルコイルサウンドを試したい場合には、Squier Classic Vibeシリーズのストラトキャスターもおすすめです。
アンプに関しては、フルサイズMarshall DSL100は自宅練習には現実的ではないため、Marshall DSL20CRやMarshall MGシリーズが手頃な選択肢になります。特にDSL20CRは真空管仕様でありながら小出力で扱いやすく、自宅や小規模ライブでも「ブリティッシュロックの王道歪み」を体感できます。
エフェクターでは、定番のBOSS SD-1が必須です。Marshallアンプの歪みをさらに押し上げるブースターとして機能し、ソロやリード部分を前に出すために効果的です。また、厚みを加える目的でPro Co RAT2や、空間処理にBOSS DD-7を組み合わせると、より大澤らしい迫力と奥行きを再現できます。
さらに、初心者にはマルチエフェクターBOSS GT-1やZoom G3Xnもおすすめです。これらはMarshall系アンプシミュレーションや歪み・ディレイの基本を網羅しているため、「大澤サウンドの要素をまとめて体感できる」点でコストパフォーマンスに優れています。
こうした代替機材を導入することで、打首獄門同好会の「分厚くもキャッチー」なサウンドを比較的安価に体験できます。重要なのは、機材に頼りすぎず「アンプ本来の歪みを活かす」ことと、ピッキングの強弱によるニュアンスコントロールを意識することです。これによって、たとえ廉価機材であっても大澤のサウンドにグッと近づけるといえるでしょう。
| 種類 | 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギター | Epiphone Les Paul Standard | Epiphone | Amazonで探す | 打首獄門同好会 | 大澤敦史 | Gibsonの廉価版として人気。中域を調整することでレスポールデラックスの硬質トーンに近づけられる。 |
| ギター | Squier Classic Vibe Stratocaster | Squier (Fender) | Amazonで探す | 打首獄門同好会 | 大澤敦史 | 明るく抜けの良いサウンドが得られる。Fender Stratocasterの代替として有効。 |
| アンプ | Marshall DSL20CR | Marshall | Amazonで探す | 打首獄門同好会 | 大澤敦史 | 小出力ながら本格的な真空管サウンド。自宅練習からライブまで対応可能。 |
| エフェクター | BOSS SD-1 Super OverDrive | BOSS | Amazonで探す | 打首獄門同好会 | 大澤敦史 | Marshallの歪みをブーストする定番。大澤のリードトーンに近づけるための必須ペダル。 |
| エフェクター | Pro Co RAT2 | Pro Co | Amazonで探す | 打首獄門同好会 | 大澤敦史 | 分厚いディストーションサウンドを提供。リフ中心の楽曲で有効。 |
| マルチエフェクター | BOSS GT-1 | BOSS | Amazonで探す | 打首獄門同好会 | 大澤敦史 | Marshall系アンプシミュレーションや空間系がまとまった一台。初心者に最適。 |
総括まとめ【打首獄門同好会・大澤敦史】

大澤敦史のサウンドは、一言で表すなら「直球で骨太、しかしキャッチー」という表現が最も近いでしょう。王道のMarshallアンプを土台に、Gibson Les Paul Deluxeの硬質で厚みのあるトーンを活かし、そこにプレイのダイナミクスを乗せることで、打首獄門同好会らしいユーモラスかつ迫力満点のサウンドが完成しています。
彼の音作りの本質は、決して複雑なエフェクトチェインではなく、「アンプ本来の歪み」と「ギター本体の個性」を最大限に引き出すことにあります。オーバードライブやディレイといったエフェクターは補助的に使うだけで、あくまで主役はMarshall DSL100やSV20Hといった真空管アンプの持つ王道サウンド。そこに強めのピッキングやリズム感のあるリフワークを組み合わせることで、唯一無二の存在感を放っています。
また、彼のEQバランスの取り方やミックスの工夫は、ベースとの住み分けを意識した「中域重視」のアプローチが鍵です。低域を支配するのはリズム隊、ギターは中域から上をしっかりと確保する。この明確な役割分担があるからこそ、3ピースでありながら音圧に不足を感じさせない分厚いバンドサウンドが実現しています。
初心者がコピーする際には、Marshall系の小型アンプやEpiphoneのレスポールを用い、BOSS SD-1でリードを押し出すだけでも大澤らしさを再現可能です。重要なのは機材の豪華さではなく、「シンプルなセットをどこまで使いこなすか」という視点です。むしろピッキングニュアンスやコードの刻み方を徹底的に研究することで、本質的な部分に近づけるはずです。
総じて、大澤敦史の音作りは「直球勝負のサウンドメイク」と言えるでしょう。複雑な音色変化や派手なエフェクトに頼らずとも、ギター・アンプ・ピッキングの三位一体で強烈な個性を放つスタイルは、多くのギタリストにとって大いに参考になるはずです。彼のサウンドを目指すことで、プレイヤー自身の基礎力や表現力を磨くきっかけにもなるでしょう。
下記恐らく使用(所持)している機材のまとめです。参考までに!
ギター
Gibson Les Paul Deluxe(ゴールドトップ)
画像で確認できるメインギター。ミニハムバッカーを搭載したモデルで、硬質でありながらも厚みのあるロックサウンドが特徴。骨太なリフや伸びのあるソロに適している。
(推測)Fender Stratocaster American Vintageシリーズ
公演やインタビューで使用が確認されることがあるモデル。明るく抜けの良いサウンドを狙う際に登場する。
アンプ
Marshall JCM2000 DSL100(フルサイズヘッド)
ステージ画像から確認。王道ブリティッシュロックの歪みを提供し、芯のあるパワフルなサウンドを作る。クランチ〜ハイゲインまで幅広く対応。
Marshall SV20H Studio Vintage
近年導入された20Wのコンパクトヘッド。本人コメントでは「20Wとは思えないパワーと抜けの良さ、可愛い見た目もお気に入り」と語られている。ライブ・レコーディング双方で使用。
キャビネット
Marshall 1960系 4×12キャビネット(推定)
ヘッドアンプと組み合わせて使用。豊かな低域と広がりのある音圧を実現。
Fender系コンボアンプ(詳細不明)
写真右にFenderスタイルのアンプも確認でき、曲や会場によって使い分けている可能性あり。
エフェクター
※画像からはペダルボード全体は確認できず。ただし、SIX LOUNGEのサウンド特性から推測される代表的なペダルは以下。
オーバードライブ(BOSS SD-1やOD-3など)
ディストーション/ファズ(Big MuffやRAT系)
ディレイ(BOSS DDシリーズやMXR Carbon Copyなど)
音作りの特徴
ヤマグチユウモリさんのサウンドは、シンプルながら力強く、ロックンロールの真髄を突く直球型。アンプの歪みを主体にし、ギター本体の個性を活かす設定が多い。SV20Hのような小出力アンプでも十分な音圧を引き出すのは、ピッキングの強さとEQバランスの妙によるものと考えられる。