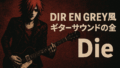始めに(特徴紹介)
Ronnie Wood(ロニー・ウッド)はThe Faces(ザ・フェイセズ)のギタリストとして、荒々しくもグルーヴィーなギターサウンドを生み出したことで知られています。彼のギターはローリング・ストーンズ時代とはまた異なり、よりルーズでブルージー、かつスライドを多用した粘り気のあるトーンが特徴的です。
代表曲「Stay with Me」では、歪んだアンプをフルアップさせ、独特のオープンチューニングを活かしたスライドフレーズが炸裂します。その音は決して過剰に作り込まれたものではなく、ギターとアンプを直結し、音量と指のニュアンスでコントロールするクラシックなロックギタリストのスタイルそのものです。
Faces時代のRonnieは、ZemaitisのカスタムモデルやAmpegの巨大アンプを用い、爆音ながらもバンド全体と溶け合う音を作り出しました。シンプルな構成でありながら、彼のギターサウンドは唯一無二で、多くのロックギタリストに影響を与えています。
また、Ronnie自身のプレイスタイルも魅力的です。コードを崩しながらリズムを刻み、必要なときに鋭いスライドフレーズを差し込むことで、ロッド・スチュワートのボーカルやバンドの荒削りなサウンドを引き立てています。
こうした理由から、The Faces時代のロニー・ウッドの音作りは、シンプルながら奥深い「ロックギターの原点」として今も研究対象となっています。
使用アンプ一覧と特徴【The Faces・Ronnie Wood】
Ronnie Wood(ロニー・ウッド)がThe Faces時代に愛用したアンプは、当時の爆音ロックサウンドを象徴するものが揃っていました。彼のスタイルは、基本的にギターをアンプに直結し、アンプをフルアップさせて得られる自然なドライブ感を活かすものでした。外部エフェクターを多用せず、アンプとギター本体のコントロールで音を作り出す姿勢は、クラシックロックの真髄とも言えます。
特に重要なのはAmpeg V-4やSVTのような大型アンプです。V-4は100Wクラスのヘッドで、爆音ながらも中域のパンチと太さを兼ね備えています。一方SVTはベース用として有名ですが、Faces時代にはギター用としても使われており、その圧倒的なローエンドとパワーでステージを支えていました。VT-22やVT-40といったAmpegのコンボタイプも確認されており、スタジオ録音や小規模会場での選択肢として重宝されていたと考えられます。
また、イギリス録音時にはHiwatt DR103(1969年製)とSE4122キャビネットを用いたことも知られており、「Stay with Me」のレコーディングではこの組み合わせが重要な役割を果たしました。Hiwattはクリーンながらも硬質なアタック感が特徴で、スライドギターのニュアンスを鮮明に引き出してくれます。
加えて、Fender系アンプも使用されており、特にChamp、Princeton、Deluxe Reverbといったシルバーフェイス期の小型コンボが挙げられます。これらはボリュームを上げることで、独特の温かみとクランチ感を得られるため、ラフでブルージーなFacesサウンドと相性が良かったと推測されます。Fender TwinはLap Steelとの組み合わせで使用されたとされ、さらにVox AC30は英国レコーディング時に登場した可能性が高いといわれています。
総じて、Ronnie Woodは「爆音アンプをフルアップさせてギターのボリュームでコントロールする」というスタイルを徹底しており、現代のギタリストが真似をする際にもその点が重要なポイントになります。こうしたアンプの使い分けにより、ライブとスタジオで異なる音色を表現していた、と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| V-4 | Ampeg | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | メインで使用された大型ヘッドアンプ、爆音かつ中域の押し出しが特徴 |
| SVT | Ampeg | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | 本来はベース用だが、ギターにも使用し極太サウンドを実現 |
| VT-22 / VT-40 | Ampeg | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | コンボ型アンプ、スタジオや中規模会場での選択肢 |
| DR103 | Hiwatt | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | 1969年製、Stay with Meで使用。Faneスピーカー搭載キャビと組み合わせ |
| Champ (Silver-face) | Fender | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | 小型アンプながらフルアップで独特のクランチを獲得 |
| Princeton (Silver-face) | Fender | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | シルバーフェイス期の定番コンボ、レコーディングにも適した音色 |
| Deluxe Reverb | Fender | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | 温かみのあるクランチサウンド、バンドサウンドに溶け込みやすい |
| Twin Reverb | Fender | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | Lap Steelとの組み合わせで使用されたとされる |
| AC30 | Vox | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | 英国レコーディング時に使用された可能性あり |
使用ギターの種類と特徴【The Faces・Ronnie Wood】

Ronnie Wood(ロニー・ウッド)のFaces時代のサウンドを語る上で欠かせないのが、彼の愛用したギター群です。ロニーは基本的に「シンプルな直結スタイル」で演奏していましたが、ギターの種類やチューニングの使い分けによって多彩なトーンを引き出していました。その中心となったのがZemaitis製のカスタムモデルです。
特に有名なのはZemaitis Disc Front Model(1972年製)で、3基のGibson PAFハムバッカーを搭載し、アルミニウム製のピックガードにはトレブルブースターが内蔵されていました。このギターはオープンEチューニングにセットされ、スライドギターとしての使用が多く確認されています。ブースターを活かしてアンプをさらにプッシュし、切れ味のあるサウンドを得ていたのが特徴です。
さらに、1971年製のZemaitis Metal Front Modelもステージで使用されており、派手なルックスと強烈な中域の押し出しでバンドサウンドを支えていました。Zemaitisのギターはロニーの象徴ともいえる存在であり、その後のキャリアでも彼のサウンドの基盤を作りました。
また、透明なボディで知られるAmpeg Dan Armstrong Luciteも使用され、こちらもオープンチューニングでのスライドプレイに活躍しました。透明なアクリルボディの独特なサステインと煌びやかさは、Facesのライブでひときわ目立つ存在でした。
加えて、ロニーは1955年製と1956年製のFender Stratocasterを所有しており、特に1955年製はワーナーから贈られたもので「#1ギター」として重宝されていました。ノントレモロ仕様で、安定したチューニングと明瞭なアタック感を実現していました。1953年製のFender EsquireやLap Steelもライブやレコーディングで用いられ、幅広い音色を生み出す助けとなっていました。
アコースティックではGibson Superが確認されており、バラードやセッション的な場面で用いられています。また、Faces時代のサウンド全体を支える要素として「ハムバッカー搭載ギター全般」が重要であり、太く芯のある歪みを作り出す上で不可欠でした。
これらのギターの選択は、ライブの爆音環境でも音が埋もれず、かつスライドやリズムのニュアンスを的確に伝えるためのものと考えられます。総じて、Zemaitisを中心とした多彩なギター群によってロニー・ウッド独特のFacesサウンドが成立していた、と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | ギターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemaitis Disc Front Model (1972年製) | Zemaitis | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | エレキギター | PAFハムバッカー3基、内蔵トレブルブースター、スライド用にオープンEで使用 |
| Zemaitis ’71 Metal Front Model | Zemaitis | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | エレキギター | 派手なルックスと強烈な中域、ライブのメイン機材のひとつ |
| Dan Armstrong Lucite | Ampeg | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | エレキギター | 透明ボディ、オープンチューニングでのスライド演奏で活躍 |
| Stratocaster (1955年製, 1956年製) | Fender | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | エレキギター | 1955年製はワーナーから贈られた#1ギター、ノントレモロ仕様 |
| Esquire (1953年製) | Fender | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | エレキギター | 初期フェンダーシングルピックアップモデル、ロックンロール黎明期のサウンド |
| Lap Steel | Fender | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | ラップスティールギター | スライドプレイで多用、Fender Twinと組み合わせることが多かった |
| Super (アコースティック) | Gibson | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | アコースティックギター | バラードやセッションで使用されたアコースティックモデル |
| ハムバッカー搭載ギター全般 | Gibson/Fender/Zemaitis等 | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | エレキギター | Faces時代の歪みサウンドを支えた要素 |
使用エフェクターとボード構成【The Faces・Ronnie Wood】
Ronnie Wood(ロニー・ウッド)のFaces時代のサウンドにおいて、エフェクターは実はほとんど使用されていませんでした。これは当時のロックギタリストとしては珍しくなく、アンプをフルアップさせて得られる自然な歪みと、ギター本体のトーン/ボリュームコントロールで音を作るという極めてシンプルなスタイルでした。したがって、現在のように複雑なペダルボードを構築していたわけではなく、サウンドの核は「ギター+アンプ」に集中していたと言えます。
ただし例外として、Zemaitisギターに内蔵されていたジャーマニウムトランジスタ系トレブルブースターは重要な存在です。これによってアンプの入力を押し込み、より鋭いアタックとサステインを得ることができました。特にオープンEチューニングでのスライドプレイでは、この内蔵ブースターが大きな役割を果たし、Faces特有の鋭くも粘りのあるトーンを実現しています。
外部ペダルについては、Faces期の明確な使用証拠はほぼなく、「ブースター以外は使っていない」と言って差し支えないでしょう。しかし後年、ロニー自身のサウンドを再現する目的で開発されたBSM RW-F Treble Boosterが登場しました。これはFaces期のトーンを求めるファンやギタリストのために設計されており、当時の内蔵ブースターの特性を再現しています。ライブでFacesサウンドを再現する際には、このペダルが最も効果的といえるでしょう。
つまり、Ronnie WoodのFaces時代のペダルボードは「ほぼ存在しない」と言ってよく、その代わりにアンプを最大出力にしてギターで音量を調整する「原始的かつ本質的なロックギターの音作り」が徹底されていました。現代のギタリストが彼の音を再現するには、ブースターをひとつ加える程度のシンプルなセットアップで十分、と想定されます。
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【The Faces・Ronnie Wood】

Ronnie Wood(ロニー・ウッド)のFaces時代の音作りの本質は「アンプ直結+爆音フルアップ」に尽きます。エフェクターをほとんど使わない彼にとって、音色を決定づけるのはギターとアンプ、そしてPAやレコーディング時のマイキングでした。そのため、ギタリストとして彼のサウンドを再現するには、アンプとEQの扱い方、さらにバンドアンサンブルの中でどう音を抜けさせるかが極めて重要となります。
まずアンプのセッティングですが、Ampeg V-4やSVTなどの大型アンプは、基本的にボリュームを限界まで上げることで自然なドライブを得ています。トーンコントロールは大きく動かさず、ミドルをやや強調して存在感を出すことが多かったと推測されます。Hiwatt DR103を使用した際も、基本は同様で、クリーン寄りの硬質なサウンドにアンプの歪みが乗ることで、「Stay with Me」で聴けるような豪快で切れ味のあるトーンが完成していました。
EQの工夫としては、ギターのボリュームとトーンを常に手元で調整していた点が重要です。フルボリュームで激しいリフを鳴らし、歌のパートではボリュームを絞って軽く歪んだクランチにする、という具合に、アンプ側を触るのではなくプレイ中の指先操作でダイナミクスをコントロールしていました。このダイナミクスの付け方こそが、シンプルな機材構成にもかかわらず立体感のあるサウンドを生み出す秘密でした。
曲ごとの使い分けも明確で、例えば「Stay with Me」ではHiwatt+スライドで鋭く抜けるトーンを、「Miss Judy’s Farm」ではAmpegの分厚いミドルとZemaitisのハムバッカーで爆音リフを刻む、といったアプローチが確認できます。アコースティック曲ではGibson Superを使い、温かみのあるバッキングでロッド・スチュワートの歌声を支えていました。
レコーディングにおいては、マイキングも重要でした。AmpegやHiwattの爆音アンプを収音するため、Shure SM57のような定番マイクをキャビネットに近接しつつ、ルームマイクで空気感を収録する手法が採られていたと考えられます。Facesのアルバムを聴くと、ギターサウンドに独特の空気感があり、これは当時のアナログ録音環境とマイク配置の妙によるものです。
ミックス段階では、ロニーのギターは左右に広がることもあれば、ロッドのボーカル横に寄せてパンニングされることもありました。特にライブ感を重視したFacesの音源では、ギターが多少荒削りでもバンド全体に馴染むことが優先され、過度なEQやコンプレッションは避けられていたようです。この「粗さ」が逆に魅力となり、現代のリスナーにも生々しさを感じさせます。
まとめると、Ronnie WoodのFaces時代の音作りは、EQやエフェクトで作り込むのではなく、アンプをフルアップし、ギター本体と演奏のニュアンスでコントロールすることが核心でした。そして録音やミックスではシンプルな手法でバンド全体のエネルギーを前面に押し出すことが重視されていた、と想定されます。
比較的安価に音を近づける機材【The Faces・Ronnie Wood】
Ronnie Wood(ロニー・ウッド)のFaces時代の音作りを完全に再現するには、ZemaitisのカスタムモデルやAmpeg V-4といった高価で希少な機材が必要になります。しかし、現代のギタリストが同じニュアンスを得るためには、もっと手軽で比較的安価な代替機材を選ぶことが可能です。ここでは初心者〜中級者でも導入しやすいモデルを紹介し、その理由を丁寧に解説します。
まずギターについてですが、ロニーのサウンドを決定づけていたのはハムバッカー搭載のZemaitisやストラト系の明瞭なアタックでした。これを再現するなら、エントリーモデルのレスポールタイプ(Epiphone Les Paul Standardなど)が効果的です。太い中域と豊かなサステインが得られ、Faces特有の粘りあるクランチに近づきます。さらに、Fender Player Stratocasterシリーズのような手頃なストラトを併用すれば、ロニーの持つ「ストラトとハムバッカーの両方を使い分ける」サウンドを再現できます。
アンプに関しては、Ampeg V-4やHiwatt DR103は現実的に高額かつ爆音仕様なので、現代では小型コンボで代用するのが良いでしょう。具体的には、Fender Blues JuniorやBoss Katanaシリーズが候補です。前者はフェンダーらしい温かみのあるクランチが得られ、後者はモデリング機能でHiwattやAmpeg系の音色をシミュレートできます。特にBoss Katanaは価格帯も手ごろで、家庭練習からライブまで幅広く対応できる点が魅力です。
エフェクターについては、ロニーが多用したのはブースターのみなので、安価なトレブルブースターやオーバードライブで代用可能です。例えば、BOSS SD-1 Super OverDriveを軽くかけることで、アンプを押し込む効果を再現できます。また、TC Electronic Spark Boosterのようなペダルも透明感あるプッシュサウンドを作るのに適しています。これにより、ギターとアンプを直結した時の「もうひと押し」が得られ、Faces時代の粗削りなトーンに近づきます。
総じて、ロニー・ウッドの音作りを現代的かつ手頃に再現するためには、「ハムバッカー搭載ギター+小型コンボアンプ+シンプルなブースター」という構成が最適です。複雑なエフェクトボードを用意する必要はなく、むしろシンプルさが彼のサウンドを再現する近道になります。これらの機材を組み合わせることで、初心者でもリーズナブルにThe Facesのサウンドに近づくことができるでしょう。
| 種類 | 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギター | Les Paul Standard | Epiphone | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | ハムバッカー搭載で太い中域が得られ、Zemaitis代替に最適 |
| ギター | Player Stratocaster | Fender | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | ストラト特有の明瞭なアタックで、1955年製ストラトの代替として有効 |
| アンプ | Blues Junior | Fender | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | フェンダー系クランチが得られる小型コンボ、家庭でも扱いやすい |
| アンプ | Katana-50 MkII | BOSS | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | 多彩なアンプモデリングでAmpegやHiwatt系サウンドを再現可能 |
| エフェクター | SD-1 Super OverDrive | BOSS | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | アンプを軽くブーストし、Faces特有の粘りある歪みを再現 |
| エフェクター | Spark Booster | TC Electronic | Amazonで探す | The Faces | Ronnie Wood | 透明感あるブーストで、Zemaitis内蔵ブースターの代替として有効 |
総括まとめ【The Faces・Ronnie Wood】

Ronnie Wood(ロニー・ウッド)のThe Faces時代の音作りを振り返ると、その本質は「シンプルさ」と「爆音によるダイナミクスコントロール」に集約されます。ZemaitisのカスタムギターやAmpeg/Hiwattの巨大アンプは確かに希少で特別な存在ですが、それ以上に重要なのは「ギターとアンプを直結し、手元のコントロールで音を操る」という姿勢でした。
代表曲「Stay with Me」に象徴されるように、フルアップさせたアンプにオープンチューニングのスライドギターを叩き込むことで、荒削りながらも圧倒的な説得力を持つサウンドが生まれています。この「荒々しさ」と「ニュアンスのコントロール」の両立こそがロニーの持ち味であり、現在のギタリストが再現を目指す際にも見落とせない要素です。
また、Facesのサウンド全体が持つ「ルーズだけど熱量のあるグルーヴ」は、ロニーのギターが中核となっていました。彼は単にリードギタリストというより、リズムギターとスライドを行き来しながら、バンド全体を支える役割を果たしていたのです。アンプやギターの選択も、その役割に応じて柔軟に切り替えており、結果的に多彩な音色がアルバムやライブで聴けることにつながっています。
読者の皆さんがロニー・ウッドのサウンドを追求する際に大切なのは、「高価な機材を揃えること」よりも、「シンプルな機材で爆音を鳴らし、演奏のニュアンスで表情を作ること」です。ギターのボリュームを絞ってクランチにしたり、開放弦を大胆に使ったスライドを取り入れるなど、プレイスタイルそのものがサウンドに直結しているのです。
現代の環境では、家庭用アンプや手頃なブースターを使っても十分に雰囲気を近づけられますし、むしろ「音作りをシンプルに保つ」ことが彼のスタイルを理解する最短ルートになります。複雑なエフェクトや細かい設定に頼るのではなく、ギターとアンプを信じ、演奏者自身の感覚で音を作る。それがFaces時代のロニー・ウッドの哲学であり、今なお多くのギタリストが学ぶべき姿勢と言えるでしょう。
結論として、Ronnie Woodの音作りの本質は「ギター+アンプ=ロックの原点」です。彼のようにシンプルなセットアップを徹底し、演奏そのものに集中することで、誰でもあの熱量あふれるThe Facesのサウンドに一歩近づくことができるはずです。
下記恐らく使用(所持)している機材のまとめです。参考までに!
🎸 ギター
Zemaitis “Disc Front Model” (1972年製)
・3基のGibson PAFハムバッカー搭載、個別のコントロールとプッシュスイッチ付き
・アルミニウム製ピックガード、内蔵トレブルブースター搭載
・オープンEチューニングでスライド使用が多い
Zemaitis “’71 Metal Front Model”
Ampeg Dan Armstrong Lucite
・オープンチューニングでも使用
Fender Stratocaster (1955年製, 1956年製)
・ワーナーから贈られた1955年製ストラトは#1ギター
・ノントレモロ仕様
Fender Esquire (1953年製)
Fender Lap Steel
Gibson Super (アコースティック)
ハムバッカー搭載ギター全般(Faces時代のサウンドの要素)
🔊 アンプ
Ampeg
・SVT, V-2, V-4, VT-22, VT-40
・特にV-4とSVTが主要使用機種
Hiwatt DR103 (1969年製, 100Wヘッド)
・SE4122 4×12キャビネット(Fane 122142スピーカー搭載)
・「Stay with Me」のレコーディングで使用
Fender Champ (Silver-face)
Fender Princeton (Silver-face, drip-edge)
Fender Deluxe Reverb
Fender Twin(Lap Steelと併用)
Vox AC30(英国でのレコーディングで使用可能性あり)
小型アンプ(Tweed Champ等)
アンプをフルアップで使用するスタイル
🎛 エフェクター / ブースト
Zemaitis内蔵ブースター(ジャーマニウムトランジスタ系トレブルブースター)
BSM RW-F トレブルブースター(後年、Faces時代のサウンド再現用に開発)
備考:Faces時代は外部エフェクトはほとんど使わず、大音量アンプ+ギター本体コントロールで音作り