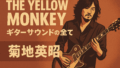始めに(特徴紹介)
ナナホシ管弦楽団は、ボカロシーンやアニメ楽曲を中心に独自の世界観を展開するサウンドクリエイターとして知られています。特にテクニカルなギターリフやメタル的なアプローチを取り入れたハードロック寄りのサウンドは、多くのリスナーを魅了してきました。
カロンズベカラズ名義でも活動し、重厚なリフと疾走感のあるアンサンブルを特徴としています。エモーショナルかつキャッチーなメロディーと、プログレッシブな構成力が融合した楽曲は、DTMベースで制作されながらも生演奏的な迫力を持っています。
代表的なサウンドの例として、ギターは鋭く歪ませつつもコード感が潰れないセッティングで、ボカロのハイトーンボーカルやオーケストラアレンジを支える骨格を形成しています。こうした音作りは、Sago Ymirのようなメタル志向ギターや、Ableton LiveといったDAW内での処理によって実現されていると考えられます。
このページでは、ナナホシ管弦楽団の音作りをギター、アンプ、エフェクター、そしてミックス処理まで徹底解説し、再現のために必要な機材や設定を紹介していきます。リスナーやギタリストにとって「どうやってあの音を出しているのか?」を紐解く一助となるでしょう。
使用アンプ一覧と特徴【ナナホシ管弦楽団】
ナナホシ管弦楽団のサウンドにおいて、実際の真空管アンプよりもデジタル環境をベースにした「イン・ザ・ボックス」の制作が主体であると明言されています。具体的には、Ableton Liveを中心とした宅録スタイルで、ドラムにはBFDを用い、ギターもアンプ実機よりもプラグインやモデリングアンプを使用している可能性が非常に高いとされています。
この背景には、自宅やスタジオ環境で効率的に制作を進めるための合理性があります。例えば、プラグイン型のアンプシミュレーターを使用することで、深夜帯でも大音量を必要とせず、即座にプリセットを呼び出して音を再現できるメリットがあります。また、モデラー(Line6 Helix、Fractal Axe-Fx、Kemperなど)を活用すれば、メタル的なディストーションからクリーントーンまで自在に切り替えることが可能です。
一方で、ライブ演奏においては実機アンプが必要となる場合も考えられます。近年のバンドシーンでは、ヘッドアンプ+キャビネットを運ぶ代わりに、コンパクトなモデラーをPA直結で使用するケースが増えており、ナナホシ管弦楽団もその流れを踏襲していると推測されます。実際に、音源で聴けるサウンドは、マーシャル系の中域が前に出る質感や、メサブギー系のタイトでヘビーな低域が感じられるため、プラグイン内でこれらのキャラクターを再現していると考えられます。
特にメタルやラウド系のギタリストがよく選ぶアンプシミュレーターとしては、「Neural DSP」「BIAS FX」「Amplitube」などが有名で、これらはAbleton Liveと相性が良いため、ナナホシ管弦楽団が採用している可能性は高いでしょう。宅録に特化したサウンドメイクの効率化を重視した機材選び、と言えるかもしれません。
以下の表は、ナナホシ管弦楽団で想定される使用アンプ・アンプシミュレーターをまとめたものです。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラグイン型アンプシミュレーター | Neural DSP / Positive Grid など | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | Ableton Live内での制作に多用されると考えられる。宅録向け。 |
| Kemper Profiling Amplifier | Kemper | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | ライブ運用でも人気。多彩なアンプモデルを収録。使用の可能性あり。 |
| BIAS FX 2 | Positive Grid | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | ソフトウェア型モデラー。Ableton Liveと組み合わせやすい。 |
| Amplitube 5 | IK Multimedia | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | 幅広いアンプとキャビネットを収録。宅録層での定番。 |
以上のように、ナナホシ管弦楽団のアンプ環境は従来型の真空管アンプではなく、プラグインやモデリング系機材を中心に構築されていると想定されます。
使用ギターの種類と特徴【ナナホシ管弦楽団】

ナナホシ管弦楽団が使用するギターは、いずれもハードロックやメタルを基盤としたサウンドを支える仕様となっています。特にテクニカルなリフや速弾き、重厚なリズムギターを表現するため、ミドル〜ハイゲインとの相性が良いモデルが多いのが特徴です。
メイン機材として確認されるのが「Sago Ymir(ヤミル)」です。これは関西発のギターブランドSagoが展開するテクニカル志向のコンセプトモデルで、メタルやプログレッシブ系ギタリストを意識した仕様となっています。ピックアップや木材構成によるタイトな低域と、鮮明な高域が特徴で、ボカロ曲に多い速いテンポや複雑なコード感を支えるのに非常に向いているギターです。
さらに、「EDWARDS e-ZUKAモデル」も使用が確認されています。これはGRANRODEOの飯塚昌明のシグネチャーモデルで、7弦や高出力ハムバッカーを搭載することで、ラウドな音楽に適したパワフルなサウンドを実現します。ナナホシ管弦楽団が重厚なサウンドを求める際に採用していると考えられます。
また、BURNY製のレスポールタイプ(ブラック)も使用。こちらは型番未確認ながら、伝統的なレスポールサウンドを活かしつつ、リードやリフの骨格として活用していると推測されます。レスポール特有の粘りのある中域は、ボカロやオーケストラのサウンドに埋もれず存在感を発揮します。
こうした選択からも、ナナホシ管弦楽団は「最新型のテクニカルモデル」と「伝統的なロックギター」の双方をバランス良く用い、楽曲ごとに最適な音色を組み合わせていることがわかります。特に宅録主体のスタイルでは、ギターそのもののキャラクターがミックス全体の輪郭を左右するため、ギター選びの重要度は高いと言えるでしょう。
以下の表は、ナナホシ管弦楽団の使用ギターをまとめたものです。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | ギターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sago Ymir | Sago New Material Guitars | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | ソリッド/メタル志向 | テクニカル系コンセプトモデル。速弾き・重厚リフ対応。 |
| EDWARDS e-ZUKA モデル | EDWARDS(ESP系列) | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | シグネチャーモデル | GRANRODEO飯塚昌明モデル。ハイゲイン向き。 |
| BURNY レスポールタイプ(ブラック) | BURNY(フェルナンデス系列) | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | レスポールタイプ | 型番未確認。粘りある中域が特徴。リードやリフに使用。 |
以上のように、ナナホシ管弦楽団のギターは「モダン」と「クラシック」の両輪を組み合わせて独自のサウンドを構築していると想定されます。
使用エフェクターとボード構成【ナナホシ管弦楽団】
ナナホシ管弦楽団の音作りは、基本的に宅録主体であり、実機のエフェクターボードよりもDAW内でのプラグイン処理を中心に構築されています。公式の発言でも「Ableton Liveを使い、ドラムはBFD、ギターはイン・ザ・ボックスで制作」と明かされており、歪みや空間系はプラグインを用いた処理である可能性が非常に高いです。
このため、具体的な個別エフェクター名は公開されていませんが、ジャンル的な特性や楽曲から推測すると、以下のような処理が行われていると考えられます。まず歪みについては、プラグインやモデラー内の「ディストーション/オーバードライブ」が主体。メタル系のリフではゲインを高めに設定しつつも、モダンなサウンドを維持するためノイズリダクションを併用している可能性があります。
空間系では、リードギターやソロ部分での「ディレイ」や「リバーブ」が強調されています。特にボカロ曲特有の広がりを演出するために、リバーブはホールタイプやプレートタイプが多用されていると考えられます。また、シンセやオーケストラと混ざる場面では、モジュレーション系(コーラスやフェイザー)が音の厚みを補強する役割を担っていると推測されます。
ライブシーンを想定すると、Line6 HelixやFractal Axe-Fxといったマルチエフェクター/モデラーを活用している可能性も高く、宅録環境とそのまま親和性を持たせられるのが利点です。Ableton Liveと連動させれば、シーケンスに合わせてエフェクトのON/OFFを自動制御することも可能で、効率的なサウンド再現が実現できます。
以下の表は、ナナホシ管弦楽団のエフェクター使用傾向を推定したものです。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | エフェクターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラグイン内ディストーション | Neural DSP / Positive Grid | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | ディストーション | Ableton Live上で利用されると考えられる。ハイゲイン用途。 |
| リバーブプラグイン | Valhalla / Waves | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | リバーブ | ホール/プレート系リバーブを多用し、空間的な広がりを演出。 |
| ディレイプラグイン | Soundtoys / Waves | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | ディレイ | リードパートで立体感を強調。テンポ同期で使用。 |
| Line6 Helix | Line6 | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | ギター用マルチエフェクター | ライブでの再現性を考慮した場合、採用の可能性が高い。 |
| Fractal Axe-Fx III | Fractal Audio | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | プリアンプ/アンプシミュレーター | 宅録からステージまで統一した音作りを可能にするプロ仕様。 |
以上のように、ナナホシ管弦楽団は実機ペダルよりも「DAW内エフェクト」「マルチエフェクター/モデラー」を中心とした柔軟な構成で音作りを行っていると想定されます。
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【ナナホシ管弦楽団】

ナナホシ管弦楽団のサウンドの特徴は「ギターが主張しつつも、ボーカロイドやオーケストラと自然に混ざるバランス」にあります。宅録ベースで制作しているため、実際のセッティングはDAW内でのEQ処理やミックス作業が大きな役割を果たしています。
まず、ディストーションギターのEQ設定について。低域(80Hz以下)はベースやキックと競合しやすいためカット気味にし、100〜150Hzあたりを少し持ち上げることで厚みを確保しています。中域(500Hz〜1.5kHz)はボーカルやシンセの存在感とバランスをとるために、ややディップ気味に処理。高域(3kHz〜6kHz)はピッキングのアタック感を強調する帯域で、ギターリフの「切れ味」を演出するためにブーストされていると考えられます。さらに、8kHz以上はシンバルなど高域成分と被るため、必要に応じてスムージングしています。
リードギターの処理では、ディレイとリバーブが重要です。ディレイはテンポシンクを基本とし、左右に軽く振り分けることで立体感を演出。リバーブはホールタイプを浅めにかけることで「広がりはあるが輪郭は残す」という絶妙なバランスを保っています。これにより、ボーカロイドの声が埋もれずに前に出ながら、ギターも存在感を確保できるのです。
リズムギターとリードギターのパンニングも工夫されています。典型的には左右にリズムギターを振り分け(L/Rそれぞれ100%寄せ)、中央にベースとボーカルを配置。その間にシンセやオーケストラが重なるため、ミッドレンジのEQ整理が不可欠です。ギターはややタイトにコンプをかけ、過度にサステインを残さないことで、オーケストレーションのダイナミクスを活かしています。
また、ノイズリダクションの活用も欠かせません。ハイゲイン系サウンドでは必然的にノイズが発生しますが、プラグイン型ゲートやノイズリダクションを適切に使うことで、楽曲全体の透明度を維持しています。ナナホシ管弦楽団の楽曲は速いテンポが多いため、余計な残響やノイズを減らすことで演奏のキレを際立たせています。
ミックス全体では、Ableton Liveのグループトラックを活用して「ギター」「ベース」「ボーカル」「オーケストラ/シンセ」「ドラム」に分け、バスコンプやマルチバンドコンプをかける手法が多用されていると想定されます。これにより、各パートのアタックと余韻をコントロールしつつ、全体を一体感ある仕上がりにまとめています。
代表的な楽曲を分析すると、ギターは必ずしも「前面に出す」わけではなく、ボーカルを引き立てつつ楽曲の土台を支える役割に徹しているのが印象的です。これはロックバンド的なアプローチというより、むしろアレンジャー/コンポーザー的な視点で音を設計している結果といえるでしょう。
最終的に、ナナホシ管弦楽団の音作りの肝は「ギターを主張させすぎずに、必要な帯域でのみ力強さを出す」という点にあります。EQ、パンニング、空間系エフェクトを駆使して、ボーカロイドやオーケストラと共存させるミックス術が独自性を生み出していると想定されます。
比較的安価に音を近づける機材【ナナホシ管弦楽団】
ナナホシ管弦楽団の音作りはプロ仕様のプラグインやモデラーを駆使していると考えられますが、初心者や趣味レベルで同じような雰囲気を再現することも十分可能です。ここでは、1万円〜5万円程度で手に入るコストパフォーマンスの高い機材を紹介します。
まずおすすめしたいのが、BOSSの「GT-1」や「GT-1000CORE」といったコンパクトマルチエフェクターです。これらはアンプシミュレーターとエフェクトを内蔵しており、宅録からライブまで幅広く対応可能です。特にGT-1は2万円以下で購入できるにもかかわらず、ディストーション、ディレイ、リバーブといった基本エフェクトが充実しており、ナナホシ管弦楽団のような厚みのあるメタル/ロックサウンドを手軽に再現できます。
次に、Line6 POD GOも注目すべき製品です。上位機種Helixシリーズの技術を継承しつつ、価格を抑えたモデルで、ナナホシ管弦楽団が想定するデジタルモデリング環境を安価に体験することができます。特に宅録ユーザーにとっては、USBオーディオインターフェースとしても利用できるため、ギターを直接PCに接続してレコーディングできるのが大きな魅力です。
また、プラグイン系では「Positive Grid BIAS FX 2 LE」などのライト版が安価に入手可能です。Ableton LiveやStudio OneなどのDAWに組み込めば、プロが使用する環境に近いセッティングを低予算で再現できます。ギター用オーディオインターフェース(Steinberg UR22CやFocusrite Scarlett Soloなど1〜2万円程度)と組み合わせれば、十分にナナホシ管弦楽団の音作りを模倣できるでしょう。
さらに、アンプを用いた練習環境を整えたい場合は「BOSS Katana Mini」や「NUX Mighty Air」といった小型モデリングアンプがおすすめです。どちらも2〜3万円程度で購入でき、ヘッドホン対応やモバイル接続に対応しているため、宅録や深夜練習にも適しています。
要するに、ナナホシ管弦楽団のようなデジタル主体の音作りは「実機にこだわらず、マルチエフェクターやプラグインを使いこなす」ことが肝になります。初心者は高価な機材に手を出す前に、まずはこうした安価で高性能な機材で練習・研究するのが現実的なステップでしょう。
| 種類 | 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギター用マルチエフェクター | BOSS GT-1 | BOSS | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | 2万円以下で購入可能。歪み〜空間系を網羅。 |
| ギター用マルチエフェクター | Line6 POD GO | Line6 | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | Helix直系のモデリング。USB接続で宅録にも最適。 |
| プラグイン | Positive Grid BIAS FX 2 LE | Positive Grid | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | 安価なソフト版。Ableton Liveに導入可能。 |
| 小型アンプ | BOSS Katana Mini | BOSS | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | 持ち運び可能なモデリングアンプ。練習向け。 |
| 小型アンプ | NUX Mighty Air | NUX | Amazonで探す | ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ) | ナナホシ管弦楽団 | Bluetooth対応。自宅用に最適なワイヤレスモデリング。 |
以上のように、比較的安価な機材でもナナホシ管弦楽団のサウンドに近づけることは十分可能です。特にBOSSやLine6製品は再現性が高く、入門者から中級者まで幅広くおすすめできます。
総括まとめ【ナナホシ管弦楽団】

ナナホシ管弦楽団(カロンズベカラズ)の音作りを振り返ると、その本質は「デジタル環境を最大限に活かした効率的かつ緻密なサウンドデザイン」にあるといえます。伝統的なロックバンドのようにスタジオアンプや実機ペダルを中心にするのではなく、DAW(Ableton Live)やモデリング環境を駆使し、常に再現性の高いトーンを作り出している点が大きな特徴です。
ギターに関しては、モダンメタル志向のSago Ymirやe-ZUKAモデルを用い、速弾きにも耐えるアタック感と、分厚いリフを支える中低域を両立しています。また、BURNYレスポールタイプのようなクラシックな機材も取り入れることで、伝統的なロックのニュアンスを加え、楽曲ごとに異なる表情を演出しています。この柔軟なギター選びこそ、ジャンルの枠を超えて幅広いサウンドを構築できる理由といえるでしょう。
エフェクトやアンプに関しては、プラグインやモデリングを中心とすることで、制作環境の自由度とスピード感を確保。特にリバーブやディレイといった空間系を積極的に使い、ボーカロイドやシンセと違和感なく溶け込む音像を作り上げています。さらに、EQ処理やパンニングの工夫により、ギターが主張しすぎず、それでいて存在感を失わない絶妙なミックスバランスが実現されています。
こうした音作りの背景には「必要な場面で必要な帯域だけを際立たせる」というプロデューサー的な視点があります。ギター単体で聴いて派手すぎない設定でも、全体に混ざると驚くほど効果的に機能するのは、まさにアレンジャーとしての経験に裏打ちされたアプローチといえるでしょう。
これからナナホシ管弦楽団の音に近づけたいと考える人にとって重要なのは、高価な機材を揃えることよりも「EQ処理」「空間系の使い方」「アンサンブルの中での役割」を理解することです。BOSSやLine6といった比較的安価なマルチエフェクターでも、十分にそのエッセンスを再現できます。逆に言えば、機材の豪華さよりも、音作りの哲学や全体設計こそがサウンドの核を成しているのです。
総括すると、ナナホシ管弦楽団の音作りは「デジタルを駆使した合理性」と「ギター本来の表情を活かす柔軟性」が融合したものです。これを理解し、自分の環境で応用していくことが、最短で彼らのサウンドに近づくための鍵になるでしょう。
“`
下記恐らく使用(所持)している機材のまとめです。参考までに!
ナナホシ管弦楽団|使用機材まとめ
ギター
Sago Ymir(ヤミル)
備考:ハードロック/メタル系のテクニカル志向コンセプトモデル。
ウィキペディア
sago-nmg.com
EDWARDS e-ZUKA モデル
備考:GRANRODEO・飯塚昌明シグネチャー系。
ウィキペディア
BURNY レスポールタイプ(ブラック)
備考:型番未確認。
ウィキペディア
アンプ
(想定)プラグイン型アンプシミュレーター/モデラー(具体製品名は未確認)
備考:制作はAbleton Live+BFDの“イン・ザ・ボックス”中心と明言されており、宅録ではアンプ実機よりソフト or モデラー運用の可能性が高い。
ウィキペディア
エフェクター
(想定)DAW内プラグイン/モデラー内蔵エフェクト(具体製品名は未確認)
備考:上記と同じ理由で、歪み/ディレイ/モジュレーション等はソフト処理の可能性。
ウィキペディア
その他(参考情報)
ベース:EDWARDS 明希モデル。
ウィキペディア
DAW/シンセ:Ableton Live を使用。
ウィキペディア
ドラム:BFD(打ち込み)。
ウィキペディア
補足:初音ミクWiki等コミュニティ情報でもギター構成は同様に整理されています(裏取り用途)。