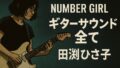始めに(特徴紹介)
シンガーソングライターとしても活動するキタニタツヤは、アニメ主題歌「青のすみか」をはじめ、独特の世界観を持つサウンドで多くのリスナーを魅了しています。
ギタリストとしての彼は、ベーシストとして培ったリズム感とサウンドプロデュース力を強みに、バンド編成でもソロでも存在感を放つトーンを生み出している点が大きな特徴です。
演奏スタイルは、ストラトキャスターを中心にしたクリアで立体感のあるクリーントーンと、Quad Cortexを駆使したアンプシミュレーションによる迫力あるドライブサウンドを両立させることにあります。
また、楽曲によってはアコースティックギター(Taylor)を使い、繊細なアルペジオやコードワークで楽曲全体を彩ります。
特に近年は「ハイファイな曲でバンバン使える」と本人が語ったFender 70th Anniversary American Professional II Stratocasterや、愛称「銀次」と名付けたMomose Stratocasterを中心に、多彩な音色を使い分けていることが確認されています。
ライブでは実機アンプを用いず、Neural DSP Quad Cortexから直接PA卓に送り込むスタイルを採用しており、サウンドの一貫性と再現性を重視した現代的な機材運用が特徴です。
このように、キタニタツヤの音作りは「現代的なマルチエフェクター運用」と「ストラト系ギターの透明感」が大きな軸になっています。
ギタリストとしての彼の強みは、音楽プロデューサー的な視点を持ち込み、必要な音像を的確に設計する点にあるといえるでしょう。
使用アンプ一覧と特徴【キタニタツヤ】
キタニタツヤのライブやスタジオワークにおけるアンプ運用は、従来のロックギタリストとは一線を画しています。
近年のライブ現場では実機アンプを使用せず、Neural DSP Quad Cortexを中核としたデジタル完結のセッティングを採用しています。
この方式では、アンプシミュレーションとキャビネットモデリングを直接PA卓に送り込むことで、安定したサウンドを実現。
特に大型会場やツアーでは、ステージ上の音響環境が一定でなくても一貫したトーンを再現できる利点があります。
本人が使用しているモデルの一例として、Quad Cortex内で「Watt D103 Normal(Hiwatt系アンプ)」と「412 Range PPC V30 ’02キャビ」が採用されており、
これはギターマガジンのライブパッチ紹介記事にも確認されています。
スタジオでのレコーディングにおいても、Quad CortexのプリセットやIR(インパルスレスポンス)を活用し、
クリーンからドライブまで幅広い音作りを可能にしています。従来のマーシャルやフェンダー系アンプを用いた場合に比べ、
デジタルならではの正確な再現性と切り替えの速さが大きな強みとなっているのです。
過去の活動では、具体的な実機アンプの使用例は明確に記録されていませんが、サポートメンバーとのセッションやライブでは、
マーシャルやHiwatt系のサウンドを模したプリセットを積極的に利用しているとされます。
このことからも「実機アンプにこだわらず、必要な音を自由に設計する」という彼のスタンスが見えてきます。
以上から、キタニタツヤのアンプ選びは「実機ではなくモデリング中心」「一貫性と汎用性を優先」という現代的な思想に基づいているといえるでしょう。
よって「Quad Cortexを核にしつつ、Hiwattやマーシャル系サウンドを選択的に使用している」と想定されます。
使用ギターの種類と特徴【キタニタツヤ】

キタニタツヤはシンガーソングライターでありながら、ステージ上ではギタリストとしての存在感も大きく、そのサウンドの核は複数のストラトキャスターとアコースティックギターにあります。
本人の発言やSNSでの投稿を追うと、時期ごとに所有・使用しているモデルがはっきりと分かれており、プレイスタイルや楽曲の方向性に応じて柔軟に使い分けていることが確認できます。
まず注目すべきは、2023年秋に本人が購入を明かしたFender Stratocasterです。彼は「フェンダーのストラトを2本所有している」と発言しており、ライブでもその姿が見られます。
ストラトならではのクリアなサウンドは、アニメ主題歌「青のすみか」をはじめ、ハイファイな楽曲で特に映える傾向があります。
さらに、Fender 70th Anniversary American Professional II Stratocasterについては、本人が「ハイファイな曲でバンバン使える」と語ったことから、現行のライブでも積極的に活用されていると推測されます。
このモデルはFenderの70周年記念として登場した上位機種で、トーンの輪郭が明瞭で、現代的なサウンド設計が魅力です。
また、2019年にはMomose Stratocasterを購入したことをSNSで報告しており、愛称を「銀次」と呼んでいます。この個体は彼の初期キャリアを支え、ライブや動画での使用も多く確認されています。
Momoseは日本のハンドメイドブランドで、丁寧な作りと豊かな鳴りが特徴。彼が愛用する理由の一端が伺えます。
アコースティックギターではTaylorを愛用しており、本人の投稿で「自曲で鳴っているアコギのほぼ全てを担っている」と言及しています。
型番は公表されていませんが、Taylorらしいクリアでバランスの良い鳴りが、彼の繊細なアレンジにマッチしています。
総じて、キタニタツヤのギター選びは「クリアで現代的な音像」を大切にしており、楽曲のハイファイさを強調するための選択が多いといえるでしょう。
そのため、ストラトキャスターを中心に据えつつ、楽曲の情感を表現する際にはアコースティックを使い分けている、と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | ギターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fender Stratocaster | Fender | Amazonで探す | キタニタツヤ | キタニタツヤ | エレキギター | 2023年秋に購入。2本所有と本人発言。 |
| Fender 70th Anniversary American Professional II Stratocaster | Fender | Amazonで探す | キタニタツヤ | キタニタツヤ | エレキギター | 「ハイファイな曲でバンバン使える」と本人談。 |
| Momose Stratocaster(愛称:銀次) | Momose | Amazonで探す | キタニタツヤ | キタニタツヤ | エレキギター | 2019年購入。SNSで報告。愛称「銀次」。 |
| Taylor(型番不明) | Taylor | Amazonで探す | キタニタツヤ | キタニタツヤ | アコースティックギター | 本人投稿で「自曲のアコギのほぼ全てを担っている」と言及。 |
使用エフェクターとボード構成【キタニタツヤ】
キタニタツヤのエフェクター構成は、近年ではNeural DSP Quad Cortexを中心としたデジタル完結型のスタイルが主流となっています。
ライブ・レコーディングを問わず、アンプシミュレーションやキャビネットモデリング、さらには複数のエフェクトチェーンを一括管理できるこの機材を核に、シンプルながらも多彩な音色を表現しています。
特に注目すべきは、Quad Cortexを介したベース・ギター両方の運用です。彼は元々ベーシストとしてもキャリアを持っており、
BOSS BC-1XやStomprox Over Drive Black Labelといったベース用エフェクターを過去のボードに組み込んでいたことが確認されています。
このことからも「低域をしっかり制御しつつ、ハイファイなトーンを維持する」というサウンド哲学が読み取れます。
また、Electro-Harmonix Micro POGやDarkglass Microtubes B7K V2といった機材は、ヨルシカなどのサポート時に使用されていたとされ、
オクターブやプリアンプ的な役割を担い、厚みのあるサウンドを作り出していました。
こうした機材は、ギタリストとしてだけでなく、サウンドプロデューサーとしての柔軟な音作りのスタンスを示しています。
現在のメインであるQuad Cortexは、アンプ・キャビ・エフェクトを一台で完結させることで機材の持ち運びを簡略化し、
ステージやスタジオでの再現性を最大化しています。過去のボード構成に比べて物理的なペダルは減りましたが、
「必要な音をデジタルで正確に呼び出す」という考え方は一貫しています。
総合すると、キタニタツヤのエフェクター構成は「デジタル完結を基盤に、必要に応じてアナログ系を取り入れる」スタイルであり、
彼の楽曲の多彩さと一貫性の両立を支える重要な要素になっていると想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | エフェクターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neural DSP Quad Cortex | Neural DSP | Amazonで探す | キタニタツヤ | キタニタツヤ | ギター用マルチエフェクター | ライブ・スタジオの中核機材。アンプ/キャビ/エフェクトを一括管理。 |
| BOSS BC-1X | BOSS | Amazonで探す | キタニタツヤ | キタニタツヤ | コンプレッサー | 過去のボードに搭載。ベース用コンプとして使用。 |
| Stomprox Over Drive Black Label | Stomprox | Amazonで探す | キタニタツヤ | キタニタツヤ | オーバードライブ | ベース用オーバードライブ。本人ボード写真で確認。 |
| Electro-Harmonix Micro POG | Electro-Harmonix | Amazonで探す | キタニタツヤ | キタニタツヤ | オクターブ | ヨルシカなどのサポート時に使用。音の厚みを追加。 |
| Darkglass Microtubes B7K V2 | Darkglass Electronics | Amazonで探す | キタニタツヤ | キタニタツヤ | プリアンプ/アンプシミュレーター | サポート時のベース用プリアンプ。アタック感を補強。 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【キタニタツヤ】

キタニタツヤの音作りの特徴は、「楽曲に合わせて柔軟に音像を変化させる」ことにあります。
そのため具体的なEQ設定やアンプシミュレーションの選択は曲ごとに異なりますが、共通するのは「ハイファイで立体的なサウンド」を維持している点です。
ここでは、ライブやレコーディングでのセッティング傾向や、エンジニア的な視点での工夫について掘り下げます。
まずEQバランスについて。
クリーントーンではローエンドを控えめにし、100Hz以下を軽くカットして音の輪郭をクリアに整えています。
ミッドはややブースト気味(500Hz~1kHz)に設定することで、ストラトキャスターのシングルコイルらしい張りと存在感を前に出し、
ハイは5kHz付近を持ち上げてきらびやかさを演出していると考えられます。
これにより、バンド全体のアンサンブルの中でもギターが埋もれず、ボーカルの邪魔をしない明瞭なサウンドが形成されます。
ドライブサウンドにおいては、Quad Cortex内のHiwatt系アンプモデル「Watt D103 Normal」を基盤に、
ゲインをミドルに設定し、コンプを軽めにかけることでアタック感と粒立ちを維持しています。
また、ドライブ時にもローを過剰に出さないようにし、ベースとの棲み分けを意識しているのが特徴です。
リフやソロではミッドをさらに押し出し、存在感を強めるセッティングが多く見られます。
アコースティックギター(Taylor)の場合は、録音段階で低域を適度にローカットし、
中高域をブーストしてストロークやアルペジオの繊細さを際立たせています。
本人が「自曲のアコギはほぼ全て担っている」と語るように、レコーディング時にはマイク録りとラインのブレンドを組み合わせ、
立体的なサウンドを構築していると推測されます。
ミックス面での工夫も見逃せません。
エフェクト処理としては、ディレイとリバーブを控えめにかけ、空間的な広がりを加えつつもボーカルを前に出す設計が多いです。
特に「青のすみか」のような壮大な楽曲では、リバーブを深めに設定し、全体にスケール感を与えています。
一方、バンド寄りの楽曲ではドライ気味に仕上げ、タイトで迫力ある印象を強めています。
ライブにおける工夫としては、Quad Cortexのプリセットを楽曲ごとに切り替え、EQ・ゲイン・空間系エフェクトのバランスを曲調に最適化。
これにより、シームレスに音色を変えながらも、全体の音像に統一感を持たせています。
また、PA卓に直結するスタイルのため、会場ごとに異なる音響環境でも一貫した音を提供できる点も強みです。
総じて、キタニタツヤのセッティングは「ローを整理してミッドを押し出し、ハイで煌びやかさを演出」という基本設計を軸に、
楽曲ごとの雰囲気に合わせて細かく調整されているといえるでしょう。
これらの工夫により、彼の音楽は繊細さと迫力を両立させる独自のサウンドを確立している、と想定されます。
比較的安価に音を近づける機材【キタニタツヤ】
キタニタツヤの音作りは、Neural DSP Quad Cortexを中心とした現代的なデジタルシステムに依存しています。
しかしQuad Cortexは高額機材(20万円以上)であるため、初心者やこれから音作りを学びたい方には敷居が高いのも事実です。
そこで、本セクションでは「比較的安価(1万〜5万円程度)」で彼のサウンドに近づけることができる代替機材を紹介します。
大前提として、キタニの音作りの本質は「ハイファイでクリアなクリーン」「粒立ちの良いドライブ」「空間的な広がりを加えるリバーブやディレイ」にあります。
つまり、この3つの要素を揃えることができれば、より安価な機材でもかなり近い質感を再現可能です。
エレキギターの基本トーンを再現するためには、BOSSのマルチエフェクター「GT-1」がおすすめです。
この機材は小型軽量ながら、アンプシミュレーション、EQ、ディレイやリバーブといった空間系を一通り網羅しており、
クリーンからドライブまで幅広く対応可能です。Quad Cortexほどの解像度はありませんが、練習からライブハウス規模まで十分対応できます。
オーバードライブやベース寄りのサウンドを再現したい場合は「BOSS OD-200」や「Darkglass Alpha Omega Ultra」の廉価版である「Darkglass Microtubes X」なども候補になります。
特にOD-200は細かいEQと多彩なドライブキャラクターを持ち、ストラトキャスターと組み合わせることで「青のすみか」風の迫力あるリフも十分表現できます。
アコースティック寄りのサウンドを狙う場合は、空間系が優秀なZOOM G3Xnや、シンプルで扱いやすいBOSS VE-8 Acoustic Singerといったマルチが有効です。
Taylorのような煌びやかなトーンは難しいですが、ライン録り+リバーブを工夫することで雰囲気は十分に近づきます。
最後に、安価に音作りを完結させたい場合は「Positive Grid Spark」や「Line6 POD Go」などのアンプシミュレーター搭載マルチエフェクターも有力な選択肢です。
これらは自宅練習用としても人気があり、アプリ連携によってサウンドを細かく調整できるため、
キタニが重視する「必要な音をシーンに合わせて作る」という思想を体験するには最適です。
まとめると、BOSS GT-1やLine6 POD Goなどの手頃なマルチエフェクターを導入し、
クリーン+リバーブ+適度なドライブを基本軸にすれば、キタニタツヤの音にかなり近づけるでしょう。
「音を自由にデザインする」という彼のスタイルは、必ずしも高価な機材でなければ体験できないものではありません。
| 種類 | 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギター用マルチエフェクター | BOSS GT-1 | BOSS | Amazonで探す | キタニタツヤ | キタニタツヤ | 低価格帯でアンプシミュ〜空間系まで対応可能。 |
| オーバードライブ | BOSS OD-200 | BOSS | Amazonで探す | キタニタツヤ | キタニタツヤ | 多彩なドライブキャラでハイファイな質感を再現。 |
| ギター用マルチエフェクター | ZOOM G3Xn | ZOOM | Amazonで探す | キタニタツヤ | キタニタツヤ | 空間系が充実。アコギやクリーンで効果的。 |
| アンプシミュレーター | Line6 POD Go | Line6 | Amazonで探す | キタニタツヤ | キタニタツヤ | 練習〜ライブまで汎用性高いマルチ。QCの廉価代替。 |
| アンプシミュレーター | Positive Grid Spark | Positive Grid | Amazonで探す | キタニタツヤ | キタニタツヤ | アプリ連携可能。自宅練習に最適。 |
総括まとめ【キタニタツヤ】

キタニタツヤの音作りを振り返ると、その本質は「楽曲に寄り添った音像設計」と「現代的なデジタル運用」の融合にあります。
従来のロックギタリストのように特定の実機アンプやペダルに固執するのではなく、必要な音をシーンごとに柔軟に構築するアプローチを徹底している点が特徴的です。
使用ギターについては、ストラトキャスターを中心に据え、Momose「銀次」やFender 70th Anniversary Stratocasterといった個性的な個体を使い分けています。
さらにTaylorのアコースティックを加えることで、バンドサウンドから弾き語りまで幅広い音楽性をカバーできる構成になっています。
これらは「クリアでハイファイ」という共通の軸を持ち、どの曲でも一貫性を保ちながらも多彩な表情を見せています。
エフェクターやアンプに関しては、Neural DSP Quad Cortexを中心に構築し、デジタル上でアンプ・キャビ・空間系を完結させるスタイルが確立されています。
特にライブにおいてはPA卓へダイレクトに送ることで、環境に左右されず安定したサウンドを提供しており、
「再現性」と「効率性」を両立させた現代的な機材運用といえるでしょう。
音作りの思想としては、EQでローを整理し、ミッドを押し出し、ハイで煌びやかさを演出することが基本軸となっています。
そこにリバーブやディレイを適度に加え、楽曲の世界観を支えるサウンドスケープを形成しているのです。
これは単なるギターサウンドにとどまらず、楽曲全体のアレンジやミックスにまで及ぶ「プロデューサー的視点」に裏打ちされています。
また、初心者やファンが彼の音を再現する場合も、必ずしも高価な機材を揃える必要はありません。
BOSS GT-1やLine6 POD Goといった手頃なマルチエフェクターを用いれば、
彼の音作りのエッセンスである「ハイファイさ」「クリアさ」「柔軟な音色切り替え」を十分に体感できます。
総じて、キタニタツヤの音作りは「サウンドそのものが音楽の世界観を表現する」という姿勢に集約されます。
機材に依存するのではなく、表現したい音像に合わせて最適な手段を選ぶ柔軟性こそが、彼のサウンドを唯一無二のものにしているのです。
そのアプローチは、現代の音楽制作における新しいスタンダードを示していると言っても過言ではないでしょう。
“`
下記恐らく使用(所持)している機材のまとめです。参考までに!
🎸ギター
Fender Stratocaster(2023年秋に購入と本人談。フェンダーのストラトを2本所有と発言)
フェンダーニュース
Fender 70th Anniversary American Professional II Stratocaster(試奏コメントあり。「ハイファイな曲でバンバン使える」)
フェンダーニュース
Momose Stratocaster(2019/4、本人が購入報告。愛称「銀次」)
X (formerly Twitter)
Taylor(アコースティック)(「自曲で鳴っているアコギのほぼ全てを担っている」と本人投稿。型番は未公表)
X (formerly Twitter)
+1
🔊アンプ
近年はNeural DSP Quad Cortex中心運用(アンプ/キャビはモデリング、PA卓へダイレクト)とまとめられている。
Rittor Music
機材図鑑
QC内でWatt D103 Normal(Hiwatt系)+412 Range PPC V30 ’02キャビ・モデルを使用(「青のすみか」ライブ想定パッチ)。
ギター・マガジンWEB|Guitar magazine
🎛️エフェクター
Neural DSP Quad Cortex(ギター/ベース兼用。近年ライブの中核)
機材図鑑
BOSS BC-1X(過去のボード。ベース用コンプ/本人ボード写真出典)
DTMBOARD
Stomprox Over Drive Black Label(過去のボード。ベース用OD/本人ボード写真出典)
DTMBOARD
Electro-Harmonix Micro POG、Darkglass Microtubes B7K V2 ほか(ヨルシカ等サポート時のベース用。キタニのサポート機材紹介記事)
サウンドハウス