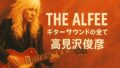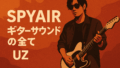始めに(特徴紹介)
The Who(ザ・フー)のギタリスト、Pete Townshend(ピート・タウンゼント)は、ロック史において革新的なサウンドとパフォーマンスで知られる存在です。 彼の代名詞といえば、ギターを振り回す“ウィンドミル奏法”、そしてライブでのダイナミックな破壊的パフォーマンスですが、その背後には独自のサウンド構築があります。
サウンド面では、骨太なコードワークとアグレッシブなリズムギターが特徴です。単なる伴奏にとどまらず、ギター自体がリード楽器としてバンドを牽引するスタイルを確立しました。 代表的な楽曲で言えば、『My Generation』における荒々しいパワーコード、『Pinball Wizard』での12弦ギターの煌びやかなサウンド、『Baba O’Riley』や『Won’t Get Fooled Again』における重厚なアンプサウンドが挙げられます。
また、60年代にはRickenbackerやFender Telecasterを使用し、クリアかつ鋭いサウンドでリズムを刻みました。70年代に入るとGibson SG SpecialやLes Paul Deluxeで厚みのある中域を強調し、Hiwattアンプと組み合わせてパワフルかつ立体的な音像を生み出しています。 80年代以降はFender Eric Clapton Stratocasterをメインとし、コンプレッションを効かせたクリーン〜クランチサウンドへと変化しながらも、常にアンサンブルの中心に立ち続けました。
ピートのサウンドは単なる機材の選択だけでなく、アンプのEQ設定やエフェクトの使い分け、さらにはバンド全体の音響設計に強く影響しています。 そのため、彼の音作りを理解することは「ロックギターの進化」を理解することにもつながります。
以下では、ピート・タウンゼントが実際に使用してきたアンプ、ギター、エフェクターを時系列と特徴ごとに整理し、さらに現代のプレイヤーが彼の音を再現するための具体的な機材選びやセッティング方法を解説していきます。
使用アンプ一覧と特徴【The Who・Pete Townshend】
Pete Townshend(ピート・タウンゼント)のサウンドを語る上で欠かせないのが、強烈な音圧とレンジの広さを誇るアンプ群です。 The Whoのライブは「史上最も大音量のバンド」と称されるほどであり、その中心にはHiwattをはじめとしたアンプの存在があります。
60年代前半には、Fender Proヘッド(1964–65)やFender Showmanを用い、TelecasterやRickenbackerと組み合わせることで鋭くもクリアな音を作っていました。 特にFender Showman+2×15キャビネットの組み合わせは、アメリカツアーでのライブ用セッティングとして知られています。
1965年頃にはVox AC-100を使用し、さらにUS Thomas Organ社の“Super Beatle”も北米ツアーで確認されています。 その後、Sunnアンプを一時期使用したほか、1967年〜68年にはSound City L100を採用。これは後にHiwattアンプ誕生のベースとなった回路構成で、タウンゼントの爆音志向を支える重要な過渡期の機材でした。
1969年以降は、Hiwatt CP103/DR103Wと4×12キャビネット(Faneスピーカー搭載)が事実上のメイン機材となります。 『Live at Leeds』や『Isle of Wight Festival 1970』で聴ける図太くも明瞭なクランチサウンドは、このHiwattシステムの賜物です。 中域の張り出しと高域のエッジがバンド全体の爆音の中でも埋もれず、むしろリズムの推進力を担っていました。
80年代にはMesa/Boogieのキャビや、スタジオでのプリアンプ直結も試みています。 90年代以降はFender Vibro-Kingを愛用し、特にFender Eric Clapton Stratocasterとの組み合わせでコンプレッションの効いたクリーン〜クランチサウンドを形成。 2010年代以降はLazy J Model 20やJ-40を併用し、よりヴィンテージトーンを求める傾向が見られます。 2006年には短期的にHiwatt Custom 50 Signature CP103 50W+Mesa/Boogie 2×12を使用した記録も確認されています。
こうした遍歴を見れば、タウンゼントの音作りが単なる「爆音」ではなく、明瞭さ・音抜け・レンジ感を重視していたことがわかります。 結果として、彼のアンプ選びは「ステージを支配する音圧と、楽曲の中で存在感を失わないギターサウンド」を両立させるための選択であったと想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fender Pro Head | Fender | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | 1964–65に使用、初期ライブサウンドの基盤 |
| Fender Showman | Fender | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | 米ツアーで使用、2×15キャビとの組み合わせ |
| Vox AC-100 | Vox | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | 1965年頃に使用、ビートバンド的な明瞭感 |
| Sound City L100 | Sound City | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | Hiwattの原型、67〜68年にメイン使用 |
| Hiwatt CP103 / DR103W | Hiwatt | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | 1969以降のメイン、爆音かつ明瞭なトーン |
| Fender Vibro-King | Fender | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | 90年代以降のメイン、EC Stratとの組み合わせ |
| Lazy J Model 20 / J-40 | Lazy J | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | 2010年代以降に使用、ヴィンテージ風の温かいトーン |
使用ギターの種類と特徴【The Who・Pete Townshend】

Pete Townshend(ピート・タウンゼント)は、時代ごとにさまざまなギターを使い分け、その選択がThe Whoの音の進化を形作ってきました。 彼のギター遍歴は単なる「機材選び」ではなく、楽曲の方向性やステージパフォーマンスと密接に結びついており、結果的にロックギターの歴史そのものを更新してきました。
60年代中盤にはRickenbacker 12弦モデル(330/12、360/12、330S/12)を導入し、『A Quick One』や『Tommy』の録音で煌びやかで広がりのあるアルペジオを響かせています。 特に330S/12は1979〜82年にも使用されており、黒リフィニッシュ個体が確認されています。 同時期にはFender Telecaster(1965–67)がライブの定番で、Selmer Treble’n’Bassアンプと組み合わせた写真も残っています。
1967〜68年頃にはFender Jazzmasterを短期間使用し、派手な破壊パフォーマンスで知られるギターとしてファンの記憶に残っています。 また、Fender Stratocasterは1966〜68年に愛用され、さらにEric Claptonから贈られた1957 Stratocasterは1973年以降スタジオ中心に登場。 1989年以降はFender Eric Clapton Stratocasterをメインとしており、今日に至るまで彼の代名詞となっています。
1968年後半から1971年にはGibson SG Special(P-90搭載)を主力とし、『Live at Leeds』や『Isle of Wight 1970』での象徴的なサウンドを生み出しました。 その後はGibson Les Paul Deluxe(ミニハムバッカー)を1973〜79年のツアーで多用し、中域に厚みを持たせたパワフルな音を実現しました。 さらに1956 Gibson Les Paul Custom “Black Beauty”も断続的に使用されており、『Relay』などの演奏で確認されています。
Gretsch 6120 Chet Atkinsは録音において定番のエレクトリックサウンドを提供し、6128 Duo Jetは1973年頃短期的に使われました。 また、ES-335/345/355系も1968〜69年の米国公演で使用が記録されています。 Epiphone WilshireやCoronetは初期の重要なギターで、特にWilshireはボーカルのロジャーから分割払いで入手したエピソードも語られています。
70年代末から80年代初頭にはSchecterやGiffin製のTelecasterスタイルギターを複数使用し、Hiwattとの組み合わせでよりモダンなサウンドを展開しました。 アコースティックギターも重要で、Gibson J-200は1968年以降の代表機材として定着し、2004年にはPTシグネチャーモデルも登場。 Guild F-612XLやHarmony Sovereign H-1270といった12弦アコースティックは録音に欠かせない存在で、Takamine製のエレアコも80〜90年代のライブで多用されています。
このように、タウンゼントのギター選びは「破壊パフォーマンスに耐えうる堅牢性」と「楽曲に応じたトーンバリエーション」の両立を意識したものであったと想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | ギターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rickenbacker 330/12 | Rickenbacker | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | エレキ12弦 | 1965–66録音、煌びやかなサウンド |
| Fender Telecaster | Fender | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | ソリッドエレキ | 1965–67ライブ使用、初期代表機材 |
| Gibson SG Special (P-90) | Gibson | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | ソリッドエレキ | 1968–71主力、『Live at Leeds』などで使用 |
| Gibson Les Paul Deluxe | Gibson | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | ソリッドエレキ | 1973–79ツアーの主力、中域に厚み |
| Fender Eric Clapton Stratocaster | Fender | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | ソリッドエレキ | 1989以降メイン、現在も使用中 |
| Gibson J-200 | Gibson | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | アコースティック | 1968以降導入、2004にシグネチャー発売 |
| Guild F-612XL | Guild | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | アコースティック12弦 | 1971以降の録音に常用 |
使用エフェクターとボード構成【The Who・Pete Townshend】
Pete Townshend(ピート・タウンゼント)のエフェクター遍歴は、ロックギターの発展をそのまま体現しています。 The Whoの爆音サウンドの中でギターを埋もれさせず、独自のアタック感と存在感を生み出すため、彼は時代ごとに多様なエフェクターを取り入れてきました。
60年代中盤にはSola Sound Tone Bender MkIを導入し、粗削りながらもギターを前に押し出すファズサウンドを獲得しました。 その後、Marshall SupaFuzz(1967–68)、Dallas Arbiter Fuzz Face(1968短期)とファズペダルを乗り換え、最終的に彼の定番となったのがUnivox Super-Fuzz(1968末〜71)です。 『Live at Leeds』の重量感あふれるディストーションサウンドは、このSuper-Fuzzによるものとして有名です。
並行して、Grampian Reverb Unitをプリアンプ兼リバーブとして使用しており、単なる空間効果ではなくギターの倍音を強調する役割を担っていました。 さらに、WEM CopicatやEchoplex、Binsonなどのテープエコー群も活用し、PA経由での音響効果として導入されました。 これらのエフェクトは『Tommy』や『Quadrophenia』といった大作の音像構築に欠かせない存在でした。
70年代後半から80年代にかけては、MXR Dyna-Compを使用し、クリーン〜クランチサウンドにコンプレッションを加えてアンサンブル内で埋もれない音を実現。 また、Boss OD-1は90年代以降に頻繁に使用され、Fender Vibro-Kingを押す役割を果たしました。 80年代初頭にはRoland SDE-2000ディレイやRoland Dimension-D SDD-320コーラスを取り入れ、より広がりのあるステレオサウンドを追求しています。
2000年代に入ると、Pete Cornishによるカスタムボードを導入。 ここにはBoss OD-1、Demeter Compulator、T-Rex Replica(ディレイ)が組み込まれ、安定したプロフェッショナル仕様のシステムとして運用されています。 ステージにおける安定性と再現性を重視しながらも、タウンゼントらしい豪快なピッキングに応える堅牢なセットアップでした。
このように、タウンゼントのエフェクターは「派手さ」よりも「音抜けと存在感」を追求するために選ばれており、特にファズとコンプレッサーの組み合わせが彼の音の本質を形作っていたと想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | エフェクターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sola Sound Tone Bender MkI | Sola Sound | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | ファズ | 1965–66使用、初期ファズサウンド |
| Univox Super-Fuzz | Univox | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | ファズ | 1968末〜71主力、『Live at Leeds』の要 |
| Grampian Reverb Unit | Grampian | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | リバーブ | プリアンプ的役割も兼任 |
| WEM Copicat | WEM | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | エコー | テープエコー、PAと併用 |
| MXR Dyna-Comp | MXR | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | コンプレッサー | 1979–85、1999–2006使用 |
| Boss OD-1 | BOSS | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | オーバードライブ | 90年代以降の常用 |
| Pete Cornish Custom Board | Pete Cornish | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | スイッチングシステム | 2006以降、安定性を重視した専用設計 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【The Who・Pete Townshend】

Pete Townshend(ピート・タウンゼント)の音作りは、単なる機材の組み合わせにとどまらず、アンプのEQ設定やミックス段階での工夫に大きく支えられています。 The Whoの爆音ライブにおいても、彼のギターが常にバンドの中心として聴こえてくるのは、緻密な音響設計の成果でした。
まずアンプのEQ設定について、Hiwatt CP103/DR103Wをメインにしていた70年代初頭は、低域を絞り気味に、中域をしっかり押し出し、高域を適度に強調するバランスをとっていたとされています。 この設定により、爆音の中でもアタック感とコードの分離感を保ち、バンド全体の音像を前進させていました。 実際、『Live at Leeds』では、パワーコードを弾いても音が潰れず、ギターの一音一音がしっかりと耳に届きます。
エフェクターの使用においては、Univox Super-FuzzやTone Benderを用いる際も、アンプ側で低域を整理することが重要でした。 Super-Fuzzは強烈な低域と倍音を生むため、アンプでローを抑えることで、ベースやドラムとの住み分けを明確にし、音の壁の中でも輪郭を残していました。 逆にクリーントーンでは、MXR Dyna-Compでコンプレッションを強めにかけ、EQでミドルをやや持ち上げることで、リズムギターがバンドの基盤として安定するよう工夫されています。
スタジオ録音においては、ダブルトラッキングや12弦ギターの多重録音を駆使しました。 特に『Tommy』や『Quadrophenia』では、Guild F-612XLやRickenbacker 12弦を重ねることで音に奥行きを与えています。 この際、片方のトラックをややハイ寄りにEQし、もう片方をロー寄りに処理することで、ステレオ空間に広がりを持たせていました。
また、ライブではグラムピアンのリバーブユニットやテープエコーを通すことで、ギター自体が空間的な厚みを持つように調整されています。 その結果、シンセサイザーが主役となる『Baba O’Riley』や『Won’t Get Fooled Again』でも、タウンゼントのギターは単なる伴奏ではなく、リズムの推進力と空間的な存在感を同時に担っています。
さらに、近年の使用機材(Fender Vibro-KingやLazy Jアンプ)では、クリーンからクランチの境目を狙った設定が多く、ボリューム操作やピッキングの強弱でニュアンスを作り分けています。 このような設定は、Boss OD-1などで軽く押し出すことで再現され、現代のギタリストにも応用可能です。
ミックス段階での工夫としては、The Whoのレコーディングではしばしばギターを左右に振り分けるのではなく、中央付近に配置し、バンドの“心臓”として機能させています。 キース・ムーンのドラムやジョン・エントウィッスルのベースが暴れる中でも、タウンゼントのギターがバンド全体を一つにまとめる役割を果たしていました。 これもEQと音像設計の工夫によって実現されていたと想定されます。
総じてタウンゼントの音作りは、「大音量の中で埋もれない明瞭さ」「バンド全体を牽引する推進力」「楽曲の構造に沿ったアレンジ力」を兼ね備えています。 単に歪ませるのではなく、EQやコンプレッションの調整、トラックの重ね方、ライブとスタジオでの使い分けといった総合的な工夫が、彼のサウンドの核心であるといえるでしょう。 これらは再現を試みるギタリストにとっても大きなヒントになると想定されます。
比較的安価に音を近づける機材【The Who・Pete Townshend】
Pete Townshend(ピート・タウンゼント)のサウンドを完全に再現するのは容易ではありません。 しかし、現代の市販機材を活用すれば、比較的安価に彼の特徴的な音に近づけることが可能です。 ここでは1万円〜5万円程度を目安に、初心者や中級者でも導入しやすいモデルを紹介します。
まず欠かせないのがファズ系です。タウンゼントの60年代後半〜70年代前半のサウンドを象徴するUnivox Super-Fuzzはビンテージ市場で高額ですが、代替としてはBOSS FZ-1W(Waza Craftシリーズ)やElectro-Harmonix Big Muffが有効です。 特にBig Muffは低域の厚みと持続感を持ち、Super-Fuzzのラフな歪み感に近い雰囲気を得られます。
次に、コンプレッサー。彼のクリーン〜クランチサウンドを支えていたMXR Dyna-Compは現在も現行品が安価に入手可能で、リズムギターをバンド全体の中で安定させるのに最適です。 強めのコンプレッション設定で、タウンゼントらしいストロークの一貫性を再現できます。
アンプに関しては、オリジナルのHiwattやFender Vibro-Kingは高額かつ大出力ですが、代替としてBlackstar HT Club 40やMarshall DSLシリーズが現実的です。 これらはミドルの押し出しが強く、バンドアンサンブルの中で埋もれにくいトーンを作りやすい点でタウンゼント的サウンドに通じます。 また、VOX AC15C1もクリーン〜クランチで煌びやかさを得られるため、RickenbackerやTelecasterの使用感を模倣するのに適しています。
エフェクト処理に関しては、BOSS OD-3やBD-2 Blues Driverがオーバードライブ用途でおすすめです。 タウンゼントがOD-1を使ってアンプを押していたのと同じように、軽めの歪みでアンプを前に出す役割を担えます。 さらにBOSS DD-8などのディレイを組み合わせれば、ライブにおける空間的な広がりも再現できます。
アコースティックサウンドを狙う場合、Takamine GDシリーズやYamaha FG820-12(12弦)が実用的です。 GuildやGibsonの高額モデルと比べても、十分に煌びやかで迫力のあるサウンドを得られるため、レコーディングや弾き語りでもタウンゼント的な空気感を演出できます。
総じて、「ファズ+コンプレッサー」「ミドルの強いアンプ」「オーバードライブで押す」という3点を意識すれば、比較的安価でもタウンゼントの本質的なサウンドに近づけます。 初心者であればBOSSやMXRのコンパクトペダルを中心に揃えるだけでも十分に効果があり、ステージや自宅練習で「The Whoらしい爆音の中でも抜けるギター」を体感できるでしょう。
| 種類 | 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファズ | Big Muff Pi | Electro-Harmonix | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | Super-Fuzzの代替、厚みある歪み |
| コンプレッサー | Dyna-Comp | MXR | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | 現行品で入手可、リズムの安定感を再現 |
| オーバードライブ | BD-2 Blues Driver | BOSS | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | OD-1の代替、軽めの歪みでアンプを押す |
| アンプ | HT Club 40 | Blackstar | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | 中域の押し出しが強く、ライブ向き |
| アコースティックギター | FG820-12 | Yamaha | Amazonで探す | The Who | Pete Townshend | 12弦モデル、煌びやかな伴奏を再現 |
総括まとめ【The Who・Pete Townshend】

Pete Townshend(ピート・タウンゼント)のサウンドを振り返ると、それは単なるギターやアンプの選択にとどまらず、ロックという音楽の枠組みを拡張する実験そのものであったと言えます。 彼のプレイはしばしば「破壊的」と形容されますが、実際には極めて緻密な音作りと構築的なアプローチに裏打ちされています。
初期のRickenbacker 12弦やTelecasterによる鋭いリズムワーク、70年代のGibson SG SpecialやLes Paul Deluxeでの重量感のあるパワーコード、そしてHiwattアンプとの組み合わせによる爆音サウンドは、どれもバンド全体を牽引するための選択でした。 また、スタジオ作品では12弦アコースティックや多重録音を駆使し、壮大でシアトリカルな音像を作り上げています。
エフェクターにおいても、Super-Fuzzやコンプレッサーを戦略的に導入し、単なる音の装飾ではなく、アンサンブル全体の推進力を高めるために使用しました。 結果として、The Whoの音楽は常に「ギターが中心にあるロック」として成り立ち、その象徴がタウンゼントの音でした。
現代のギタリストにとって、彼のサウンドを完全に再現するのは難しいかもしれません。 しかし「爆音の中でも埋もれない明瞭さ」「リズムギターでバンド全体を前へ押し出す推進力」「アコースティックとエレクトリックを自在に組み合わせる柔軟性」という3つの本質を意識することで、タウンゼント的な音作りに近づけることができます。 これは決して高額な機材を揃えることだけが重要なのではなく、EQやコンプレッションの調整、ピッキングの強弱、楽曲構造に応じたセッティングの工夫が大切であることを示しています。
The Whoの音楽を聴くと、ギターが単なる伴奏を超えて「物語を語る役割」を担っていることがわかります。 タウンゼントのプレイはパワフルでありながらも繊細で、時にオーケストラ的な広がりを生み出し、時にリズムの推進力として突き進む。 その二面性こそが彼のサウンドの魅力であり、今日のロックギタリストにも多大な影響を与え続けています。
総じて、Pete Townshendの音作りの本質は「バンドを動かす力」と「音楽を演出する力」の両立にあります。 あなたが彼の音を追いかける際には、単なる機材コピーにとどまらず、その背景にある音楽的思想を理解し、自分の演奏に応用してみることが何よりの近道となるでしょう。
“`
下記恐らく使用(所持)している機材のまとめです。参考までに!
🎸ギター
• Rickenbacker 330/12・360/12・330S/12(12弦) — 1965–66に使用、後年スタジオや’89/’93ツアーでも再登場。330S/12は’79–82に使用(黒リフィニッシュ個体)。
• Fender Telecaster(’65–’67) — 初期ライブで多用(Selmer Treble’n’Bassに接続の写真あり)。
• Fender Jazzmaster(’67–’68) — 短期使用・破壊で有名。
• Fender Stratocaster(’66–’68)/1957 Strat(Eric Claptonからの贈呈・’73〜スタジオ中心)/Fender Eric Clapton Strat(’89〜現在のメイン)/P-90載せStrat(2002)。
• Fender Electric XII(’69『Tommy』録音)。
• Gibson SG Special(P-90、’68後半〜’71) — 『Live at Leeds』『Isle of Wight 1970』期の主力。画像でも確認(上の写真)。
• Gibson Les Paul Deluxe(ミニハム、’73–’79ツアーの主力)。
• 1956 Gibson Les Paul Custom “Black Beauty”(断続的に使用、『Relay』TV出演など)。※この項目は複数の強い一次情報が少なめ(補助的情報)。
• Gretsch 6120 Chet Atkins(録音で“定番の電気的サウンド”)/Gretsch 6128 Duo Jet(’73短期使用)。
• Gibson ES-355 / ES-345 / ES-335(’68–’69の米国公演・プロモで使用)。
• Epiphone Wilshire(初期、ロジャーから分割払いで入手)/Epiphone Coronet(’62使用記録)。
• Schecter/Giffin製“Tele”スタイル(’79〜80年代初頭のメイン群)。
• アコースティック:Gibson J-200(’68導入、’96以降も継続・2004にPT SJ-200リミテッド)/Harmony Sovereign H-1260(6弦)・H-1270(12弦)/Guild F-612XL(12弦、’71以降の録音で常用)/Takamine各種(FP360SCほか、’86–’93)。
🔊アンプ
• Fender Pro“ヘッド”(’64–’65)/Fender Showman & 2×15(’67米ツアー)。
• Vox AC-100(’65)/US Thomas Organ “Super Beatle”(’67北米・Monterey Pop)。
• Sunn(’67北米で併用)。
• Sound City L100(’67–’68、のち改造)→ Hiwatt誕生の下敷きに。
• Hiwatt CP103/DR103W(’69–’82 ほぼ専用)+Hiwatt SE4122/SE4123 4×12(Fane搭載)。
• Mesa/Boogie 4×12(’82にキャビとして)/プリを直接卓へ(スタジオ)。
• Fender Vibro-King(’90年代〜現在、EC Stratと組み合わせ)。
• Lazy J(Model 20/J-40 3×10、2010以降にVibro-Kingと併用)。
• (短期)Hiwatt Custom 50 Signature CP103 50W+Mesa/Boogie 2×12(2006)。
🎛️エフェクター/周辺機器
• Sola Sound Tone Bender MkI(’65–’66)→ Marshall SupaFuzz(’67–’68)→ Dallas Arbiter Fuzz Face(’68短期)→ Univox Super-Fuzz(’68末〜’71、PTクラシックの要)→ Shaftesbury Duo Fuzz(同時期の使用例あり)。
• Grampian Reverb Unit(プリアンプ/リバーブとして’67頃)。
• WEM Copicat(テープエコー)/Echoplex/Binson などのエコー群(主にPA/ギター処理で運用)。
• Edwards Light Beam Volume Pedal(Gretsch 6120+’59 Fender Bandmasterと併用)。
• MXR Dyna-Comp(’79–’85、’99–’06)/Boss OD-1(’99〜、Vibro-Kingを押す用途)。
• Roland SDE-2000(’82ディレイ)/Roland Dimension-D SDD-320(’81コーラス)。
• Pete Cornish Custom Designボード(2006〜) — T-Rex Replica(ディレイ)/Boss OD-1/Demeter Compulatorを内蔵した専用ユニット。