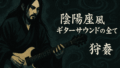始めに(特徴紹介)
Linked Horizonのギタリスト・西山毅は、緻密なアレンジと迫力あるサウンドでファンを魅了してきました。彼のギターは「物語を彩る伴奏」という位置づけでありながらも、楽曲の世界観を一気に広げる重要な役割を担っています。
特に『進撃の巨人』主題歌シリーズで聴ける重厚かつ緊張感あふれるギターワークは、ストリングスやコーラスと混じり合いながらも輪郭を失わない独自のトーンを放ちます。ソリッドなディストーションサウンドだけでなく、クリアなクリーントーンや空間系を駆使することで、物語的な起伏を生み出しています。
また、彼のプレイスタイルはテクニカルな速弾きよりも、リフの厚みやアルペジオの広がり、音の質感を重視する点に特徴があります。フロイドローズ搭載モデルを駆使してのピッチ表現、ライン出しによる安定した音作りなど、ライブとレコーディング両面で一貫したスタイルを確立している点も注目すべきポイントです。
この解説では、西山毅の使用アンプ、ギター、エフェクターを丁寧に整理しながら、そのサウンドの本質に迫ります。さらに、比較的手頃な機材で再現する方法や、具体的なEQセッティングの工夫も紹介していきます。
Linked Horizonの壮大な世界観を支えるギターサウンドを深掘りし、読者が「どうすれば近づけるか」を実感できる記事を目指します。
▶ Linked Horizon の公式YouTube動画を検索
使用アンプ一覧と特徴【Linked Horizon・西山毅】
西山毅のアンプ事情は、他のロック系ギタリストとは大きく異なる特徴を持っています。Linked HorizonやSound Horizonでのライブ現場では、基本的に「ステージ上にアンプを設置しない」スタイルを徹底しています。これは本人がインタビューやライブレポートで明言している通り、Fractal Audio Axe-Fxを用いたライン出しによる運用を基本にしているためです。
その背景には、オーケストラやシンフォニックなサウンドと混ざり合うLinked Horizonの音楽性があります。ステージで大音量のアンプを鳴らすと、他の楽器とのバランスが崩れやすくなるため、ライン直結でPAに送る方法が最適解となったのです。この方式により、西山のギターは会場規模に関係なく一貫してクリアで迫力あるトーンを維持できます。
ただし、レコーディングや小規模ライブにおいては、Roland JC-120やSoldano SLO-100といった定番アンプを使用してきたことも明らかになっています。JC-120はクリーントーンの美しさとコーラス効果で有名であり、西山のアルペジオやクリーンパートを支える重要な存在です。一方、Soldano SLO-100は90年代からプロに愛用されてきたハイゲインアンプで、西山も「ループの癖」に触れる発言をしており、スタジオ作業で信頼を置いていることが伺えます。また、Marshallアンプもレコーディング現場で使用したことを明言しており、クラシックなロックサウンドを補う役割を担っていると考えられます。
総じて、西山毅は「ライブ=ライン出し」「スタジオ=真空管アンプやJC-120併用」という使い分けを行っていると考えられます。ステージ上での効率性とサウンドの安定感を重視しながら、レコーディングでは伝統的なアンプサウンドで厚みを加えるという柔軟なアプローチは、Linked Horizonの壮大な楽曲に欠かせない要素です。以上を踏まえると、西山のアンプ環境はFractal Audio Axe-Fxを軸にしつつ、場面ごとにRolandやSoldano、Marshallを使い分けている、と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fractal Audio Axe-Fx | Fractal Audio | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | ライブ現場は基本ライン出し。アンプ未使用方針を本人が明言。 |
| Roland JC-120 | Roland | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | クリーントーン用。ライブやスタジオで実使用。 |
| Soldano SLO-100 | Soldano | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | レコーディング使用。ループの癖について本人が言及。 |
| Marshall(機種不明) | Marshall | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | レコーディングでの使用を本人が明言。機種未確定。 |
使用ギターの種類と特徴【Linked Horizon・西山毅】

西山毅のサウンドの核を担っているのは、カスタム仕様を含む複数のギターです。中でも特に象徴的なのが、MOON GUITARS製のST-NISHIYAMA MODEL。Floyd Roseを搭載し、DiMarzio Air Zoneを2基+True Velvetを組み合わせたSSH構成というユニークな仕様で、さらにタップ/ハム同時ONスイッチを備えています。カラーはBlackとDakota Redが確認されており、Linked Horizonの重厚な楽曲で必要とされる「パワーと繊細さの両立」を実現する一本です。
また、moon Stratocaster(通称「moon Stratocaster No.2」)も重要な存在です。Bartolini V-90sを搭載し、Wilkinson VS-100SSBブリッジを装備。2007年に入手し翌年2008年には再塗装されており、長期に渡って彼の現場を支えた一本です。このギターはシングルコイルらしい抜けの良さを持ちながらも、独特の太さを持つトーンが特徴で、オーケストラと共演するシーンにおいても音像が埋もれにくいのが魅力です。
他にもP-PROJECT PST-1TN(Ash 2P、Lindy Fralin系PU、Wilkinson VSVG)やnivram製のカスタムストラト(Alder 1P、Fender CS Fat ’50s PU搭載)といったカスタム系のストラトキャスターを所有しています。これらはいずれも伝統的なストラトのニュアンスを残しながらも、独自のカスタマイズにより「分厚いミドルレンジ」と「繊細な高域」を両立させているのがポイントです。
さらに、西山が所有しているFender Mustang 1966(ホワイト)も見逃せません。オリジナルの60年代ムスタングは短めのスケールによる柔らかいサウンドが特徴で、荒々しいリフよりもアルペジオや独特のトーンを必要とする場面で活躍したと考えられます。
こうしたギター群はいずれも「多様な音楽的世界観に即応できる柔軟性」を備えており、楽曲ごとに必要な音色を選び分けている点がLinked Horizonらしい重厚なサウンドを支えています。総じて、西山毅のギターはメインのMOONモデルを中心に、カスタムストラトやビンテージ・ムスタングを使い分けることで幅広いトーンを作り出している、と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | ギターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-NISHIYAMA MODEL | MOON GUITARS | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | ストラトシェイプ | Floyd Rose搭載。DiMarzio Air Zone×2 + True Velvet。本人のメインモデル。 |
| moon Stratocaster No.2 | MOON GUITARS | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | ストラトシェイプ | Bartolini V-90s搭載。2007年入手→2008年再塗装。長期使用。 |
| P-PROJECT PST-1TN | P-PROJECT | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | ストラトタイプ | Ash 2P、Lindy Fralin系PU、Wilkinson VSVG搭載。 |
| nivram Custom Stratocaster | nivram | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | ストラトタイプ | Alder 1P、Fender CS Fat ’50s PU搭載。 |
| Mustang 1966 | Fender | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | オフセットギター | 1966年製。短スケール特有の柔らかいトーン。 |
使用エフェクターとボード構成【Linked Horizon・西山毅】
西山毅のエフェクトシステムは、ライブやスタジオでの状況に応じて大きく変化してきました。近年のLinked HorizonやSound Horizonの現場では、Fractal Audio Axe-Fxを中心とした「アンプレス・システム」を採用しており、これが彼のメインツールになっています。アンプを使わずにPAへ直接ライン出しすることで、オーケストラやシンフォニックアレンジの中でも一貫したサウンドを確保できるのが大きな利点です。Axe-Fx内蔵のアンプシミュレーターや空間系エフェクトを駆使し、壮大な楽曲にも埋もれないギターサウンドを構築しています。
一方で、2000年代中盤以降はVOX ToneLab LEを用いた時期もありました。これは真空管回路を備えたマルチエフェクターで、小音量の現場やリハーサル、ツアーでの持ち運びやすさを重視する場面で多用されていました。VOX ToneLab LEはシンプルな「OVER DRIVE」セッティングをよく用いていたとされ、歪みを抑えめにすることでアンサンブル全体のバランスを保ちながら存在感を出す工夫が感じられます。
さらに、80年代から90年代にかけてはBOSS SD-1 Super OverDriveやYamaha Overdriveといったペダル型のオーバードライブも使用されていました。特にBOSS SD-1は中域に特徴があり、リードやリフの輪郭を強調するのに適しており、西山のロック的な側面を補強していたと推測されます。また、Yamaha Overdriveは80年代らしい粗削りなドライブ感を持ち、当時のスタジオやライブで独自の歪み作りに貢献したと思われます。
現在のボード構成はAxe-Fxを中心としたシンプルなものですが、過去のペダル利用歴を見ると「必要に応じて最適なツールを選択する柔軟な姿勢」が一貫していることがわかります。西山の音作りは「ギター本体と基本の歪み」で基礎を固め、その上で必要に応じて空間系やモジュレーションを加えるというシンプルながら計算されたアプローチです。総じて、Axe-Fxが中心でありながらも、VOX ToneLab LEやBOSS SD-1、Yamaha Overdriveといった機材をシーンごとに使い分けてきた、と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | エフェクターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fractal Audio Axe-Fx | Fractal Audio | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | プリアンプ/アンプシミュレーター | 近年のメイン機材。ライン出しでPAへ直接送る運用。 |
| VOX ToneLab LE | VOX | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | ギター用マルチエフェクター | 2006年以降のツアーや小音量現場で使用。シンプルなOVER DRIVEセッティング。 |
| BOSS SD-1 Super OverDrive | BOSS | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | オーバードライブ | 80年代〜90年代に使用。中域に特徴がありリードやリフの輪郭を強調。 |
| Yamaha Overdrive | Yamaha | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | オーバードライブ | 80年代使用歴あり。粗削りな歪み感で独自のサウンドを形成。 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【Linked Horizon・西山毅】

西山毅の音作りは、「物語を支える音像作り」という観点で非常に独自性があります。Linked Horizonの楽曲はオーケストラ、コーラス、シンセサイザーなど多くの楽器が同時に鳴っているため、ギターの音がただ歪んでいるだけでは全体に埋もれてしまいます。そのため、彼のセッティングは歪みの量を抑え、ミドルの存在感を強調するEQ処理を中心に構築されています。
まず、基本的な歪みセッティングとしては、Axe-FxやVOX ToneLab LEを用いた場合でも「ゲインは控えめ」「ミドルをやや強調」「ローは出しすぎない」「ハイは刺さらない程度に調整」というバランスが軸になっています。これは特に進撃の巨人シリーズ楽曲で顕著で、疾走感あるリフでも中域がしっかり抜けて聴こえるのはこの工夫によるものです。
クリーントーンでは、Roland JC-120のように広がりのあるサウンドを意識したセッティングが中心です。コーラスを軽くかけることで空間的な広がりを演出しつつ、コンプレッションを強めすぎずに「自然なアタック」を残すことがポイントです。これにより、アルペジオやストロークの粒立ちがしっかり残り、オーケストラと調和しながらも埋もれないサウンドを実現しています。
具体的なEQ例を挙げると、
- ゲイン:3〜4(最大値の40%程度)
- Bass:4.5(控えめ、ローエンドの濁り防止)
- Middle:6〜7(中域を強調して抜け感を確保)
- Treble:5(刺さらずに抜ける程度)
- Presence:4〜5(広がりを調整し、刺さり防止)
ミックスの工夫としては、Linked Horizonの楽曲はレイヤーが非常に多いため、ギターの定位はややサイド寄りにパンニングされることが多いです。これにより、ストリングスやコーラスと中央でぶつかるのを避け、左右に広がるギターが「壁のような音圧」を形成します。また、ディレイやリバーブは深くかけすぎず、ショートディレイで空間を補強するのが特徴です。長いリバーブはオーケストラ側に任せ、ギターはあくまで前面に押し出す処理が多い印象です。
ライブでは、アンプレスでPA直結する関係上、FOH(フロント・オブ・ハウス)エンジニアとの連携が非常に重要になります。Axe-Fxから出すライン信号は安定しているため、PA側でのEQ補正やコンプ処理で最終的な音作りを仕上げるケースが多いと考えられます。例えば大規模ホールではローをさらにカットし、ミッドハイを強調して「遠くまで届くギター」を作るといった調整が行われると推測されます。
また、曲ごとの使い分けとして「重厚なリフ=ハイゲイン+ロータイト」「壮大なバラード=クリーン+コーラス」「疾走曲=ゲイン控えめ+中域ブースト」といった明確な切り替えがなされています。この柔軟なセッティングの使い分けは、Axe-Fxのプリセット切替を駆使することで実現しており、現代的かつ効率的な方法であると言えるでしょう。
総合的に見ると、西山毅の音作りは「過剰な歪みに頼らず、EQとミックスで存在感を出す」「クリーンと歪みを場面ごとに緻密に使い分ける」「ライン出しによる一貫した音質管理」という三本柱が特徴です。これにより、Linked Horizonの壮大な楽曲世界の中でも、常にギターが適切な役割を果たすよう設計されている、と想定されます。
比較的安価に音を近づける機材【Linked Horizon・西山毅】
西山毅の音作りを完全に再現するのは、カスタムギターやAxe-Fxといった高額機材を前提としているため容易ではありません。しかし、初心者や中級者でも比較的安価に「西山サウンド」に近づける手段はいくつか存在します。ポイントは、(1) 歪みを抑えた中域重視のドライブ、(2) 広がりを持たせるクリーン、(3) シンプルかつ安定したマルチエフェクターの活用、です。
まず歪み系では、BOSS SD-1 Super OverDriveの現行モデルが手軽な選択肢です。西山自身が過去に愛用していた事実があるため、キャラクター的にも近いサウンドを得やすく、ゲインを控えめにしつつミドルを強調することで「抜けるギター」を再現できます。加えて、クリーントーンを支えるためにRoland JC-22のような小型ジャズコーラスアンプを使うと、JC-120の特徴的なコーラス感を低価格帯で体験できます。
また、マルチエフェクターではZOOM G3XnやLine 6 POD Goといった機種が候補になります。Axe-Fxほど高額ではないものの、アンプシミュレーターや空間系エフェクトを十分に備えており、Linked Horizon的なシンフォニックメタルのバッキングやクリーントーンを安定して鳴らすことが可能です。特にLine 6 POD Goは、ライブや宅録どちらにも対応できる柔軟性を持っており、「PA直結で使える」という点で西山のライン出しシステムに近いアプローチを取れます。
ギターについては、ストラトキャスター系のモデルであれば比較的低価格帯でも似たニュアンスを得られます。YAMAHA PACIFICA 612VやFender Player Stratocasterは、SSH構成のため西山のMOONカスタムのような幅広い音色を再現可能です。特にフロイドローズ搭載モデルを選べば、ピッチ表現の幅も広がり、ライブ的なニュアンスが強まります。
総じて、これらの機材を活用することで「西山毅風サウンド」の入り口に立つことができます。数万円規模で揃えられるため、学生や趣味レベルでも十分にLinked Horizon的な重厚かつクリアな音を楽しめるでしょう。
| 種類 | 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバードライブ | BOSS SD-1 Super OverDrive | BOSS | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | 本人も使用歴あり。ゲイン控えめで中域ブースト可能。 |
| コンボアンプ | Roland JC-22 | Roland | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | JC-120の小型版。自宅や小規模ライブで再現性が高い。 |
| マルチエフェクター | ZOOM G3Xn | ZOOM | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | 安価でアンプシミュ搭載。宅録や小規模現場で使いやすい。 |
| マルチエフェクター | Line 6 POD Go | Line 6 | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | PA直結可能。Axe-Fxに近い思想を低価格帯で実現。 |
| エレキギター | YAMAHA PACIFICA 612V | YAMAHA | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | SSH構成。多様な音作りに対応可能で初心者向け。 |
| エレキギター | Fender Player Stratocaster | Fender | Amazon検索 | Linked Horizon | 西山毅 | ストラト系で万能。中級者以上の定番モデル。 |
総括まとめ【Linked Horizon・西山毅】

西山毅の音作りを振り返ると、その本質は「楽曲全体を支えるためのギター」という視点に尽きます。彼のサウンドは単独で派手に目立つことを目的としていません。むしろ、Linked Horizonの壮大な物語性を崩さないよう、あくまで「編曲の一部」として設計されているのが最大の特徴です。
使用機材を見ても、その方向性がよく表れています。メインとなるMOON GUITARS ST-NISHIYAMA MODELは、多彩な音色切り替えを可能とするカスタムモデルであり、必要に応じて重厚なリフから繊細なアルペジオまで幅広く対応します。さらに、Axe-Fxによるアンプレス運用は、複雑なオーケストラアレンジの中でも安定した音質を確保するための合理的な選択であり、徹底したプロフェッショナリズムがうかがえます。
また、EQやミックスの工夫も重要です。西山のセッティングは「歪ませすぎない」「中域を強調する」「空間系は深くかけすぎない」といったシンプルながら的確な調整が施されています。このアプローチにより、ギターは楽曲の骨格を形成しつつも他の楽器と干渉せず、結果的に全体の迫力を増幅させる役割を果たしています。
さらに、彼のサウンド作りの背景には「柔軟性」があります。過去にはBOSS SD-1やYamaha Overdriveといったコンパクトペダルを駆使していた時期があり、2000年代にはVOX ToneLab LEを導入し、現在ではAxe-Fxを中核とするなど、時代や環境に応じて最適な機材を選び続けています。この変遷は「固定化されたトーンを守る」よりも「その時々の現場で最も良い音を出す」ことを優先する姿勢を示しています。
これらを踏まえると、西山毅の音作りの核心は「場の要求に応じたサウンドメイク」と言えるでしょう。大規模ホールではPA直結での安定性を重視し、レコーディングでは真空管アンプやJC-120で厚みを補い、ギター自体は多彩なバリエーションを用意することで楽曲ごとのカラーに応えています。
読者が西山サウンドを再現したい場合、まずは「中域を意識するEQ」「過剰に歪ませないドライブ」「空間系を控えめに」という3つのポイントを押さえるとよいでしょう。そのうえで、安価なマルチエフェクターやSSH構成のギターを選ぶだけでも、Linked Horizon的な重厚かつクリアな音像に近づけます。
最終的に、西山毅の音作りの真髄は「ギター単体ではなく、全体を見据えた調和の美学」にあります。その哲学を理解し、自分の演奏にも取り入れることができれば、単なるコピーを超えて「西山毅らしいギターサウンド」の本質に迫れるはずです。
“`
下記恐らく使用(所持)している機材のまとめです。参考までに!
🎸ギター
• MOON GUITARS ST-NISHIYAMA MODEL(Floyd Rose、DiMarzio Air Zone×2 + True Velvet、タップ/ハム同時ONスイッチ搭載。カラー:Black/Dakota Red)
• moon Stratocaster(Bartolini V-90s、Wilkinson VS-100SSB/2007年入手→2008年に再塗装=“moon Stratocaster No.2”)
• P-PROJECT PST-1TN(Ash 2P、Lindy Fralin系PU、Wilkinson VSVG)
• nivram Custom made Stratocaster(Alder 1P、Fender CS Fat ’50s)
• Fender Mustang 1966(White、’66)
🔊アンプ
• (Linked/Sound Horizonの現場)ステージ・アンプ未使用/ライン出し ※Axe-Fxからラインで運用と本人明言。
• Roland JC-120(ライブでの使用あり/自身も使用と明言)
• Soldano SLO-100(レコーディング等で使用。ループの癖についての言及あり)
• Marshall(レコーディングでの使用ありと明言/機種未特定)
🎛️エフェクター/システム
• Fractal Audio Axe-Fx(最近はAxe-Fxを使用。Sound Horizonではアンプを使わずライン出し)
• VOX ToneLab LE(2006年以降のツアーや小音量現場で使用。併せてシンプルな“OVER DRIVE”セッティングも記載)
• BOSS Super OverDrive(SD-1)/Yamaha Overdrive(80年代〜の歪みメイクとして言及)