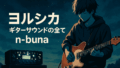始めに(特徴紹介)
Kroiのギタリスト・長谷部悠生は、ファンク、ソウル、R&Bを基盤としつつ、ロックやポップスまでを自在に横断するプレイスタイルで注目を集めています。彼のギターサウンドはカッティングのキレとグルーヴ感、そして柔らかさと鋭さを同居させる独特のトーンが特徴です。
代表曲「Funky GUNSLINGER」では、アンプのスプリング・リバーブを深めに設定しつつ、リアピックアップで突くようなカッティングを聴かせています。一方で、ストラトキャスターを用いたカッティングやクリーントーンでは、繊細かつ抜けの良い音を追求しており、スタジオレコーディングにおける柔軟な音作りが光ります。
彼の音が注目される理由は、単なるジャンルの模倣にとどまらず、古き良きヴィンテージのニュアンスと現代的なファンクサウンドを融合させている点にあります。グルーヴ主体のベースやドラムと絶妙に絡み合うギターアプローチは、Kroi全体のサウンドを引き締める要の役割を担っています。
また、武道館ワンマンに合わせて導入したGibson Les Paul Standard(1958年リイシュー, Murphy Lab)など、機材選びにも妥協がなく、現場に応じた適切なサウンドメイクを常に意識していることがうかがえます。今後の作品やライブごとに、さらに新しい機材やアプローチが加わることが期待されます。
まずは彼の公式MVを見て、音とプレイの関係性をチェックしてみましょう。
使用アンプ一覧と特徴【Kroi・長谷部悠生】
長谷部悠生のアンプの中心は、Fender Hot Rod DeVilleです。本人が「人生で最初に自分で買ったアンプ」と公言しており、今でもレコーディングやライブで活躍しています。このアンプはクリーントーンの艶やかさ、歪ませた時の豊かな倍音、そしてクラシカルなFender系サウンドをベースに、ファンクやR&Bのカッティングに適した音色を生み出します。
特に「Funky GUNSLINGER」では、DeVille内蔵のスプリング・リバーブを深めに効かせ、アンプ側のトレブルを落としてリアピックアップを活用することで、太く粘り気のあるカッティングトーンを実現しています。これによりリズム隊との絡みが際立ち、グルーヴが一層強調されるのです。
また、DeVilleは4×10インチのスピーカーを備えているため、立ち上がりの速いレスポンスと空気を揺らすような低域感が特徴。Kroiのようなグルーヴ重視のサウンドにおいて、ギターが埋もれずに存在感を放つ要因の一つといえるでしょう。
他のアンプの使用情報は現時点で公的な一次ソースには乏しいですが、音楽性やジャンル特性から推測すると、ライブ会場によってはFender Twin Reverbや同系統のクリーンアンプをレンタル機材として用いる可能性があります。ファンクやソウルの現場では特に定番とされるモデルであり、長谷部が目指すトーンにも通じる部分が多いからです。
エフェクターによる歪みよりも、アンプ本体のクリーントーンや軽いクランチを軸にしている点は大きな特徴。必要に応じてブースターやローゲインのオーバードライブを追加し、アンプ本来のサウンドを活かすスタイルを採用していると考えられます。
したがって、長谷部悠生のアンプ選びは「Fenderらしいクリーン+リバーブ」を核に、ファンク/ソウルのギターサウンドに最適化されたセッティングを意識している、と想定されます。
使用ギターの種類と特徴【Kroi・長谷部悠生】

長谷部悠生のサウンドを支える最大の要素は、多彩なギターコレクションです。ジャンル横断的なKroiの楽曲に合わせ、彼は曲ごとに最適なトーンを選び分けています。その中でも特に重要なのが、近年のメイン機材として導入されたGibson 1958 Les Paul Standard “Lemon Burst / Green Lemon” Light Aged(Murphy Lab)です。
このモデルは武道館ワンマンに合わせて導入され、「軽めの個体」「リアが良い音」と本人が語っていることから、ライブにおいて強い存在感を発揮する一本であることがわかります。ヴィンテージライクなトーンと現代的なプレイアビリティを両立させており、Kroiのグルーヴィーなカッティングからソロまで幅広く対応します。
次に注目すべきはGibson SG。2021年に初めて手に入れたGibsonギターであり、バンドの成長期に寄り添ってきた一本です。SG特有の軽量さと歯切れの良い中高域は、長谷部のファンキーなカッティングスタイルに自然にフィットし、ステージでの扱いやすさも際立っています。
また、Gibson ES-335(1970年代ヴィンテージ)も所有しており、本人が「自分の70sヴィンテージを持っている」と明言。セミアコ特有のウォームなトーンは、ソウルフルなフレーズやバラードでの表現力を高めています。335の丸みある中域は、Kroiのサウンドの中でも特にムードを演出する場面で活躍していると考えられます。
さらに、Fender Stratocasterも重要な存在です。所有明記はないものの、インタビューで「ほぼ全曲で試す」「カッティングはだいたいストラト」と語っており、レコーディングの現場では欠かせない一本といえます。シングルコイル特有のシャープで立ち上がりの速い音は、ファンクやR&B寄りのリズムに最適であり、ストラトを使うことで楽曲全体のノリがよりタイトに引き締まります。
このほか、Epiphone Inspired by Gibson CustomシリーズやFender Acoustasonic Player Telecasterなども試奏動画やインタビューで取り上げられています。特にAcoustasonicについては「1本でライヴもいける」と高評価をしており、今後のステージ投入が期待されます。
以上のように、長谷部のギターは「レスポールの太さ」「ストラトのキレ」「セミアコの温かみ」を巧みに使い分けることで、Kroiの多彩な楽曲に対応しています。したがって、時期や楽曲ごとにギターを選び分けるスタイルこそが彼の音作りの核である、と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | ギターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 Les Paul Standard “Lemon Burst / Green Lemon” Light Aged(Murphy Lab) | Gibson | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | エレキギター(レスポール) | 武道館ワンマンに合わせて導入。メイン機。軽量個体でリアPUサウンドを評価。 |
| SG(年式不詳) | Gibson | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | エレキギター(SG) | 2021年に初めて購入したGibson。ライブで使用。 |
| ES-335(1970年代ヴィンテージ) | Gibson | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | エレキギター(セミアコ) | 所有を明言。70年代ヴィンテージ。バラードやソウル寄り楽曲に活用。 |
| Stratocaster(モデル不詳) | Fender | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | エレキギター(ストラトキャスター) | 所有明記はなし。レコーディングでほぼ全曲試す。カッティング中心。 |
| Acoustasonic Player Telecaster | Fender | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | エレアコ/ハイブリッド | 試奏動画で「1本でライヴもいける」と評価。今後使用の可能性あり。 |
使用エフェクターとボード構成【Kroi・長谷部悠生】
長谷部悠生のペダルボードに関しては、現時点で具体的な機種名や写真による一次情報は確認されていません。しかし、本人のサウンド傾向やインタビューから推測される構成を整理すると、ファンクやR&Bに最適化されたシンプルで実用的なボードが想定されます。
まず重要なのは、アンプ内蔵のスプリング・リバーブ。代表曲「Funky GUNSLINGER」ではこのリバーブを深めにかけ、カッティングの余韻を広げる使い方が確認されています。外付けリバーブペダルを使わなくても十分に個性を出せる点は、Fenderアンプを軸にしている彼ならではの特徴です。
次に考えられるのは、リズムの粒立ちを揃えるコンプレッサー。ファンク寄りのカッティングでは音量差が出やすいため、コンプレッサーで音を均一化し、歯切れの良さを確保する可能性が高いです。Keeley CompressorやBOSS CSシリーズなどの定番機種を想定すると自然です。
さらに、音の輪郭をコントロールするためにブースター/ローゲインオーバードライブを軽く加えるスタイルも推測されます。アンプ自体を歪ませすぎず、ブースターで押し出すことで、クリーンの芯を残しながら迫力をプラスするのはファンク・ソウル系ギタリストの定番手法です。
加えて、楽曲によってはワウペダルが導入されている可能性もあります。Kroiのグルーヴ主体の楽曲では、ワウをリズムに合わせて踏み込むことで、よりファンキーで動きのあるサウンドが生まれます。
空間系としてはディレイを薄く使う場面も考えられます。ソロやアルペジオで残響を加え、立体感を演出するための最小限のセッティングです。ただし、彼のサウンドの主軸はリバーブにあるため、ディレイはあくまで補助的に使われていると想定されます。
最後に必須なのはチューナーとパワーサプライ。プロ現場では安定した電源供給が不可欠であり、ライブごとに安定したピッチを保つためのチューナーは欠かせません。
以上の要素をまとめると、長谷部悠生のエフェクト構成は「シンプルだが本質的」であり、アンプとギターの持ち味を最大限に活かしつつ、必要最低限のペダルで機能性を補っている、と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | エフェクターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蔵スプリング・リバーブ | Fender(アンプ内蔵) | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | リバーブ | 「Funky GUNSLINGER」で強めに使用。アンプ由来。 |
| コンプレッサー(推定:Keeley Compressor/CSシリーズ等) | Keeley / BOSS | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | コンプレッサー | カッティングの粒を揃える目的で使用想定。具体モデルは未確認。 |
| ブースター/ローゲインOD(推定) | BOSS / Xotic ほか | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | ブースター | アンプのクリーンを押し出す用途。具体モデルは不明。 |
| ワウペダル(推定) | Dunlop Cry Baby 等 | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | ワウペダル | ファンク的リズム表現での使用が想定される。現状写真証拠なし。 |
| ディレイ(推定) | BOSS DDシリーズ ほか | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | ディレイ | ソロで薄く使う可能性あり。基本はリバーブ主体。 |
| チューナー | BOSS / KORG 等 | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | チューナー | ライブ・レコーディング必須。具体モデル未確認。 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【Kroi・長谷部悠生】

長谷部悠生の音作りは、アンプ・ギター・エフェクターを最小限に組み合わせることで、Kroi特有のグルーヴ感を最大化する方向にまとめられています。その核となるのは、Fender Hot Rod DeVilleを中心としたクリーントーンとスプリング・リバーブの扱いです。本人がインタビューで語っているように、アンプ側のハイ(トレブル)を抑えてミドルとローを持ち上げ、リアピックアップで強くアタックすることで、芯のあるファンキーなカッティングが生まれます。
EQ設定の具体例としては、アンプのトレブルを「4前後」、ミドルを「6〜7」、ベースを「5〜6」に設定するイメージです。こうすることで、耳に刺さる高音を抑えながらも、バンド全体の中でギターが埋もれない立ち位置を確保できます。プレイのニュアンスを拾いやすくするために、プレゼンスはあまり強調せず、あくまでリズムの一部として機能させることを意識していると考えられます。
カッティング主体の曲では、ピックアップセレクターをリアに固定しつつ、ギターのトーンノブを絞りすぎないように調整。これはファンク系プレイヤーに共通するセッティングであり、音抜けを保ちながらリズムのキレを維持する狙いがあります。一方で、バラードやソウル寄りの楽曲ではES-335を用いてフロント寄りのセッティングに切り替え、ウォームで空気感のあるトーンを作り出しています。
レコーディングにおいては、ストラトキャスターを多用し、シングルコイルのシャープなアタックを積極的に取り入れている点も特徴的です。「カッティングはだいたいストラト」と語っているように、特にスタジオワークではシングルコイルの生っぽい質感を活かす工夫をしているといえます。これにより、ミックスの中でもギターが埋もれずにリズムの輪郭を強調することが可能です。
ミックス処理に関しては、コンプレッションを軽めにかけて音量差を均一化する一方、余計なEQ処理を避け、ギター本来のニュアンスを残す方向が採用されていると推測されます。特にリバーブについては、デジタル処理ではなくアンプ内蔵のスプリング・リバーブを録音段階で積極的に使い、その独特の揺らぎを音源に取り込んでいる点が重要です。
ライブとレコーディングでの違いもポイントです。ライブでは音抜けを重視し、リズムの中で埋もれないようにハイを少し上げる傾向があります。一方でレコーディングでは、楽曲全体のバランスを考慮してよりロー〜ミッド寄りに設定し、厚みと温かさを強調する傾向があると考えられます。
また、Kroiはベースやドラムのリズムが楽曲を牽引するバンドであるため、ギターが主張しすぎないことも大切です。そのため、ソロ時以外は歪みをほとんど使わず、クリーン〜クランチ領域にとどめているのが長谷部の大きな特徴といえるでしょう。
総合すると、長谷部悠生の音作りは「クリーントーンを基盤に、EQで不要な帯域を整理し、リバーブで空間を演出する」ことに尽きます。機材の多さよりも、選び抜いたギターとアンプの組み合わせで表現する姿勢が、Kroi特有の都会的でファンキーなサウンドを形作っている、と想定されます。
比較的安価に音を近づける機材【Kroi・長谷部悠生】
長谷部悠生の音作りをそのまま再現しようとすると、Murphy Labのレスポールや70sのES-335といった高額なヴィンテージ系機材が必要になり、初心者にとっては現実的ではありません。しかし、基本となる要素を押さえれば、より安価な機材で“長谷部サウンド”に近づけることは可能です。
彼のサウンドの根幹は「クリーンで粒立ちの良いトーン」「カッティングに適したレスポンス」「深めのスプリング・リバーブ活用」にあります。そのため、初心者や中級者は以下のような機材を選ぶと再現度が高まります。
まずギターでは、GibsonやFenderの本家モデルに手が届かない場合、EpiphoneやSquierが選択肢になります。EpiphoneのLes Paul Standardは、太いサウンドとシンプルな操作性を持ち、レスポール系のトーンを学ぶのに最適です。また、Squier Classic VibeシリーズのStratocasterは、シングルコイルのカッティングに特化したサウンドを手頃に体験できます。
アンプは、Fender系のトーンを手軽に得られるBOSSのKATANAシリーズがおすすめです。特にKATANA-50 MkIIは、クリーンチャンネルが優秀で、リバーブやEQ調整もしやすく、自宅練習から小規模ライブまで対応できます。Fender Champion 40なども同価格帯で、Fenderらしい煌びやかなクリーントーンが魅力です。
エフェクターでは、BOSS CS-3(コンプレッサー)を導入すれば、ファンク的な粒立ちを整えたカッティングが容易に再現できます。さらにBOSS SD-1(オーバードライブ)は、軽めのブースト用途で活躍し、アンプのクリーンを少し押し出すのに最適です。ワウペダルとしては定番のDunlop Cry Babyを選べば、グルーヴィーなフレーズを強調することができます。
こうした構成を組み合わせれば、10万円以下でも長谷部悠生の音作りにかなり近づけることが可能です。大切なのは、機材の価格ではなく「クリーンを基盤にリズムを意識したEQとリバーブの扱い」を学ぶことにあります。
| 種類 | 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギター | Les Paul Standard | Epiphone | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | 本家Gibsonの代替に最適。太いサウンドでレスポール系の特徴を再現。 |
| ギター | Classic Vibe Stratocaster | Squier by Fender | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | カッティング主体の音作りに最適。コストパフォーマンス高。 |
| アンプ | KATANA-50 MkII | BOSS | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | Fender系クリーンに近いサウンドを持つ。リバーブ搭載で練習〜ライブ対応。 |
| アンプ | Champion 40 | Fender | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | 安価にFenderらしい煌びやかなクリーントーンを得られるモデル。 |
| エフェクター | CS-3 | BOSS | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | コンプレッサー。ファンク的カッティングの粒を揃えるのに有効。 |
| エフェクター | SD-1 | BOSS | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | ブーストや軽い歪みに最適。アンプのクリーンを押し出す役割。 |
| エフェクター | Cry Baby | Dunlop | Amazonで探す | Kroi | 長谷部悠生 | ファンキーなニュアンスを演出する定番ワウペダル。 |
総括まとめ【Kroi・長谷部悠生】

長谷部悠生の音作りを振り返ると、その本質は「引き算の美学」にあるといえます。派手な歪みや複雑なエフェクトに頼るのではなく、ギターとアンプ本来のポテンシャルを最大限に活かし、EQとリバーブで緻密に空気感をコントロールするスタイルです。これにより、Kroiの楽曲に不可欠なリズム感とグルーヴを強調しながら、全体のサウンドに溶け込みつつも存在感を放っています。
特に特徴的なのは、レスポールの太い鳴りとストラトの鋭いカッティングを楽曲ごとに使い分けている点です。さらにES-335の温かみやセミアコ特有の中域を加えることで、バンド全体の色彩を豊かにしています。機材そのものの選択眼はヴィンテージ志向ですが、実際の使い方は現代的で、曲ごとに適切なキャラクターを与える柔軟さがあります。
また、アンプのセッティングにおいても「高音を抑え、中域と低域で厚みを作る」という明確な方向性があり、ここに本人の音作り哲学が感じられます。ファンクやR&B寄りのカッティングではコンプレッションを効かせ、ブースターで押し出しながらクリーンの芯を残す。ソウルやバラードではセミアコやフロントPUを使い、温かく深いトーンを生み出す。これらのバランス感覚こそが長谷部悠生のギタリストとしての魅力です。
初心者や中級者が彼の音を目指す場合、必ずしも高額なギターやアンプを用意する必要はありません。重要なのは、クリーンを基盤にしたセッティング、リズムを意識したプレイ、そして必要最小限のエフェクトでサウンドを補強するという姿勢です。例えばBOSS CS-3やSD-1のような安価な定番ペダルと、Fender系のアンプ(もしくはシミュレーター)を組み合わせれば、十分に長谷部らしいファンキーなトーンを再現できます。
最終的に、長谷部悠生の音作りの特徴は「バンド全体のグルーヴを活かすための音作り」であるといえます。ギター単体で完結させるのではなく、リズム隊やボーカルとの関係性を重視し、自分のトーンを“全体のピース”として機能させる。その考え方こそが、Kroiの都会的かつソウルフルなサウンドを形作っているのです。
つまり、長谷部悠生の音を真似るために必要なのは「高級機材」ではなく「リズム感とEQへの理解」。それを意識することで、あなたの演奏もぐっとKroiらしく洗練されたものになるでしょう。
“`
下記恐らく使用(所持)している機材のまとめです。参考までに!
ギター
Gibson 1958 Les Paul Standard “Lemon Burst / Green Lemon” Light Aged(Murphy Lab)
近年のメイン。武道館ワンマンに合わせて導入。「軽め個体」「リアが良い音」と言及。
Gibson Japan
Gibson SG(年式・仕様不詳)
2021年に初めて手にしたGibsonとして購入。
Gibson Japan
Gibson ES-335(1970年代ヴィンテージ)
所有を明言。試奏比較コメント内で“自分の70sビンテージを持っている”と発言。
ギター・マガジンWEB|Guitar magazine
Fender Stratocaster(レコーディングで頻用)
所有明記はなし。“ほぼ全曲で試す/カッティングはだいたいストラト”と述べる。
FenderNews
試奏/企画で使用(所有情報なし)
Epiphone Inspired by Gibson Custom
1959 Les Paul Standard Reissue / 1957 Les Paul Goldtop Reissue / 1960 Les Paul Special Double Cut Reissue / 1962 ES-335 Reissue / 1963 Firebird V Maestro Vibrola Reissue / 1964 SG Standard with Maestro Vibrola Reissue を動画連動で試奏。
ギター・マガジンWEB|Guitar magazine
Fender Acoustasonic Player Telecaster
高評価コメント(“1本でライヴもいける”“レックやツアーで使えそう”)。
FenderNews
アンプ
Fender Hot Rod DeVille
“人生で最初に自分で買ったアンプ”。レコーディングでも活用。
FenderNews
例:「Funky GUNSLINGER」でスプリング・リバーブを強め、アンプ側でハイを落としギターはリアPUで突く設定を採用。
FenderNews
エフェクター
アンプ内蔵スプリング・リバーブ(作品で強めに使用した記述あり)。
FenderNews
(想定) 公開された具体的ペダル名は見当たらず※。音楽性・言及(ファンク/R&B寄りのカッティング、リアPUの活用、アンプ・リバーブ多用)から、コンプレッサー, ブースター/ローゲインOD, ワウ, ディレイ(薄く), チューナー等の基本的ペダル構成の可能性は高いと判断。※個別モデル名は不明のため“想定”止まり。
※ペダルボード写真・型番特定の一次情報(雑誌/公式SNS/個人ブログの検証写真など)は現時点で確認できませんでした。