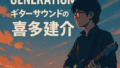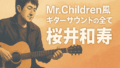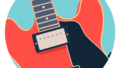始めに(特徴紹介)
Helsinki Lambda Club(ヘルシンキラムダクラブ)のギタリスト・熊谷太起は、独自のギターサウンドでバンド全体の雰囲気を支える存在です。彼のギターは単にコードを鳴らすだけでなく、時には歪みを効かせたリフで楽曲の推進力を作り、時には空間系エフェクトで幻想的なサウンドスケープを描き出します。
特にHelsinki Lambda Clubの楽曲は、ポストパンクやインディーロックの影響を受けながらも、ポップでキャッチーなメロディを兼ね備えています。その中で熊谷のギターは「攻め」と「余白」を絶妙に使い分け、楽曲の中に奥行きを生み出しています。
代表曲である「PIZZASHAKE」や「イースタン・ユース」では、オレンジのアンプ特有の温かみあるクランチと、空間系エフェクトを組み合わせたサウンドが印象的です。これにより、単なるインディーロックを超えて、独自のアート性を持った音像を作り出しているのです。
また、熊谷はライブでの再現性を非常に重視しており、複雑なエフェクターボードを駆使して、レコーディングさながらの音を再現していることでも知られています。BOSS ES-8を中心としたスイッチャーシステムにより、複数のエフェクターを自在に組み合わせるスタイルは、彼の音作りの大きな特徴といえるでしょう。
彼の音作りを理解することは、Helsinki Lambda Clubの音楽の核心に触れることでもあります。これから紹介するアンプ、ギター、エフェクターの構成を見ていくことで、熊谷太起のサウンドがどのように構築されているのかを紐解いていきます。
▶ Helsinki Lambda Club の公式YouTube動画を検索
使用アンプ一覧と特徴【Helsinki Lambda Club・熊谷太起】
熊谷太起がメインで使用しているアンプは、英国ブランドのOrange社製「AD30」ヘッドと「PPC212B」キャビネットの組み合わせです。このアンプ構成は、インディーロックやガレージロック系のギタリストに好まれるクラシックなサウンドを生み出すことで知られています。AD30は真空管アンプならではのナチュラルなコンプレッションと太い中域が特徴で、バンド全体の音に埋もれることなく存在感を放ちます。
AD30のクランチサウンドは、軽いピッキングではクリーン寄り、強く弾けば歪みが立ち上がるというダイナミックレンジの広さを持っています。熊谷のスタイルはこの特性を最大限活かしており、シンプルなコードワークであっても繊細なニュアンスが表現できるようになっています。特にライブにおいては、ギターのボリュームノブとピッキング強弱だけで曲中の表情を変えることができるのが大きな魅力です。
また、キャビネットに使用される「PPC212B」は、Celestion Vintage 30スピーカーを搭載しており、ミッドレンジが豊かでカッティングもリードも前に出るサウンドが得られます。ステージ上でも明瞭に聴こえるため、ボーカルや他の楽器に埋もれにくく、Helsinki Lambda Clubのツインギター体制においても絶妙なバランスを保っています。
他の可能性としては、スタジオや小規模会場でFender系のアンプを使ったとされる情報も一部で見られます。特にTwin Reverbなどのクリーンアンプとペダルで音を作るスタイルは、同系統のインディーロックバンドではよく採用されるため、熊谷が状況に応じて使い分けていた可能性もあります。ただし、公式なインタビューや写真ではOrange AD30の使用が最も多く確認されています。
総じて、熊谷のアンプセッティングは「クランチベースに多彩なエフェクトを重ねる」ことを軸にしていると考えられます。エフェクターで作り込んだ音が映える下地を作るのに、AD30のようなシンプルで表現力豊かなアンプは非常に適しており、彼の音作りの根幹を支えているといえるでしょう。したがって、彼のライブサウンドを再現するには、まずこのOrangeアンプの特性を理解することが欠かせない、と想定されます。
使用ギターの種類と特徴【Helsinki Lambda Club・熊谷太起】

熊谷太起のギターといえば、近年のライブやインタビューでたびたび登場しているのが、D’Angelico社の「Deluxe Bedford SH Matte Walnut with Wilkinson 6-point Tremolo」です。セミホロウ構造を採用しつつも、ボディは軽量で取り回しが良く、モダンかつビンテージライクなルックスが印象的です。ウィルキンソン製の6点支持トレモロを搭載しているため、アーミングプレイや微妙なピッチ変化を生かした表現力豊かな演奏が可能です。
このギターの大きな特徴は「セミホロウ構造」と「SSピックアップの組み合わせ」によるサウンドです。セミホロウ特有の空気感や倍音が、Helsinki Lambda Clubの楽曲に漂うサイケデリックな雰囲気を支えています。歪ませても芯が残り、クリーントーンではウォームで立体感のある響きが得られるため、インディーロックからポップスまで幅広く対応できる仕様です。
また、熊谷はD’Angelicoをメインとしつつ、過去にはFender系のギター(MustangやTelecaster系)を使用していた可能性もファンの間で指摘されています。インディー系の音楽シーンでは、取り回しの良さや独特のジャングリーなサウンドを求めて、複数本のギターを使い分けることが一般的です。特にHelsinki Lambda Clubのように多彩なアレンジを施すバンドにおいては、楽曲やツアーごとにサブギターを導入していた可能性は高いといえます。
Deluxe Bedford SHは、モダンなギターでありながらもジャズ的なトーンからロックな歪みまでをカバーできる万能性があり、熊谷がライブで自在に音色を操る姿はこのギターのポテンシャルを最大限に引き出していることを示しています。さらに、ホロウ構造ゆえの軽量さは長時間のステージでも負担を軽減し、実際のライブパフォーマンスにも大きく寄与しています。
総じて熊谷太起のギターセレクトは「汎用性」と「独自性」の両立に重きを置いているといえます。フェンダーのような定番機種ではなく、D’Angelicoのような個性的なブランドを選ぶことで、音のキャラクターにも一貫性と差別化を持たせているのです。したがって、熊谷が今後もメインギターとしてD’Angelicoを中心に据えつつ、楽曲やシーンに応じて他のギターを併用していくことが想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | ギターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Bedford SH Matte Walnut with Wilkinson Tremolo | D’Angelico | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | セミホロウ・エレキギター | メイン使用ギター。セミホロウ特有の空気感と多彩な音作りが可能。 |
使用エフェクターとボード構成【Helsinki Lambda Club・熊谷太起】
熊谷太起のエフェクターボードは、Helsinki Lambda Clubの楽曲で聴ける多彩なサウンドを支える中核です。彼はBOSSのスイッチャー「ES-8」を中心に構築された複雑なシステムを用いており、複数の歪み・空間系・変調系エフェクトを自在に切り替えています。ライブにおいても楽曲ごとに緻密にプログラムされたセッティングを再現できるのは、このスイッチングシステムの恩恵によるものです。
歪み系では「EarthQuaker Devices / Plumes」「Friedman / BE-OD Deluxe」「JHS Pedals / Kilt」「ELECTROGRAVE / Peipper Fuzz」と、4種類ものドライブ・ファズを使い分けています。Plumesはクリアなオーバードライブ、BE-OD Deluxeはマーシャル系のハイゲインディストーション、Kiltはブーストやオーバードライブ寄りの歪み、Peipper Fuzzはノイズ感の強いファズと、それぞれ異なるキャラクターを持っているため、楽曲に応じて音の色彩を切り替えることが可能です。
空間系では「BOSS / DD-500」「BOSS / MO-500」「Strymon / BigSky」といった、いずれもプロの間で高評価を得ている高機能デジタルエフェクターを導入。DD-500は多彩なディレイアルゴリズム、MO-500はモジュレーション全般、BigSkyは豊かなリバーブ空間を作り出し、熊谷のプレイに奥行きと浮遊感を与えています。特にBigSkyのシマーリバーブなどは、Helsinki Lambda Club特有のドリーミーな音像に直結している要素といえます。
さらに「Old Blood Noise Endeavors / BL-44 Reverse Variable Clock Reverser」や「Paradox Effects / Arquitecto」といったユニークなエフェクターも導入しており、逆再生的なサウンドや非現実的なモジュレーション効果を加えることで、楽曲に実験的な要素を注入しています。これらのセレクトは熊谷の音作りにおける冒険心を示すものであり、単なるコピーではなく「熊谷らしい音」を形成する源といえるでしょう。
ボード全体の電源供給は「Fender / Engine Room LVL12 Power Supply」によって安定化されています。電源をしっかり管理することで、大型デジタルエフェクターや複数の歪みペダルを同時に駆動してもノイズを最小限に抑えることが可能になります。ライブやスタジオワークで常に安定したサウンドを提供できるのは、この電源管理の徹底も大きな要因です。
こうして整理すると、熊谷太起のペダルボードは「歪みの多彩さ」「空間系の厚み」「実験的な特殊エフェクト」の3要素で構成されており、それらをES-8で自在に操ることで、楽曲ごとに独自の音世界を描いていることがわかります。確定的な使用情報は公式SNSやライブ写真で確認されていますが、楽曲や時期に応じて一部の機材は入れ替わっている可能性もあり、すべてのペダルが常時固定されているわけではないと想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | エフェクターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compressor Plus | Keeley | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | コンプレッサー | ピッキングニュアンスを整え、音の粒を揃える用途。 |
| PolyTune 3 | TC Electronic | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | チューナー | ライブで必須の定番チューナー。常時ボードに組み込み。 |
| ES-8 Effects Switching System | BOSS | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | スイッチングシステム | 複雑なエフェクト切り替えを一括管理。ライブで必須。 |
| Plumes | EarthQuaker Devices | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | オーバードライブ | クリーンで明るいドライブ。コードワークに適用。 |
| BE-OD Deluxe | Friedman | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | ディストーション | マーシャル系ハイゲインサウンドを提供。 |
| Kilt | JHS Pedals | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | オーバードライブ/ブースター | ゲインブーストや荒い歪みに使用。 |
| Peipper Fuzz | ELECTROGRAVE | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | ファズ | ノイジーでラウドな質感を楽曲に付与。 |
| MO-500 | BOSS | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | モジュレーション系 | 多彩なコーラスやフェイザー効果を提供。 |
| BL-44 Reverse Variable Clock Reverser | Old Blood Noise Endeavors | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | ノイズ系エフェクター | 逆再生的な効果を加えるユニークなサウンド。 |
| Arquitecto | Paradox Effects | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | モジュレーション系 | 実験的で立体的な効果を楽曲に追加。 |
| DD-500 | BOSS | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | ディレイ | 多機能ディレイ。空間の広がりを演出。 |
| BigSky | Strymon | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | リバーブ | ドリーミーな空間系サウンドの要。 |
| Engine Room LVL12 Power Supply | Fender | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | パワーサプライ | 安定した電源供給でノイズレス環境を維持。 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【Helsinki Lambda Club・熊谷太起】

熊谷太起の音作りにおける核心は「アンプのナチュラルクランチ」と「多層的なエフェクトの組み合わせ」にあります。Orange AD30を基本に据えた場合、アンプ側はゲインを抑えめに設定し、軽いピッキングでクリーン〜クランチ、強いピッキングで歪みに寄るように調整されています。EQは中域をしっかり持ち上げ、低域は抑え気味に設定することで、バンド全体の中で抜けの良い音を確保しています。
具体的な例を挙げると、AD30のトーン設定はBassを10〜11時、Middleを1〜2時、Trebleを12時前後にすることが多いと推測されます。これにより、ベースやドラムと干渉しすぎず、かつギターの存在感を失わない帯域が作られます。Gainは12時前後で、Volumeは会場規模に応じて調整。ライブではマイキングを前提としたセッティングであるため、アンプから直接出ている音はややドライ寄りで、PAで空間系を足していると想定されます。
歪み系エフェクトの使い分けも重要です。オーバードライブの「Plumes」は軽い歪みを追加し、コード感を損なわない透明感を保つために使用。激しい楽曲では「BE-OD Deluxe」でマーシャルライクなハイゲインを得て、リフやソロを前面に押し出しています。さらに「Kilt」をブースターとして組み合わせることで、音量を持ち上げつつドライブ感を強調する使い方もされています。ファズである「Peipper Fuzz」は、ノイジーで実験的な場面やアウトロでの爆発力を演出するために使用される傾向があります。
空間系では「DD-500」のディレイがリズムギターの刻みやフレーズに厚みを加え、「BigSky」のリバーブが楽曲全体に浮遊感を付与しています。特にシマー系リバーブは、Helsinki Lambda Clubの楽曲に多く見られるドリーミーな質感に欠かせない要素です。「MO-500」や「Arquitecto」といったモジュレーション系は、楽曲ごとにコーラスやビブラート的な揺れを加える用途で使われ、クリーントーンの単調さを避けています。
また、特殊系エフェクト「BL-44 Reverse Variable Clock Reverser」の逆再生的な効果は、録音物ではエディットやリバース処理に頼る部分をライブで再現するための要となっています。これにより、レコーディングと同等のサイケデリックな質感を観客に届けられるのです。
ミックスの観点では、熊谷のギターはあえて「中央に置かれすぎない」定位を取っていると考えられます。Helsinki Lambda Clubはツインギター編成であり、熊谷のサウンドはやや左寄りにパンニングされ、もう一方のギターとの対比によって立体的な音場が形成されます。EQ処理においても、エンジニアはギターの高域を少しロールオフし、中域を浮き立たせることで、耳に刺さらずにバンド全体の中で埋もれないサウンドを実現していると想定されます。
総じて熊谷太起の音作りは「シンプルなアンプ設定を基盤に、多彩なペダルで色付けする」ことに尽きます。アンプ単体のセッティングは比較的オーソドックスですが、その上に加えるエフェクトの組み合わせと使い分けが独自の個性を生み出しています。PAやレコーディングでは、その音を適切に定位・EQ処理することで、リスナーに「熊谷の音」として届くように工夫されているのです。したがって、彼のセッティングを再現したい場合は、アンプをシンプルに鳴らし、エフェクトで世界観を作り込む姿勢が不可欠だといえるでしょう、と想定されます。
比較的安価に音を近づける機材【Helsinki Lambda Club・熊谷太起】
熊谷太起が使用する機材は、プロ仕様の高価なモデルが多いため、初心者や中級者にとってはハードルが高い部分もあります。しかし、音作りの「エッセンス」をつかむことで、比較的安価な機材でも近しいサウンドを再現することは可能です。ここでは1万〜5万円程度で入手できる市販モデルを中心に、再現性の高い代替機材を紹介します。
まず歪み系では、熊谷が使う「Friedman BE-OD Deluxe」の代替として、BOSSの「DS-1」や「ST-2 Power Stack」が有力候補です。DS-1は王道のディストーションとして長年愛されており、アンプライクな歪みを作りやすいです。ST-2はマーシャル的なクランチ〜ハイゲインをシミュレートできるため、BE-OD Deluxeの代わりとしてライブで十分通用します。
オーバードライブでは、EarthQuaker Devices Plumesの代替に「BOSS SD-1 Super OverDrive」が適しています。Plumes同様、明るいトーンとクリーンさを兼ね備えており、コードプレイでも音が濁りにくい特性を持ちます。さらに、JHS Kiltのようなブースト的用途には「BOSS BD-2 Blues Driver」が役立ちます。こちらはゲイン幅が広く、軽いクランチから力強いブーストまで対応可能です。
ファズに関しては、ELECTROGRAVE Peipper Fuzzの代わりとして「Electro-Harmonix Big Muff Nano」が定番です。ノイジーで分厚い壁のようなサウンドが特徴で、シューゲイザーやインディーロック的な轟音サウンドに最適です。
空間系では、Strymon BigSkyやBOSS DD-500のような高級マルチ空間系の代替として「BOSS RV-6(リバーブ)」と「BOSS DD-8(ディレイ)」を組み合わせるのが効果的です。RV-6はシマーリバーブも搭載しており、BigSkyに近い浮遊感を安価に再現できます。DD-8はタップテンポ機能を持ち、DD-500ほど多機能ではないもののライブでの汎用性が高いです。
モジュレーションに関しては「BOSS CE-2W Chorus」や「MXR Phase 90」などが候補となります。MO-500の多彩さには及びませんが、シンプルにコーラスやフェイザーを足すことで、熊谷が持つ揺らぎあるサウンドを安価に再現できます。
電源面では、Fender Engine Roomの代替として「One Control / Distro Minimal」や「CAJ / AC/DC Station」などのリーズナブルなパワーサプライがおすすめです。電源の安定性は音質に直結するため、安価に導入できるモデルでも大きな効果があります。
総合的にまとめると、「BOSS製エフェクターを中心に組み合わせること」が、熊谷太起サウンドを安価に再現する最も手軽で確実な方法です。特にSD-1やRV-6、DD-8といった定番モデルを揃えるだけで、Helsinki Lambda Clubの楽曲で聴ける浮遊感あるクランチサウンドを十分体験できるでしょう。
| 種類 | 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディストーション | DS-1 | BOSS | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | BE-OD Deluxeの代替。定番のディストーション。 |
| オーバードライブ | SD-1 Super OverDrive | BOSS | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | Plumesの代替として明るいトーンを再現可能。 |
| ブースター/オーバードライブ | BD-2 Blues Driver | BOSS | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | Kiltの代替。幅広いゲイン調整が可能。 |
| ファズ | Big Muff Nano | Electro-Harmonix | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | Peipper Fuzzの代替。ノイジーで厚みのある轟音。 |
| リバーブ | RV-6 | BOSS | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | BigSkyの代替。シマーリバーブ搭載。 |
| ディレイ | DD-8 | BOSS | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | DD-500の代替。ライブで使いやすい機能を搭載。 |
| モジュレーション | CE-2W Chorus | BOSS | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | MO-500の代替。シンプルながら深みのあるコーラス。 |
| パワーサプライ | Distro Minimal | One Control | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 熊谷太起 | Engine Roomの代替。小型軽量で安定した電源供給。 |
総括まとめ【Helsinki Lambda Club・熊谷太起】

熊谷太起の音作りを総合すると、その本質は「アンプの素直なクランチを軸に、多層的なエフェクトで彩る」という一点に集約されます。彼は決して歪みを過剰に頼るタイプではなく、ピッキングの強弱やボリューム操作といったギタリスト自身のニュアンスを大切にしながら、必要な場面でエフェクターを加えて世界観を演出しています。この「人間的なニュアンス+機材の多彩な響き」のバランスこそ、Helsinki Lambda Clubのギターサウンドを特別なものにしている要素です。
具体的には、Orange AD30のナチュラルなクランチを土台に、PlumesやBE-OD Deluxeといった歪み系で強弱をつけ、さらにBigSkyやDD-500などの空間系で奥行きを与えています。ここにリバースや特殊モジュレーション系エフェクトを加えることで、独自の幻想的かつサイケデリックな音像が形成されています。これはただのギタープレイではなく、楽曲全体の「サウンドデザイン」の一部として機能しているのが特徴です。
また、彼のボード構成を見れば分かるように「幅広いジャンル性への対応力」も意識されています。ガレージロックのラフさから、ポップなカッティング、実験的なノイズアプローチまで、すべてをライブで瞬時に呼び出せる体制を整えているのは、BOSS ES-8を中心としたスイッチングシステムの存在が大きいでしょう。ライブごとに音作りを緻密に再現できる点は、熊谷のプロ意識を強く感じさせます。
もし読者が熊谷太起の音を再現したいと考えるなら、まず「アンプでの基本クランチ」を理解することが最重要です。その上で、オーバードライブとリバーブ/ディレイの組み合わせを意識するだけで、雰囲気を大きく近づけることができます。さらに余裕があれば、逆再生系やファズを導入すると、彼らしいサイケデリックな質感をより強く再現できるでしょう。
総じて熊谷の音作りは、単なる「機材の組み合わせ」ではなく「楽曲の世界観をどう提示するか」というアーティスト視点に基づいています。そのため再現を目指す際も、同じ機材を揃えるだけでなく「曲ごとの空気感をどう表現するか」を意識することが欠かせません。つまり、熊谷太起の音の本質は「表現力と実験精神」であり、それがHelsinki Lambda Clubのユニークなサウンドを支えているのです。
“`
下記恐らく使用(所持)している機材のまとめです。参考までに!
ギター
D’Angelico / Deluxe Bedford SH Matte Walnut with Wilkinson 6-point Tremolo
エフェクター
Keeley / Compressor Plus
TC Electronic / PolyTune 3
BOSS / ES-8 Effects Switching System
EarthQuaker Devices / Plumes
Friedman / BE-OD Deluxe
JHS Pedals / Kilt
ELECTROGRAVE / Peipper Fuzz
BOSS / MO-500
Old Blood Noise Endeavors / BL-44 Reverse Variable Clock Reverser
Paradox Effects / Arquitecto
BOSS / DD-500
Strymon / BigSky
Fender / Engine Room LVL12 Power Supply
アンプ
Head:Orange / AD30
Cabinet:Orange / PPC212B