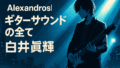始めに(特徴紹介)
Crystal Lakeのギタリスト、Shinya Horiは、モダン・メタルコアを象徴するような重量感と切れ味を兼ね備えたサウンドで知られています。
彼のプレイは、7弦ギターを駆使したローエンドのリフから、メロディアスなフレーズやクリーントーンまで幅広く、バンドの音像を強烈に支える存在です。
代表曲である「Apollo」や「True North」では、タイトで攻撃的なリフと空間的な広がりを持つクリーントーンが交錯し、海外フェスでも高い評価を得ています。
特にAxe-Fx II XL+を中心としたモダンなデジタルシステムは、ライブとスタジオの両面で安定した音作りを可能にしている点が特徴的です。
さらに、Horiのサウンドはメタルコアの典型であるドロップチューニングや7弦ならではの重厚さを取り入れつつも、単なる重低音だけでは終わらず、煌びやかで立体感のあるギタートーンを実現しています。
このバランス感覚が、国内外でCrystal Lakeを唯一無二の存在に押し上げていると言えるでしょう。
彼の音作りは、メタルコア、デスコア、ポストハードコアといったジャンルを横断するファンにとって参考になる要素が多く、特に現代的なマルチエフェクターやEvertune搭載ギターを活用した安定性は注目に値します。
以下では、実際に確認されたアンプやギター、エフェクター構成をもとに、Crystal LakeのShinya Horiがどのようにしてその強靭なサウンドを作り上げているのかを解説していきます。
▶ Crystal Lake の公式YouTube動画を検索
使用アンプ一覧と特徴【Crystal Lake・Shinya Hori】
Crystal LakeのShinya Horiが実際に使用しているアンプシステムは、従来の真空管アンプではなく、Fractal Audio Systemsのデジタルアンプシミュレーター「Axe-Fx II XL+」が中心です。
2019年のResurrection Fest EGのライブ映像(22:52付近)でも明確に確認でき、現場で安定した音を供給していることが分かります。これはメタルコア系バンドの中でも特に先進的な選択で、ライブ会場ごとに異なる環境下でも一貫したトーンを再現できるメリットがあります。
また、コントローラーとして同社の「MFC-101 MIDI Foot Controller」を使用しており、ライブ中にプリセットの切り替えをスムーズに行っています。
従来のアンプ+ペダルの組み合わせに比べると、よりコンパクトかつ効率的で、ツアーの多いバンドにとっては大きな強みとなっています。
一方で、過去にはMarshallやEVH系アンプを使用していた可能性も指摘されており、特にスタジオや一部のセッションではチューブアンプ特有の温かみを持つサウンドを試していたとされます。ただし、Crystal Lakeのメインステージにおいては、Axe-Fxによるシミュレーションが圧倒的に多用されていると考えられます。
その理由として、メタルコアに求められる「ローエンドのタイトさ」と「ハイゲインのノイズレスな制御性」を満たす点が挙げられます。従来の真空管アンプではゲインを上げるとノイズも増えますが、Axe-Fxではダイナミクスを保ちながらクリアな音像を維持できるため、特に7弦やドロップチューニングとの相性が良いのです。
こうした背景から、現在のHoriのアンプシステムは「Fractal Audio Axe-Fx II XL+」を中心に構成されており、ライブ・レコーディングの両方で統一されたトーンを実現している、と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fractal Audio Axe-Fx II XL+ | Fractal Audio | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | Resurrection Fest 2019で使用確認。ライブのメインシステム。 |
| Fractal Audio Systems MFC-101 MIDI Foot Controller | Fractal Audio | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | Axe-Fxのコントローラーとしてライブで使用。 |
| Marshall JCMシリーズ(推定) | Marshall | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | スタジオで一部使用の可能性あり。未確定。 |
| EVH 5150III(推定) | EVH | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | メタル系定番アンプ。過去使用の可能性あり。未確定。 |
使用ギターの種類と特徴【Crystal Lake・Shinya Hori】

Shinya Horiのギター選びは、モダン・メタルコアに必要な「チューニングの安定性」と「ハイゲインでも抜ける音」を重視しています。
代表的なモデルが、ESPのE-II TE-7 SW(Evertuneブリッジ搭載)です。この7弦仕様のモデルは「True North」のMV冒頭(0:10付近)で確認でき、ドロップチューニングの低音リフにおいても音程がブレないことが特徴です。特にメタルコアやデスコアのように激しいリフが多いジャンルでは、Evertuneによる安定性が絶大な信頼を生んでいます。
さらに、FenderのJim Root Telecaster(ホワイト)も使用していることが「Rollin」のMVで確認されています。これはSlipknotのギタリストJim Rootのシグネチャーモデルで、EMGピックアップを搭載したモダン・メタル仕様。Horiがこのモデルを選んでいる点からも、彼がいかにアグレッシブかつタイトなサウンドを求めているかが分かります。
この2本のギターの使い分けは、ライブとレコーディングの両面で重要です。E-II TE-7は主に7弦のローエンドリフやブレイクダウンで使用され、一方でJim Root Telecasterは6弦ベースの楽曲やクリーントーンが求められる場面で活躍していると考えられます。
また、ライブでの映像資料やSNS投稿では、ESP系のモデルをメインにしていることが多いため、Horiの「本番での信頼機材」として位置づけられているのはESP E-II TE-7だと言えるでしょう。
加えて、一部のファンサイトやSNS投稿では、過去に他のESPカスタムモデルやJackson系のギターを使用していたという情報もあります。ただし、公式な確認が取れているのは前述の2本が中心であり、現行のメインセットアップはESPとFenderのシグネチャーモデルが軸になっていると想定されます。
結果として、Horiのギター選びは「激しいチューニングとラウドな音圧を支えるための安定性」と「モダンで抜けるトーン」を両立しており、彼のサウンドの核を作っている、と言えるでしょう。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | ギターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP E-II TE-7 SW(Evertune搭載) | ESP | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | 7弦ギター | 「True North」MVで使用確認。Evertuneでチューニング安定性抜群。 |
| Fender Jim Root Telecaster(White) | Fender | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | 6弦ギター | 「Rollin」MVで使用確認。EMG搭載のモダン仕様。 |
| ESP カスタムモデル(推定) | ESP | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | エレキギター | SNSや一部ファン投稿で確認されるが、公式には未確定。 |
使用エフェクターとボード構成【Crystal Lake・Shinya Hori】
Shinya Horiのエフェクターボードは、従来のペダルを並べた形ではなく、デジタルマルチエフェクターを中心としたシンプルかつ効率的な構成になっています。
その中核を担うのがFractal Audio Systemsの「Axe-Fx II XL+」であり、これ1台でアンプシミュレーションから空間系、モジュレーション系までほぼすべてをまかなっています。
Resurrection Fest 2019の映像(21:58付近)では、「MFC-101 MIDI Foot Controller」を用いてプリセットを切り替えている姿が確認されており、ライブではリアルタイムでのエフェクト操作よりも、シーンごとに切り替えられたプリセットを呼び出す方式を採用していると考えられます。
これにより、曲ごとに最適化された音色を即座に再現でき、さらにノイズやトラブルのリスクを最小限に抑えています。
Axe-Fx内蔵の主なエフェクトとしては、ハイゲイン用のプリアンプ/アンプシミュレーター、空間系のディレイやリバーブ、さらにブースター系のセッティングが多用されていると推測されます。
特にメタルコアのライブでは、リードパートに厚みを加えるためのディレイや、クリーンパートでのリバーブは必須であり、Horiのサウンドにも大きな役割を果たしているでしょう。
一部の楽曲では、ブレイクダウン直前のタイトなノイズカットやゲート処理が必要とされるため、Axe-Fx内の「ノイズリダクション」や「コンプレッサー」機能を併用していると考えられます。これにより、超低音域でも輪郭のはっきりしたサウンドをキープすることが可能になっています。
従来型の歪みペダルや空間系ペダルを個別に並べるよりも、Axe-Fxの統合システムを選択しているのは、Crystal Lakeのようにツアーを頻繁に行うバンドにとって機材トラブルを避け、セッティングを迅速に行える点で非常に理にかなっています。
この構成は「効率性」と「再現性」を両立するものであり、現代的なプロフェッショナルの選択肢として参考になるでしょう。
結果的に、Shinya Horiのエフェクトシステムは、Fractal Audioを軸とした「デジタル完結型」の構成であり、ノイズレスかつ多彩な音色を生み出す基盤となっている、と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | エフェクターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fractal Audio Axe-Fx II XL+ | Fractal Audio | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | プリアンプ/アンプシミュレーター, マルチエフェクター | ライブ・レコーディングでメイン使用。歪み・空間系を網羅。 |
| Fractal Audio Systems MFC-101 MIDI Foot Controller | Fractal Audio | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | スイッチングシステム | プリセット切替用。Resurrection Fest 2019で使用確認。 |
| Axe-Fx内蔵ノイズゲート | Fractal Audio | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | ノイズリダクション | 低音域でもタイトな輪郭を保つために使用されると推測。 |
| Axe-Fx内蔵リバーブ/ディレイ | Fractal Audio | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | ディレイ, リバーブ | リードやクリーンで多用。楽曲の空間演出に必須。 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【Crystal Lake・Shinya Hori】

Shinya Horiの音作りの最大の特徴は、モダンメタルコアに不可欠な「タイトで重厚なローエンド」と「突き抜けるハイミッドの存在感」の両立です。
そのため、アンプシミュレーションやEQ処理の段階で、徹底した周波数コントロールが行われていると考えられます。特に7弦ギターを活かした低音リフでは、100Hz前後のローを引き締め、ブーミーにならないようカット気味に調整しつつ、70Hz付近の超低域はベースに譲る形でミックスされています。
一方で、リフの芯を形成する250Hz〜400Hz帯域はややブーストし、さらに2kHz〜4kHzのハイミッドを強調することで、激しいバッキングの中でも輪郭が明瞭に聞こえるよう工夫されています。特に「Apollo」や「True North」のギターリフでは、このハイミッドがカットスルーするようなアグレッシブな存在感を持っています。
クリーントーンでは、ローを抑え、1kHz〜2kHzの帯域を中心に透明感を出す設定が多用されていると考えられます。Axe-Fxのプリセットには「Shimmer系リバーブ」や「ステレオディレイ」が多用され、空間的な広がりを演出しています。例えば「Aeon」や「Six Feet Under」では、透明感と残響を兼ね備えたサウンドが確認でき、これがCrystal Lakeの楽曲におけるドラマティックなダイナミクスを生んでいます。
さらに、歪みのセッティングにおいては、ゲインを過剰に上げず、むしろミドルゲイン気味に抑えた上でブースター(Axe-Fx内蔵のOD/TS系モデリング)をかけることで、タイトでノイズレスなサウンドを実現しています。これにより、ピッキングのアタック感やリズムの切れ味を損なうことなく、メタルコア特有の高速リフにも対応できるのです。
ライブでの音作りに関しても特徴的で、PAとの協力で「ギター帯域とベース帯域のすみ分け」が徹底されています。ベースが担う超低域(50Hz〜70Hz)を避け、ギターは80Hz〜120Hz付近を締めたローエンドを中心に構築し、全体として分離感のあるサウンドに仕上げられています。これにより、大規模フェスでも音の輪郭が潰れず、迫力と明瞭さを両立しているのです。
EQ以外にも、コンプレッサーを軽くかけることで演奏の粒立ちを均一化し、さらにノイズゲートを厳密に設定してブレイクダウンの切れ味を強調しています。特にドロップチューニングの7弦では、ゲートが緩すぎると音が濁り、硬すぎるとニュアンスが消えるため、極めてシビアな調整が行われていると考えられます。
ミックスにおいては、左右にハードパンされたギター2本のダブルトラッキングが基本。そこにリードギターをセンター寄りに配置し、必要に応じて空間系エフェクトで立体感を持たせています。これにより、轟音リフでも中域の飽和を避けつつ、バンド全体の音圧が増幅されています。
総じて、Shinya Horiの音作りは「EQとゲート処理による徹底的な整理」「中域とハイミッドの存在感強調」「空間系エフェクトによるクリーンパートの演出」が柱となっています。
これらの要素が組み合わさることで、メタルコアの中でも唯一無二のバランスを持ったサウンドが生まれている、と想定されます。
比較的安価に音を近づける機材【Crystal Lake・Shinya Hori】
Shinya HoriのサウンドはFractal Audio Axe-Fx II XL+のようなハイエンド機材に支えられていますが、これらは初心者や中級者にとって高価で導入ハードルが高いのも事実です。
そこで、比較的安価に彼のサウンドを再現できる機材を選ぶ際には「ハイゲインでもタイトさを保つこと」「空間系エフェクトで広がりを出すこと」「チューニングの安定感」をポイントにするのが良いでしょう。
まず、アンプシミュレーター/マルチエフェクターとしておすすめなのがです。これは10万円未満で購入可能ながら、アンプシミュレーションや空間系エフェクトを高品質で再現でき、ライブでもレコーディングでも扱いやすい設計になっています。プリセットの切り替えが容易な点も、Shinya Horiが実際に行っているスタイルに近づけやすいポイントです。
さらにエントリーモデルとしてはやも選択肢に入ります。これらは5万円以下で手に入る上、ハイゲインサウンドや空間系のセッティングを直感的に扱うことができ、メタルコア系バンドのコピーや練習用としても十分に機能します。特にLine 6はモダンメタル系のシーンで実績があり、再現度の高さに定評があります。
ペダル単体で構成する場合は、歪みにはがコストパフォーマンスの高い選択肢となります。ゲインを絞ってミッドをしっかり出す設定にすると、意外にもタイトなメタルコアサウンドが得られます。これに加え、クリーンパートでの広がりを再現するためにはやといった空間系ペダルを組み合わせるのが有効です。
また、チューニングの安定性に関しては、実際にEvertuneブリッジを導入するのが理想ですが、費用がかかるため、初心者であればやなどを併用し、常に安定したピッチを保つ工夫をすると良いでしょう。
結果として、初心者や中級者がShinya Hori風のサウンドを安価に再現するには、「BOSS GT-1000COREやLine 6 POD Goといったマルチエフェクターを導入し、歪みと空間系を活用する」ことが最も効率的です。これにより、彼のような重厚かつ切れ味のあるサウンドに近づけることができます。
| 種類 | 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチエフェクター | BOSS GT-1000CORE | BOSS | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | Axe-Fxに近い多機能を10万円以下で実現。ライブ向け。 |
| マルチエフェクター | Line 6 POD Go | Line 6 | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | 5万円前後で導入可能。ハイゲイン再現度が高く初心者に最適。 |
| ディストーション | BOSS MT-2W Metal Zone Waza Craft | BOSS | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | タイトにセッティングすればモダンメタル系に対応可能。 |
| ディレイ | BOSS DD-8 Digital Delay | BOSS | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | リードパートやクリーンに空間的な広がりを与える。 |
| リバーブ | MXR M300 Reverb | MXR | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | シマー系含む多彩なリバーブでクリーンを再現。 |
| チューナー | BOSS TU-3 Chromatic Tuner | BOSS | Amazonで探す | Crystal Lake | Shinya Hori | ライブ必携。常に安定したピッチを維持。 |
総括まとめ【Crystal Lake・Shinya Hori】

Shinya Horiの音作りは、メタルコアやラウドロックのギタリストにとって非常に参考になるものです。
その根幹を支えるのは「安定性」と「切れ味」であり、Evertune搭載のESP E-II TE-7をメインとすることで、過酷なライブ環境でも音程を維持しつつ、激しいリフを正確に届けています。さらに、Fender Jim Root Telecasterのようなシグネチャーモデルをサブに加えることで、異なるキャラクターを持つサウンドを使い分けています。
アンプやエフェクター面では、Fractal Audio Axe-Fx II XL+を中心としたデジタル完結型のシステムを採用。ライブでもレコーディングでも一貫したトーンを提供できることから、Crystal Lakeの国際的な活動に不可欠な存在となっています。特に「MFC-101 MIDI Foot Controller」との組み合わせは、曲ごとのサウンド切り替えをスムーズに行うため、プロフェッショナルとしての効率性を極限まで高めています。
音作りの本質は、ローエンドを締めつつ中域とハイミッドを強調したEQ処理にあります。これにより、低音が飽和せず、どんな大規模フェス環境でもギターが前に出る存在感を発揮します。また、Axe-Fx内蔵のディレイやリバーブを駆使することで、重厚なリフと透明感のあるクリーントーンを自在に切り替えられる点も大きな特徴です。
もしこれからShinya Horiのサウンドを目指すなら、「機材そのものをコピーする」だけでなく、彼の音作り哲学に注目するのが大切です。つまり、
・チューニングの安定性を徹底すること
・ローエンドとハイミッドの整理によって音圧と明瞭さを両立すること
・ライブ環境に合わせて効率的にセッティングできるシステムを構築すること
この3つがポイントとなります。
また、初心者や中級者にとっては、BOSS GT-1000COREやLine 6 POD Goのような比較的手の届きやすいマルチエフェクターを用いることで、Horiのサウンドにかなり近づけることができます。ペダル単体で揃える場合も、歪み+空間系を中心に組み合わせれば、十分に迫力あるトーンを実現できるでしょう。
総じて、Shinya Horiの音作りは「モダン・メタルギターの完成形」とも言える洗練度を持っています。
その根底には、ジャンルにおける技術的要請と、世界で戦うための合理性があり、それを機材選びやセッティングに落とし込んでいるのです。
読者の皆さんも、この哲学を意識して機材や音作りに取り組めば、Crystal Lakeのような強靭で美しいサウンドに一歩近づくことができるでしょう。
“`
下記恐らく使用(所持)している機材のまとめです。参考までに!
ギター
ESP E-II TE-7 SW(Evertuneブリッジ搭載)
「True North」MV(0:10)で使用確認。Evertune搭載の7弦仕様。
Fender Jim Root Telecaster(ホワイト)
「Rollin」MVで使用確認。Jim Root Signatureモデル。
アンプ/プロセッサー
Fractal Audio Axe-Fx II XL+
Resurrection Fest EG 2019(22:52)で使用確認。
コントローラー/ペダル
Fractal Audio Systems MFC-101 MIDI Foot Controller
Resurrection Fest EG 2019(21:58)でAxe-Fx用コントローラーとして使用。