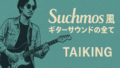始めに(特徴紹介)
結束バンドのギタリスト・生本直毅は、原作『ぼっち・ざ・ろっく!』の世界観を体現するかのように、鮮やかで存在感のあるギターサウンドを響かせています。
彼のプレイは、歪みを基盤にしつつもクリーンの透明感を巧みに使い分け、楽曲ごとに色彩豊かな表情を持たせている点が特徴です。
代表曲「星座になれたら」では、ワウを駆使したリフが印象的で、疾走感と情緒が同居する独特のサウンドを作り出しています。
一方で「青い春と西の空」ではストラトキャスターを使用し、レスポールの分厚いトーンから一転して、煌びやかなクリーントーンを奏でています。
ライブ現場では、Bognerアンプを中心に構築された音圧のあるトーンが、結束バンドのサウンド全体を支えているのが確認できます。
また、彼のボードにはLine 6 HX Stompをはじめとした最新のデジタルマルチも組み込まれており、アナログとデジタルの良さをミックスしたモダンなシステムを実現しています。
オーバードライブにはVEMURAM Jan RayやWampler Tumnus、ブーストにはXotic EP Boosterを使用し、音の厚みやダイナミクスの表現力を高めています。
生本直毅の音作りが注目されるのは、単に機材の豪華さだけではなく、楽曲の展開に合わせて適材適所で機材を使い分けるセンスにあります。
観客に「この音こそ結束バンド」と感じさせる説得力のあるプレイスタイルこそ、彼の最大の魅力といえるでしょう。
使用アンプ一覧と特徴【結束バンド・生本直毅】
生本直毅の音作りにおいて、もっとも重要な役割を果たしているのがアンプです。
ライブやスタジオで確認されているのは、ドイツ発祥でハイゲインアンプの代名詞ともいえる「Bogner(ボグナー)」のシステム。
ギターマガジンWEBでも「2ch/3chを組み合わせて使用」と明記されており、Bogner特有の密度感と立体的なサウンドが、結束バンドの楽曲に厚みを与えています。
Bognerアンプはクリーンチャンネルの透明感と、ハイゲインチャンネルの図太さを兼ね備えた設計。
特に代表的なモデルである「Ecstasy」シリーズや「Uberschall」シリーズは、国内外のプロも愛用しています。
生本直毅が実際にどのモデルを使用しているかは明確に記されていませんが、ライブ現場の写真や記事内容から、3ch仕様のヘッドアンプとBognerキャビネットを組み合わせていることが確認できます。
また、アンプのセッティングは4ケーブルメソッドを駆使したLine 6 HX Stompとの連携によって柔軟に変化。
これにより「星座になれたら」のワウを生かしたリフではミドルを強調した音作りを、バラードではクリーンにリバーブを重ねた表現を容易に切り替えています。
Bognerの持つ奥行きのあるサウンドと、デジタルマルチによる多彩なエフェクト処理の組み合わせが、彼のギターを楽曲に最適化しているのです。
結束バンドのライブ音源を聴くと、ギターがバンドサウンドに埋もれることなく、かつ耳に刺さらないバランスを保っているのが特徴です。
これはBognerの中域の表現力と、強力なキャビネットの鳴りがあってこそ可能なアプローチであるといえます。
現状ではモデル名まで確定されていませんが、Bognerの代表的なヘッドと4×12キャビネットの組み合わせである「Ecstasy Head+412キャビ」が最有力候補、と想定されます。
使用ギターの種類と特徴【結束バンド・生本直毅】

生本直毅のギターサウンドを形作る最大の要素は、メインとして使用しているレスポールにあります。
彼が愛用しているのは「Gibson Historic Collection 1959 Les Paul Standard Reissue HRM(レモンドロップ)」で、単なるリイシューモデルにとどまらず、徹底したモディファイが施されています。
ピックアップはLindy Fralin製に交換、さらに50s Bumblebeeコンデンサーやヴィンテージ配線材、ジャックのアップグレードまで行われており、往年のレスポールサウンドを再現しながらも、現代的な安定性を実現しています。
特筆すべきは、結束バンドの「恒星ライブ」において、このレスポールがほぼ全曲で使用されている点です。
厚みのあるミッドレンジとサステインの豊かさは、生本直毅のプレイスタイルに不可欠であり、リード・リフ・アルペジオいずれにおいても存在感を発揮します。
彼の音が「芯が太く、それでいて抜けが良い」と形容されるのは、このレスポールとモディファイの組み合わせによるものです。
一方で、楽曲「青い春と西の空」ではFender Stratocasterを使用。
この曲のみストラトに持ち替えていることがギターマガジンWEBでも明言されており、レスポールの分厚い音から一転、煌びやかでレンジの広いトーンを選択しています。
この使い分けによって、セットリスト全体に音色のコントラストを与え、リスナーを飽きさせない工夫がなされています。
なお、レスポールはライブでの核となるギターであり、ストラトはあくまで楽曲単位でのピンポイント起用。
こうした明確な使い分けからも、生本直毅が曲の雰囲気や構成を重視して機材を選んでいることが分かります。
現時点で公的に確認できるギターは上記2本ですが、今後のライブやスタジオワークで新たなモデルが登場する可能性もあり、引き続き注目が集まります。
使用エフェクターとボード構成【結束バンド・生本直毅】
生本直毅の音作りを支えるのは、徹底的に整えられたエフェクターボードです。
アナログとデジタルを組み合わせ、ライブ現場で即座に多彩な音色を切り替えられるよう構築されています。
特に中心的な役割を果たしているのが「Line 6 HX Stomp」で、ピッチシフトやモジュレーション、ディレイなど幅広い処理を担当。4ケーブルメソッドでBognerアンプと接続され、アンプの特性を活かしつつ柔軟な音色コントロールを実現しています。
歪み系には複数のオーバードライブを使い分けています。
「Wampler Tumnus」はケンタウルス系ODとして知られ、レスポールの厚みあるサウンドに透明感と中域の張りを加えます。
「VEMURAM Jan Ray」はクリーンブースト寄りのオーバードライブで、楽曲によってはピッキングニュアンスを前に出すために使用。
さらに「Analog Man Ibanez TS9 Mod.」は、定番のチューブスクリーマーをベースにした改造品で、ミッドブーストを強調しつつも抜けの良さを獲得しています。
加えて「Xotic EP Booster」を組み合わせることで、ソロやリフの存在感を高めています。
空間系や特殊効果では、「Jim Dunlop GCB-95 Cry Baby Wah」が「星座になれたら」のリフで使用されており、バンドサウンドに独特の揺らぎを生み出しています。
また、Free The ToneのJB-82S(ジャンクションボックス)やARC-53M(プログラマブル・スイッチャー)が組み込まれ、煩雑になりがちな信号経路を整理。これにより、ライブ中も安定した音質と操作性を確保しています。
補助機材として、BOSS TU-3s(チューナー)、Kenton Turu-5(MIDIスルー)、Ex-pro PS-2(パワーサプライ)も使用。
これらは音作りに直接関わるわけではありませんが、システム全体の安定性と再現性に大きく貢献しています。
特にMIDIスルーとスイッチャーの組み合わせにより、ワンタッチで複雑な音色切り替えが可能になっている点は、生本直毅のライブパフォーマンスを大きく支えています。
このように、彼のボードは「アナログの温かみ」と「デジタルの汎用性」を高次元で融合させた実戦的な構成、と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | エフェクターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Dunlop GCB-95 Cry Baby Wah | Jim Dunlop | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | ワウペダル | 「星座になれたら」のリフで使用。 |
| Free The Tone JB-82S | Free The Tone | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | ジャンクションボックス | 信号を整理しノイズを低減。 |
| Free The Tone ARC-53M | Free The Tone | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | スイッチングシステム | プログラマブルスイッチャー。複雑な切替を一括管理。 |
| Line 6 HX Stomp | Line 6 | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | ギター用マルチエフェクター | ピッチ/モジュレーション/ディレイ等を担当。4CMでアンプ連携。 |
| Wampler Tumnus | Wampler | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | オーバードライブ | ケンタウルス系OD。レスポールに透明感と中域をプラス。 |
| VEMURAM Jan Ray | VEMURAM | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | オーバードライブ | クリーンブースト的に使用。ニュアンスを前に出す。 |
| Analog Man Ibanez TS9 Mod. | Analog Man | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | オーバードライブ | 定番TS9を改造。抜けの良いミッドブースト。 |
| Xotic EP Booster | Xotic | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | ブースター | ソロやリフに厚みを加える。 |
| BOSS TU-3s | BOSS | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | チューナー | ボード内蔵用コンパクトチューナー。 |
| Kenton Turu-5 | Kenton | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | MIDIスルー | エフェクト群をMIDI制御で統合。 |
| Ex-pro PS-2 | Ex-pro | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | パワーサプライ | 安定した電源供給。ノイズを抑制。 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【結束バンド・生本直毅】

生本直毅の音作りは、単に機材を並べただけでは再現できない緻密なセッティングに支えられています。
Bognerアンプのチャンネル切替とHX Stompを駆使した柔軟な音作り、さらにPAやミックス段階での調整が組み合わさることで、結束バンド特有の「迫力と透明感を併せ持つギターサウンド」が成立しているのです。
まず、基本のアンプEQ設定について考えられるのは、ミドルを強めに設定した中域主体のセッティングです。
レスポールを用いたメインサウンドでは、低域はタイトに締めつつ中域に厚みを持たせ、高域は刺さらない程度に抑えることで、バンド全体の中で抜けるトーンを獲得しています。
特にライブでは、ドラムやベースとの混ざり具合を考慮し、低域をカットしすぎずに「存在感」を保つ工夫がなされていると考えられます。
曲ごとにセッティングを変える点も特徴的です。
「星座になれたら」ではCry Baby Wahによるフィルタリングを生かすために、アンプのミドルをさらに強調し、ハイ寄りの音抜けを確保。
一方で「青い春と西の空」ではストラトキャスターを使用し、クリーンチャンネルにリバーブやモジュレーションを加え、透明感を前面に押し出しています。
つまり、使用するギターやエフェクターに合わせて、アンプのCH切替とEQバランスをダイナミックに調整しているのです。
さらに注目すべきはHX Stompを使った空間系処理です。
ディレイはステレオ感を強調するために短めのディレイタイムとフィードバックを抑えた設定が多く、リバーブはホールタイプを薄くかけることで、会場の残響と馴染ませています。
ピッチシフターは一部のリフやフレーズで使用され、ライブにおいても「原曲の厚み」を再現する役割を担っています。
ミックス段階でも彼の音作りのこだわりが反映されています。
ギターはバンドアンサンブルの中で左右にパンを振らず、センター寄りに配置されるケースが多く、その結果「主役のギター」としての存在感を確立。
EQ処理では中高域を2~3kHz付近で少し持ち上げ、プレゼンスを加える一方、不要な低域はハイパスフィルターでカットしてバンド全体の低域と分離を図っています。
また、ソロパートではブースターやJan Rayを活用し、音量とゲインを同時に持ち上げることで、ギターが前に出てくるように調整されています。
エンジニア視点で見ても、ダイナミクスのコントロールが非常に上手く、コンプレッサーに頼りすぎずにピッキングニュアンスを自然に残している点が大きな特徴といえます。
総じて、生本直毅のセッティングは「機材本来の音を活かすEQ」「楽曲に応じたCH切替」「PAとの協調によるミックス」の三本柱で構築されていると言えるでしょう。
これらの工夫を踏まえることで、結束バンドらしい重厚でありながらクリアなギターサウンドを再現できる、と想定されます。
比較的安価に音を近づける機材【結束バンド・生本直毅】
生本直毅が実際に使用している機材は、GibsonのカスタムレスポールやBognerアンプ、VEMURAMやWamplerなどの高価なペダル群で構成されており、初心者がそのまま揃えるのは現実的に難しい部分があります。
しかし幸いなことに、彼の音作りの特徴である「分厚い中域」「抜けの良さ」「空間系の立体感」を再現できる、比較的安価な代替機材が市販されています。ここでは1万円〜5万円程度で導入できるアイテムを中心に紹介します。
まずギターに関しては、レスポール系であればEpiphone Les Paul Standardが最有力候補です。
本家Gibsonと比べれば価格は大幅に抑えられますが、厚みのあるサウンドはしっかりと得られ、アンプやエフェクターとの組み合わせ次第で「結束バンド的な芯のあるトーン」を十分に体感できます。
ストラトに関しても、Fender Player Stratocaster(メキシコ製)やSquier Classic Vibeシリーズなどが選択肢として有効です。
アンプでは、Bognerと同様に中域の張りと立体感が得られるモデルとして、BOSS Katanaシリーズが圧倒的にコストパフォーマンスに優れています。
特にKatana-50 MkIIは自宅練習から小規模ライブまで幅広く対応し、クリーンからハイゲインまでカバー可能。HX Stompのような多機能性はなくとも、アンプ単体で十分に生本直毅のトーンに近い感覚を得られます。
エフェクターに関しては、ケンタウルス系の代替としてはJHS Pedalsの「3 Series Overdrive」や、Electro-Harmonix Soul Foodが人気。
Jan Ray系を模したペダルでは、Xotic RC Boosterも手の届きやすい価格でありながらクリーンブースト的に使えるためおすすめです。
Cry Baby Wahはオリジナルモデルが比較的安価で入手できるため、そのまま導入可能です。
マルチエフェクターを導入する場合、Line 6 HX Stompはやや高額ですが、代わりにZoom G5nやBOSS GT-1000 Coreの廉価機であるGT-1などが良い選択肢となります。
これらは空間系の処理が得意で、ディレイやリバーブをうまく設定すれば「星座になれたら」の立体感あるトーンに近づけます。
電源やスイッチャーは必須ではありませんが、安定性を求める場合はOne Control製のパワーサプライや、BOSS ES-5のような簡易スイッチャーを導入すると、よりライブ的な使い勝手が再現できます。
総じて、Epiphone+Katanaアンプ+Soul Food+Cry Babyの組み合わせは、最小限の予算で「結束バンドらしい音」を掴む第一歩になるでしょう。
| 種類 | 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギター | Epiphone Les Paul Standard | Epiphone | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | 厚みのあるレスポール系サウンドを安価に再現可能。 |
| ギター | Squier Classic Vibe Stratocaster | Squier | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | 「青い春と西の空」風クリーンに適した廉価ストラト。 |
| アンプ | BOSS Katana-50 MkII | BOSS | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | Bognerに近い中域特性を持つ万能練習用アンプ。 |
| オーバードライブ | Electro-Harmonix Soul Food | Electro-Harmonix | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | ケンタウルス系ODの廉価版。Tumnusの代替候補。 |
| ブースター | Xotic RC Booster | Xotic | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | Jan Rayの代替として透明感あるブーストを実現。 |
| ワウペダル | Jim Dunlop Cry Baby Standard | Jim Dunlop | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | 「星座になれたら」のリフ再現に必須。 |
| マルチエフェクター | Zoom G5n | Zoom | Amazonで探す | 結束バンド | 生本直毅 | 空間系処理に強く、HX Stompの代替として有効。 |
総括まとめ【結束バンド・生本直毅】

生本直毅の音作りを振り返ると、その本質は「バンドサウンドの中で存在感を放ちながらも楽曲に寄り添うバランス感覚」にあるといえます。
Gibson Historic Collection 1959 Les Paulをモディファイしてメインに据えることで、骨太な中域と豊かなサステインを確保。さらに曲ごとにFender Stratocasterを使い分けることで、音色のレンジを広げています。
このギターの選択と使い分けこそが、結束バンドの音世界を支える重要な軸です。
アンプ面では、Bogner特有の高解像度かつ立体的なトーンを軸にし、クリーンとハイゲインを自在に切り替えながら、Line 6 HX Stompを介して空間系エフェクトやピッチ処理を重ねています。
その結果、重厚なリフから透明感のあるアルペジオまで、楽曲に応じた多彩なサウンドがライブで瞬時に展開されます。
この柔軟さは「アナログの力強さ」と「デジタルの利便性」を融合させた現代的なアプローチの好例といえるでしょう。
エフェクターボード構成もまた特徴的です。
複数のオーバードライブを使い分けて音の表情を作り分け、Cry Baby Wahで楽曲にアクセントを加える。
さらにスイッチャーやジャンクションを活用することで、ライブ中の安定性と即応性を両立させています。
これらは単なる機材選びに留まらず、「いかに楽曲の雰囲気を壊さず、最大限に活かすか」という哲学の表れでもあります。
また、PAやミックス段階での工夫によって、ギターはバンド全体の中で常にクリアに聴こえるよう調整されています。
EQで中域を押し出しつつ、高域は過度に尖らせず、低域はタイトにまとめる。
この緻密なバランス感覚が、結束バンドのライブで聴ける「重厚で抜けの良い音」の秘密です。
総じて、生本直毅の音作りは「ギタリスト個人の自己主張」ではなく「バンド全体を支える核」としての役割を果たしている点が最大の特徴です。
それは、レスポールの存在感あるサウンドを基盤にしつつも、必要に応じてストラトの透明感やワウの揺らぎを取り入れる柔軟さに表れています。
これを再現するためには、高価な機材を揃える必要は必ずしもなく、音作りの根底にある「バンドを生かす意識」を持つことが何より重要だといえるでしょう。
結束バンドの楽曲をコピーする人にとって、生本直毅の音作りは一つの到達点であり、学ぶべきポイントの宝庫です。
彼の音の本質を理解し、自分の環境に合わせた工夫を重ねることで、誰もがあの「ライブで心を震わせるギターサウンド」に近づくことができるはずです。
“`
下記恐らく使用(所持)している機材のまとめです。参考までに!
🎸ギター
Gibson Historic Collection 1959 Les Paul Standard Reissue HRM(レモンドロップ。PU=Lindy Fralinに交換、50s Bumblebeeコンデンサー/ヴィンテージ配線材&ジャック。恒星ライブでは「青い春と西の空」以外ほぼ全曲で使用)。
ギター・マガジンWEB|Guitar magazine
Fender Stratocaster(「青い春と西の空」でのみ持ち替え)。
ギター・マガジンWEB|Guitar magazine
🔊アンプ
Bogner アンプ(記事記載は「ボグナーの2ch/3chを組み合わせて使用」とのみ。モデル名は未掲載)+Bognerキャビネット(現場写真でも確認可)。
ギター・マガジンWEB|Guitar magazine
🎛️エフェクター
Jim Dunlop GCB-95 Cry Baby Wah(「星座になれたら」リフで使用)。
ギター・マガジンWEB|Guitar magazine
Free The Tone JB-82S(ジャンクション)/ARC-53M(プログラマブル・スイッチャー)。
ギター・マガジンWEB|Guitar magazine
Line 6 HX Stomp(ピッチ/モジュレーション/ディレイ等を担当。4ケーブル・メソッドでアンプと連携)。
ギター・マガジンWEB|Guitar magazine
Wampler Tumnus(OD)/VEMURAM Jan Ray(OD)/Analog Man Ibanez TS9 Mod.(OD)/Xotic EP Booster(ブースト)。
ギター・マガジンWEB|Guitar magazine
BOSS TU-3s(チューナー)/Kenton Turu-5(MIDIスルー)/Ex-pro PS-2(電源)。