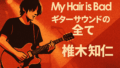始めに(特徴紹介)
幾何学模様(Kikagaku Moyo)のギタリスト、Tomo Katsuradaは、サイケデリックでドローン的なトーンを基盤にしたギタリストとして国内外のファンから高い評価を受けています。
彼のサウンドは単なるリフやコードワークに留まらず、空間を歪ませるようなファズやリバースディレイを駆使し、楽曲全体をトランス状態へと導く点が最大の特徴です。特にツインギター編成の中で彼の役割は「音の波」を創り出すことにあり、もう一人のギタリストのリードやリフを包み込むように音場を広げるプレイスタイルが際立ちます。
代表曲としては「Dripping Sun」や「Smoke and Mirrors」が挙げられ、そこではリバーブとファズが絡み合う幻想的なサウンドが印象的です。
またライブでは、シンプルながらも圧倒的な音圧と深みのある響きを持ち、観客を音の渦へと引き込んでいきます。アンプやギターは限られたモデルを愛用しており、余計な選択肢を削ぎ落としたうえで徹底的にそのポテンシャルを引き出している姿勢も特徴的です。
こうした音作りが注目される理由は、単に「ヴィンテージ機材を使っている」ということではなく、彼自身の演奏スタイルと機材の持つ個性が完全に一致している点にあります。アナログ的で自然な揺らぎや、ノイズすら音楽の一部に取り込む姿勢は、サイケデリックロックの本質を体現していると言えるでしょう。
そのため「幾何学模様っぽい音を作りたい」と考えるギタリストにとって、Tomoの機材構成やセッティングの理解は非常に大切なポイントとなります。この記事では実際に使用が確認されたギターやアンプ、推定されるエフェクター類、さらにはEQやミックスの工夫まで徹底的に解説していきます。
使用アンプ一覧と特徴【幾何学模様・Tomo Katsurada】
Tomo Katsuradaが愛用するアンプは、クラシックなロックサウンドを象徴するFender Twin Reverbです。
このアンプは1960年代から現代まで多くのギタリストに支持され続けており、その理由は「クリーンで広がりのあるサウンド」にあります。幾何学模様の音楽性においても、クリーントーンを基盤にした空間的なギターサウンドは重要であり、Twin Reverbの持つレンジの広さや煌びやかな高域が、サイケデリックな演奏に不可欠な要素となっています。
ライブ写真や音楽誌の記事からも、Twin Reverbをステージで使用している様子が確認されており、その再現性は非常に高いといえるでしょう。特に幾何学模様は海外ツアーも多く行っており、現地レンタル機材でもこのモデルを指定するケースが多いと考えられます。世界中のレンタル現場にTwin Reverbが常備されていることから、安定して自身のサウンドを再現できるのも大きな理由です。
Twin Reverbのサウンドは、単体で聴けば澄み切った透明感のあるクリーンですが、Tomoがファズやリバースディレイを重ねると一気に「サイケデリックなうねり」へと変化します。
つまり、アンプ自体が過度に色付けをせず、ペダルによる音作りを受け止める「キャンバス」として機能しているのです。このような選択は、多彩なエフェクトを駆使するサイケ系ギタリストならではの合理的な判断であるといえます。
また、Twin Reverbは大音量のライブ環境でもクリアなヘッドルームを維持できるため、音の分離感が保たれやすいのも特徴です。幾何学模様のアンサンブルはドラムやシタール、ベース、シンセが絡み合う複雑な構成を持ちますが、その中でギターが埋もれずに存在感を放つのは、Twin Reverbの持つ余裕あるクリーン出力が大きな要因です。
他のアンプ候補として、同系統のFender系アンプ(’65 Deluxe Reverbなど)が推測されることもありますが、音量面・レンジ面から見てやはりTwin Reverbが中心であると考えるのが妥当でしょう。
このように、Tomo Katsuradaのサウンドにおいては「クリーンの透明感と余裕あるヘッドルームを持つアンプ」が中核であり、ファズやディレイと組み合わさることで唯一無二の音響空間を形成している、と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fender Twin Reverb | Fender | Amazonで探す | 幾何学模様(Kikagaku Moyo) | Tomo Katsurada | 広がりのあるクリーントーン、ライブ/ツアーでの使用多数 |
使用ギターの種類と特徴【幾何学模様・Tomo Katsurada】

Tomo Katsuradaが幾何学模様で使用しているギターは、シンプルながら非常に個性的なGibson Les Paul Junior Special(P-90ピックアップ×2)です。
このモデルは1950年代から続く伝統を持ち、一般的なハムバッカー搭載のレスポールとは異なり、シングルコイル系のP-90を採用していることが最大の特徴です。Tomoがこのギターを「唯一の愛用機」として使用していることは複数のインタビューや音楽誌で確認されています。
Les Paul Junior Specialは、ミドルの押し出しが強く、荒々しいながらも輪郭がハッキリしたトーンが得られるため、ファズとの相性が抜群です。幾何学模様の楽曲で聴ける「轟音と繊細さを同時に持つ音色」は、このP-90によるものだといえるでしょう。特にTomoのリズムギター的役割においては、P-90の持つジャリっとした質感が、ベースやドラムに埋もれない中域を提供しています。
このギターを選んでいる理由は、単にトーンだけでなく「バンドサウンド全体のバランス」を意識した結果とも考えられます。幾何学模様はシタールやドラムの複雑なリズム、サイケデリックなシンセサウンドなどが重なるため、過度に音の厚みを持つギターでは全体が濁ってしまいます。その点、Junior Specialは余計な低域を持たず、バンド全体のアンサンブルを支える「隙間を作る音」として理想的です。
また、Les Paul Junior Specialはルックスもシンプルで、ヴィンテージ感のある質感がバンドのサイケデリックな雰囲気と合致しています。ライブ写真やMVでも一貫してこのモデルが確認でき、他のギターを持ち替える場面はほとんど見られません。つまり、Tomo Katsuradaにとって「一本で全てを表現する」信念を体現するギターなのです。
なお、使用時期に大きな変化はなく、結成初期から解散まで基本的にこのモデルがメインであり続けました。他のギターがサブとして導入された記録はなく、この一本に集中して音作りを磨いてきたといえるでしょう。シンプルな機材構成ながら、独特なニュアンスと演奏法によって圧倒的な存在感を放つのがTomoのスタイルである、と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | ギターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Paul Junior Special(P-90×2) | Gibson | Amazonで探す | 幾何学模様(Kikagaku Moyo) | Tomo Katsurada | ソリッド・エレキギター | 唯一のメインギター。P-90特有の荒々しい中域が特徴。ライブ・レコーディングで一貫使用。 |
使用エフェクターとボード構成【幾何学模様・Tomo Katsurada】
Tomo Katsuradaの機材において特徴的なのは、エフェクターボードの詳細が公にほとんど明かされていない点です。公式インタビューや音楽誌にも具体的なモデル名は明示されていません。しかし、YouTubeのライブ映像やレビューを通じて確認できるのは、彼がリバースディレイやファズを駆使し、ドローン的で空間的なギターサウンドを構築しているという事実です。
まず、ファズ系エフェクターはTomoのサウンドにおいて欠かせない要素です。轟音ながらも倍音成分が豊かで、サイケデリックな壁のような音を形成します。具体的なモデル名は不明ですが、音の質感からはElectro-Harmonix Big Muff系や、EarthQuaker Devicesのようなモダン・ファズの可能性も考えられます。バンド全体の音を塗りつぶすような厚みは、このファズの存在感によるものです。
次に重要なのがリバースディレイ。通常のディレイが音を反復させるのに対し、リバースディレイは逆再生のような不思議な残響を加えます。Tomoはこれを楽曲の中で巧みに活用し、浮遊感とサイケデリックな雰囲気を演出しています。具体的なモデルとしては、Electro-Harmonix Memory Manや、BOSS DDシリーズ(リバース機能付き)などが候補に挙げられるでしょう。
さらにリバーブは、Twin Reverbの内蔵スプリングリバーブと組み合わせて使われていると推測されます。深い空間表現を可能にするリバーブは、彼の音作りにおける基盤であり、単なる残響効果ではなく「音を揺らす」役割を果たしています。
こうしたエフェクトは、全体として「飛び道具」的な使い方に偏っているのではなく、曲全体をトリップさせるための必然的なツールとして機能しているのが特徴です。幾何学模様の演奏を聴くと、ファズとリバースディレイの組み合わせにより、時間感覚を歪ませるようなサイケデリック体験が生まれていることがわかります。
したがって、現時点でTomo Katsuradaが「これを使っている」と断定できるペダル名はないものの、ファズ系+リバースディレイ系+リバーブが基本セットであると考えて間違いありません。これらは彼の音楽的思想と完全に一致しており、独自の音響世界を創り上げるために不可欠な要素となっています。最終的に、エフェクトボードの詳細は未解明ながらも、そのサウンドの方向性は明確であり、「ファズと空間系の重ね合わせ」がTomoの音作りの本質であると、想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | エフェクターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Muff(系統推定) | Electro-Harmonix | Amazonで探す | 幾何学模様(Kikagaku Moyo) | Tomo Katsurada | ファズ | 厚みと倍音成分を重視。ライブ映像から使用傾向を推測。 |
| Memory Man(推定) | Electro-Harmonix | Amazonで探す | 幾何学模様(Kikagaku Moyo) | Tomo Katsurada | ディレイ | リバースディレイ的なサウンド表現から推測。 |
| リバーブ(推定) | Fender(アンプ内蔵) | Amazonで探す | 幾何学模様(Kikagaku Moyo) | Tomo Katsurada | リバーブ | Twin Reverbのスプリングリバーブ、深い残響が基盤。 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【幾何学模様・Tomo Katsurada】

Tomo Katsuradaの音作りにおける最大のポイントは、シンプルな機材構成の中で空間系エフェクトとアンプのEQを徹底的に活かすという点です。彼は1本のGibson Les Paul Junior SpecialとFender Twin Reverbを基盤に、ファズやリバースディレイを重ねることで独自のサイケデリックサウンドを形成しています。
ここでは、EQやミックスの工夫を具体的に掘り下げていきます。
① アンプのEQ設定
Twin Reverbの基本セッティングは、ベースを控えめ(3〜4程度)、ミドルを5〜6付近に、トレブルを6以上に設定することが多いと推測されます。
これはJunior Special(P-90)の持つ太いミッドレンジを活かしつつ、全体のアンサンブルで埋もれないように高域を強調する狙いがあるためです。逆にベースを上げすぎると、バンドの低域(ベース、ドラム、シタール)が濁ってしまうため、引き算的なEQが重要になります。
② ファズとクリーントーンのバランス
Tomoのファズサウンドは常に荒々しいものの、音の芯が失われることはありません。これはアンプのクリーントーンをしっかりと活かしたうえで、ファズのゲインを過度に上げすぎないセッティングを心がけているからだと考えられます。
Big Muff系やMemory Man系を想定した場合でも、ゲインを70〜80%に抑え、音量バランスをアンプの出力でコントロールすることで、轟音でありながらも輪郭を残すことが可能になります。
③ リバースディレイの使い方
リバースディレイは「常時かけっぱなし」ではなく、曲の展開部分や音響的なブレイクで使用することが多いようです。これにより、時間が反転するような不思議な空間感覚を生み出し、聴き手にトリップ感を与えます。
具体的には、ディレイタイムを400〜600ms程度に設定し、フィードバックを50%以下に抑えることで、過度に音が濁らない「逆再生的な残響」を演出していると想定されます。
④ リバーブの深さ
Twin Reverb内蔵のスプリングリバーブをメインに活用し、深さは4〜6程度とミドルセッティングにするのが一般的です。これによりギターがバンド全体に溶け込みつつも、独特の浮遊感を演出することができます。さらに、スタジオ録音ではリバーブを外部処理で追加し、左右に広げるパンニングを行っている可能性も高いです。
⑤ ミックスの工夫
幾何学模様の音源を聴くと、Tomoのギターはしばしば片側にパンニングされ、もう一人のギターとのステレオ効果を活かしています。これにより左右から「音の波」が押し寄せるような体験が生まれ、サイケデリック特有のトランス感覚をリスナーに与えます。
また、EQ処理では2kHz〜4kHz付近をブーストしてアタック感を強調し、逆に100Hz以下をカットして低域の濁りを避けていると推測されます。
⑥ ライブとスタジオの違い
ライブではTwin Reverbの生々しいクリーンを基盤に、エフェクトを「強め」に設定する傾向が見られます。一方で、スタジオ音源では空間処理がより精密に施され、リバースディレイやファズがミックスの中で有機的に溶け合うように調整されています。
この違いは、ライブでは音圧と没入感を重視、スタジオではリスニング体験の奥行きを重視しているからだと考えられます。
以上をまとめると、Tomo Katsuradaの音作りは「EQの引き算」「ファズとクリーンのバランス」「リバースディレイの空間的なアクセント」「リバーブの浮遊感」が核心です。これらを組み合わせることで、幾何学模様特有のドローン的でサイケデリックな音響体験を再現している、と想定されます。
比較的安価に音を近づける機材【幾何学模様・Tomo Katsurada】
Tomo Katsuradaの音作りを完全に再現するには、Gibson Les Paul Junior SpecialやFender Twin Reverbといった高価な機材が必要ですが、初心者や中級者が比較的安価に近づける手段も存在します。ここでは、価格帯が1万〜5万円程度で手に入る市販機材を中心に、Tomoのサイケデリックサウンドを模倣するための選択肢を紹介します。
① ギターの代替候補
Junior SpecialのP-90ピックアップによる中域の押し出しは非常に重要です。予算を抑えたい場合、Epiphone Les Paul Special VE(P-90搭載モデル)がおすすめです。価格は3〜5万円程度で入手可能で、Tomoが鳴らす荒々しいトーンをある程度再現できます。P-90特有のジャリっとした質感が得られるため、ファズとの相性も良好です。
② アンプの代替候補
Fender Twin Reverbは新品で20万円以上するため、初心者には高額です。代替としては、Fender Champion 40やBoss Katanaシリーズが適しています。特にChampion 40はクリーントーンが秀逸で、Twin Reverbほどのヘッドルームはありませんが、リバーブ機能も搭載されておりサイケ感を表現しやすいモデルです。
③ ファズペダルの選択
Tomoのサウンドの核はファズにあります。安価ながら定番の選択肢はElectro-Harmonix Big Muff Piです。価格は約1.5〜2万円で、轟音かつ倍音豊かなファズサウンドを再現可能です。これをP-90搭載ギターと組み合わせれば、幾何学模様らしい壁のような音を体感できます。
④ リバースディレイの再現
リバースディレイは専用機が少ないですが、BOSS DD-8 Digital Delayにはリバースモードが搭載されています。価格は2〜3万円程度で、逆再生的な空間を作れるため、幾何学模様の浮遊感を模倣するのに最適です。
⑤ リバーブの選択
アンプ内蔵リバーブでも十分ですが、より深い空間表現を求めるなら、TC Electronic Hall of Fame 2などのペダルもおすすめです。これによりTwin Reverb特有の奥行き感を補うことができます。
以上のように、ギターはEpiphone、アンプはChampionやKatana、ファズはBig Muff、ディレイはBOSS DD-8を選べば、総額10万円以下でもTomo Katsuradaの音作りに大きく近づけます。大切なのは「P-90の中域」「ファズの轟音」「リバースディレイの浮遊感」の3要素を揃えることです。これらを意識すれば、幾何学模様のトリップ感あふれるサウンドを手軽に再現できるでしょう。
| 種類 | 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギター | Les Paul Special VE(P-90搭載) | Epiphone | Amazonで探す | 幾何学模様(Kikagaku Moyo) | Tomo Katsurada | P-90による中域の押し出しを安価に再現可能 |
| アンプ | Champion 40 | Fender | Amazonで探す | 幾何学模様(Kikagaku Moyo) | Tomo Katsurada | リバーブ搭載。クリーン基盤でサイケサウンドに最適 |
| エフェクター | Big Muff Pi | Electro-Harmonix | Amazonで探す | 幾何学模様(Kikagaku Moyo) | Tomo Katsurada | 厚みと倍音豊かなファズを低価格で導入可能 |
| エフェクター | DD-8 Digital Delay | BOSS | Amazonで探す | 幾何学模様(Kikagaku Moyo) | Tomo Katsurada | リバースディレイ搭載で浮遊感を再現可能 |
| エフェクター | Hall of Fame 2 | TC Electronic | Amazonで探す | 幾何学模様(Kikagaku Moyo) | Tomo Katsurada | 深い空間表現を実現するリバーブ |
総括まとめ【幾何学模様・Tomo Katsurada】

Tomo Katsuradaの音作りを振り返ると、その核心は「少数精鋭の機材で最大限の表現を引き出す」というシンプルかつ哲学的な姿勢にあります。
ギターは1本のGibson Les Paul Junior Special、アンプはFender Twin Reverb、そして限られたファズやリバースディレイを駆使することで、幾何学模様のサイケデリックな音世界を支えてきました。
この徹底したミニマリズムは、逆に「自由度の高さ」を生み出しています。多くの機材を揃えなくても、音の出し方や組み合わせ次第で圧倒的に個性的なサウンドを作れることを示しているのです。実際、彼のサウンドはシンプルな構成ながら、轟音から繊細なアルペジオ、さらには浮遊感のあるアンビエントまでを網羅しています。
幾何学模様のライブやレコーディングを聴くと、Tomoのギターは常に「音の波」として存在しています。ツインギター編成の片翼として、時にはリズムを支え、時には空間を埋め尽くすように響く。その役割は、単なるギタリスト以上に「音響を操る存在」と言えるでしょう。
特に、ファズとリバースディレイの使い方は彼の真骨頂であり、時間や空間の感覚を歪ませるような表現は、サイケデリックロックの本質そのものです。
再現を目指すギタリストにとって重要なのは、「どんな機材を揃えるか」以上に「どのように響かせるか」という感覚です。EQで余分な低域を削り、バンド全体の中でギターの居場所を確保する。ファズを単なる歪みではなく「音の壁」として活用する。リバースディレイを飛び道具ではなく「曲全体を揺らす要素」として取り入れる。これらの意識があれば、機材の価格やブランドに関係なく、幾何学模様的なサウンドに近づくことができます。
また、彼の音作りから学べるもう一つの重要な点は「制限を力に変える」という考え方です。ギター1本、アンプ1台、数台のエフェクター。この限られた環境でどれだけ音を拡張できるかに挑み続けた結果、Tomo Katsuradaの唯一無二のサウンドが生まれました。多機材主義ではなく、あえて引き算を選ぶことで、音楽的な純度と説得力を高めているのです。
結論として、Tomo Katsuradaの音作りの本質とは「シンプルな機材で無限のサウンドスケープを描くこと」にあります。幾何学模様の音楽に心を奪われた人々が、自分の環境でその雰囲気を再現したいと思ったとき、必要なのは高価な機材を揃えることではなく、この思想を理解し実践することです。
そうすることで、あなたの音もまた「幾何学模様」の一部となり、リスナーを音の旅へと誘うことができるでしょう。
“`
下記恐らく使用(所持)している機材のまとめです。参考までに!
ギター
Gibson Les Paul Junior Special(P-90ピックアップ×2搭載)
Tomo氏が使用する唯一のギターとして明記されており、ツインギター編成での役割も担う重要な一本です
Equipboard
+15
Premier Guitar
+15
musictribunetokyo.com
+15
。
アンプ
Fender Twin Reverb
清潔で広がりのあるクリーントーンの王道アンプとして、Tomo氏のサウンドにフィットしているとの記録あり
Premier Guitar
。
エフェクター
現時点、具体的なエフェクター名についての明示された情報は見当たりませんでした。ただし、YouTubeレビューから以下のような特徴的な使用が確認できます:
リバース・ディレイやファズ(Fuzz)サウンドをたっぷり使った、ドローン的でサイケデリックなギタートーンを構築しており、飛び道具的な響きの表現に力を入れていることが明記されています
YouTube
。
ただし、現時点で「これを使ってます」と特定されているペダル名はありませんので、下に「想定候補」としてお示ししておきます。
まとめ一覧(重複排除済み)
カテゴリ 機材名 備考
ギター Gibson Les Paul Junior Special P‑90×2、Tomoの一本勝負ギター
musit.net
+7
Premier Guitar
+7
Mikiki
+7
アンプ Fender Twin Reverb クリーンサウンド基盤
Premier Guitar
エフェクター —(不明) リバース・ディレイ、ファズ使用の記録あり
YouTube
補足(想定) リバースディレイ系、ファズ系ペダル 使用傾向からの推測(例:Electro-Harmonix Memory Manの逆再生、Big Muff系など)