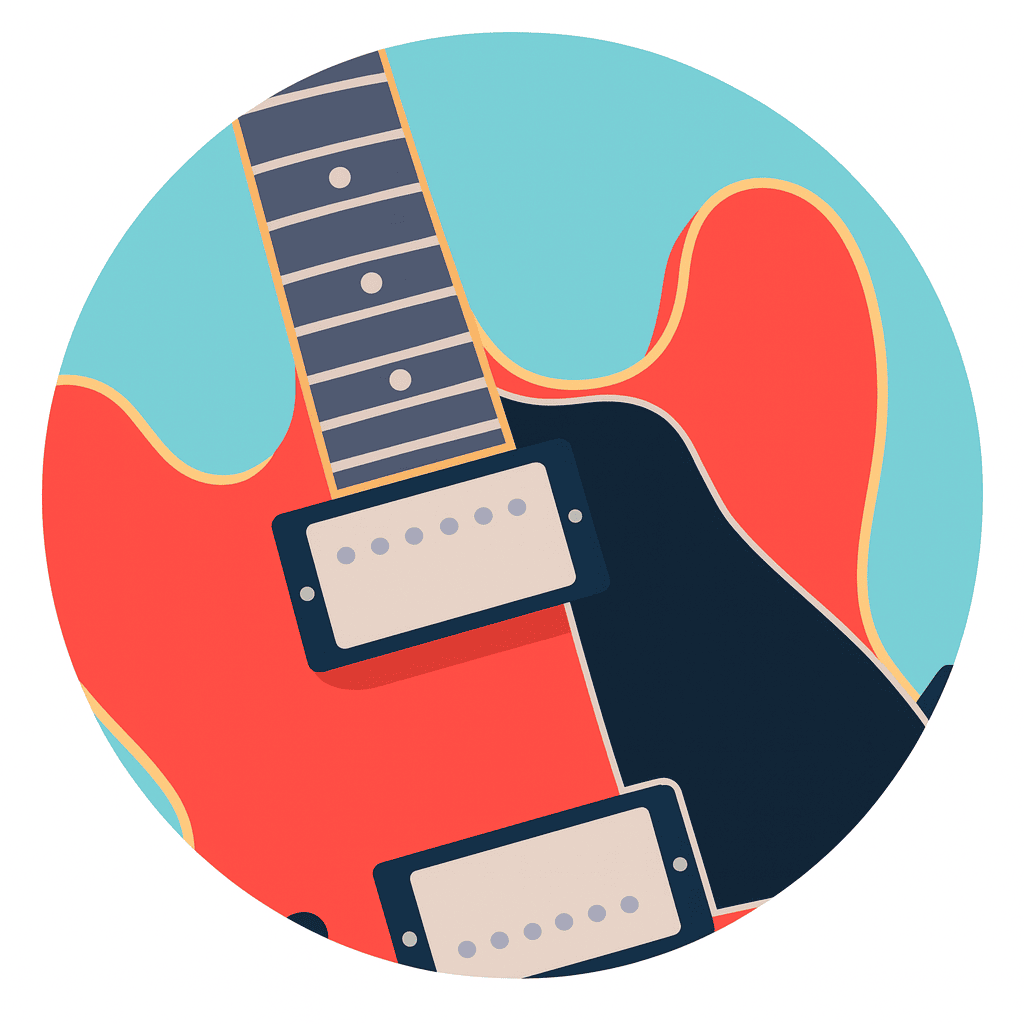始めに(特徴紹介)
Helsinki Lambda Clubのギタリスト、橋本薫のサウンドは、オルタナティブやインディーロックの影響を強く感じさせる独自のスタイルです。シンプルなコードワークの中に不協和音や揺らぎを巧みに織り込み、浮遊感と攻撃性を両立させています。
特にライブにおいては、クリーンから歪みへのダイナミックな切り替えや、フェイザーやディレイを活用したスペーシーな音作りが顕著で、観客を独特のサイケデリックな世界観へと引き込んでいきます。彼のプレイは決して派手なテクニックに頼るものではなく、むしろ「どのような質感の音を選び、どうミックスするか」に重点が置かれており、これはHelsinki Lambda Club全体の音像形成にも直結しています。
代表曲としては「午睡」「Skin」「See The Light」などが挙げられます。これらの楽曲では、Fender Mustangを中心としたクランチサウンドと、空間系エフェクトを駆使したトーンが印象的であり、音数を抑えながらも曲の個性を際立たせています。
また、SNSやtone.bookなどで確認されている機材は実際にライブやレコーディングでも使用されており、彼のサウンドの核を理解する上で非常に参考になります。シーン全体で「いかに個性を持ったサウンドを構築できるか」が問われる中で、橋本薫の音作りは確実に一つの指標になっているといえるでしょう。
使用アンプ一覧と特徴【Helsinki Lambda Club・橋本薫】
橋本薫の音作りにおいて、アンプの選択は非常に重要な役割を担っています。確認できるメインの使用アンプは、Fender HOT ROD DEVILLE 410 IIIです。これは10インチスピーカーを4発搭載したコンボアンプで、フェンダーらしいクリーントーンと、十分なヘッドルームを持つ点が特徴です。ライブでもスタジオでも扱いやすく、ピュアなクリーンから荒々しいクランチまで幅広く対応できるため、Helsinki Lambda Clubの多彩な楽曲にフィットしています。
このアンプは特に、Mustangのシングルコイルピックアップとの相性が良く、ガラスのように透き通った高域や、歯切れの良いカッティングを際立たせる傾向にあります。歪みの大部分はペダルによって補うことが多く、アンプ自体はクリーン〜軽いブレイクアップ程度で使用されるケースが多いと考えられます。
さらに、tone.bookで確認された情報によると、Kemper Profiling Ampも導入されているとのことです。これはモデリングアンプとして、ライブや宅録での再現性を高めるために用いられているようで、実際のアンプとペダルを併用していると記録されています。これにより、実機のFenderアンプの音を再現しながら、必要に応じてプリセット切替を行うことが可能となっています。
その他、明確な証拠は少ないものの、スタジオレコーディングや一部のライブでは、Fender Twin ReverbやBlues Deluxeといった他のフェンダー系アンプを使用していた可能性も指摘されています。これらは公式インタビューなどで直接的な言及は確認できませんが、サウンド傾向やジャンル的な背景を踏まえると、補助的に利用されていた可能性は高いでしょう。
全体として、橋本薫のアンプ選びは「クリーントーンの美しさ」「ペダルとの相性」「ライブでの音抜け」を重視しているといえます。フェンダー系のアンプを土台にしながら、エフェクターで幅広い音色を構築するスタイルは、彼の音作りの根幹となっていると想定されます。
使用ギターの種類と特徴【Helsinki Lambda Club・橋本薫】

橋本薫が使用するギターは、Fender Mustangを中心としています。特に1978年製のMustangを愛用しており、ショートスケールによる独特の弦のテンション感と、シングルコイルピックアップの明瞭なトーンが特徴です。Mustangはその軽快なフィーリングにより、コードカッティングやアルペジオに適しており、橋本のプレイスタイルに非常にマッチしています。
また、彼は楽曲によっては、Fender JazzmasterやFender Stratocasterなども使用しているとされています。これらのギターは、トレモロアームを活かしたヴィブラートや、幅広い音色のバリエーションを提供するため、楽曲に応じて使い分けられています。Jazzmasterの豊かなミドルレンジやStratocasterのクリアな高域は、橋本のサウンドに多彩な表情を加える要素となっています。
これらのギターはそれぞれに特徴があり、橋本はその音色の特性を巧みに活かしてHelsinki Lambda Clubの多様な楽曲に対応しています。特に、ショートスケールやトレモロユニットによるニュアンスのコントロールは、彼の演奏における重要な要素となっています。
使用エフェクターとボード構成【Helsinki Lambda Club・橋本薫】
橋本薫の音作りにおいて特に重要な要素が、エフェクターボードの構成です。ライブ写真やtone.book、各種インタビューから確認できるように、彼はチューナー、EQ、コンプレッサー、ブースター、オーバードライブ、ファズ、ディストーション、フェイザー、ディレイといった幅広いジャンルのペダルを駆使しています。
まずシグナルチェーンの起点には、KORG pitchblackのチューナーが配置されています。シンプルで正確なチューニングを可能にし、ライブでの安定した演奏を支えています。その後に置かれるのが、Source Audio EQ2 Programmable Equalizer。これは細かい周波数調整が可能なグラフィックEQで、Mustang特有のショートスケール・シングルコイルの音色を最適化する役割を担っています。
ダイナミクス系では、Carl Martin Classic Opto Compressorを使用。これによりピッキングニュアンスを均一化し、クリーントーンの粒立ちを揃えることが可能になります。さらに、MXR Micro AmpやTC Electronic Spark Boosterといったクリーンブースター/ブースターを活用し、ソロや楽曲の盛り上がりで音量と存在感を強調しています。
歪み系では、VEMURAM Jan Ray(オーバードライブ)を中心に、クラシックでありながら現代的なトーンを実現。加えて、借り物とされるメーカー不明のディストーションや、Electro-Harmonix OP-AMP Big Muffによる分厚いファズサウンドを組み合わせ、楽曲によって多彩な歪みを使い分けています。
モジュレーション系では、Electro-Harmonix Small Stone(フェイザー)が特徴的です。特にサイケデリックな質感を持たせたい楽曲で活躍し、アルペジオやカッティングに揺らぎを与えています。そして空間系では、TC Electronic Flashback X4 Delayが導入されており、タップテンポ機能を活用することで、楽曲ごとに異なる空間処理を即座に行える点が強みです。
このように橋本薫のボードは「クリーン〜歪み〜空間系」の流れを徹底的にコントロールする設計となっており、楽曲の持つ浮遊感や攻撃性を自在に演出できる構成になっています。特にペダルを複数段階で重ねがけすることで、細やかな音色変化を生み出している点が彼のサウンドの肝といえるでしょう。全体を通して、「シンプルなコード進行でも音色の厚みで楽曲をドラマチックに展開する」という橋本薫のアプローチがよく表れたボード構成と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | エフェクターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pitchblack | KORG | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | チューナー | 定番チューナー。ライブでの安定性を支える。 |
| EQ2 Programmable Equalizer | Source Audio | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | イコライザー | 周波数調整でMustangの特性を補正。 |
| Classic Opto Compressor | Carl Martin | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | コンプレッサー | クリーントーンの粒立ちを整える。 |
| Micro Amp | MXR | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | ブースター | クリーンブースター。ソロで音量を上げる。 |
| Jan Ray | VEMURAM | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | オーバードライブ | メインの歪みペダル。ナチュラルなドライブ感。 |
| ディストーション(借り物) | 不明 | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | ディストーション | 借り物との記録あり。曲によって使用。 |
| OP-AMP Big Muff | Electro-Harmonix | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | ファズ | 分厚い壁のような歪みを作る。代表曲でも使用。 |
| Spark Booster | TC Electronic | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | ブースター | 音量・音圧を底上げする多用途ペダル。 |
| Small Stone | Electro-Harmonix | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | フェイザー | サイケデリックな揺らぎを演出。 |
| Flashback X4 Delay | TC Electronic | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | ディレイ | タップテンポ対応。楽曲ごとにディレイタイムを調整。 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【Helsinki Lambda Club・橋本薫】

橋本薫の音作りは、ギターやアンプ、エフェクター単体の特性に頼るだけでなく、EQ設定やミックス上での工夫によって完成されています。特にMustang(1978年製)のようにレンジがやや狭く、ミドルが控えめなギターを使用しているため、アンプやEQでの補正が重要な要素となります。
アンプに関しては、Fender HOT ROD DEVILLE 410 IIIを基本クリーン設定にし、ペダルで歪みを作るスタイルが多いと考えられます。トーン設定の傾向としては、
・Bass(低域):4〜5程度。過剰なローを削ることで、ベースとの棲み分けを行う。
・Middle(中域):6〜7程度。Mustangの弱点であるミドル成分を補い、抜けを強調。
・Treble(高域):5〜6程度。シングルコイルのきらびやかさを残しつつ耳に痛くならない範囲で調整。
このように設定することで、クリーンでも前に出るサウンドが形成されます。
エフェクターに関しては、EQ2 Programmable Equalizerが大きな役割を担います。曲によっては2kHz付近を軽くブーストしてカッティングを際立たせたり、ローをカットしてタイトなリズムを出す工夫が行われていると想定されます。また、コンプレッサー(Carl Martin Classic Opto Compressor)は、ピッキングの強弱を自然に整え、空間系との相性を良くするために使用されているでしょう。
歪み系は複数のステージを重ねて作られます。Jan Rayによる軽いオーバードライブを常時ONにしてクランチの基礎を作り、その上にMicro AmpやSpark Boosterでゲインを押し上げることで、ソロやサビの盛り上がりを演出します。さらに、Big Muffを組み合わせたときには壁のような分厚いサウンドが形成され、グランジ/シューゲイザー的な質感を加えることが可能です。
モジュレーションと空間系の使い分けも特徴的です。Small Stoneは主にアルペジオやバラード曲で揺らぎを与える役割を果たし、ディレイ(Flashback X4)はタップテンポを活用することで、BPMに応じたリピートタイムを設定しています。リピート回数は2〜4回、Mixは30〜40%程度に設定することで、演奏を邪魔せず奥行きを広げるバランスを実現しています。
ミックスの観点では、橋本薫のギターは常にバンド全体のサウンドを支えるポジションを担っています。特にHelsinki Lambda Clubの楽曲は多層的なアレンジが多いため、ギターのEQは中域を強調しつつ、他パートとの住み分けを重視しているのが特徴です。例えば、ベースがローを厚く支えている場合、ギターはローカットを強めにして定位をミドル〜ハイに寄せることが多いと考えられます。
PAやエンジニアリングにおいては、アンプのマイキングはSM57やリボンマイクとの組み合わせが想定されます。これによりアタック感と空気感の両方を捉え、スタジオ録音でもライブに近い迫力を再現している可能性があります。加えて、Kemper Profiling Ampを併用することで、楽曲によってはプリセットされたサウンドを使い分け、即座に音色を切り替える柔軟性を確保しています。
総じて橋本薫の音作りは、「クリーンを土台に、複数の歪み・EQで色付けし、空間系で広がりを与える」設計思想に基づいています。これにより、シンプルなフレーズでもバンド全体を支配する存在感を持ち、Helsinki Lambda Clubの世界観を演出していると想定されます。
比較的安価に音を近づける機材【Helsinki Lambda Club・橋本薫】
橋本薫の機材は高価なモデルが多く、特にVEMURAM Jan RayやKemper Profiling Ampといったアイテムは初心者にはハードルが高いです。しかし、彼のサウンドの本質は「クリーンを基盤にしたシンプルな歪み」「EQでの中域補強」「空間系の広がり」にあります。そのため、比較的安価な市販機材を組み合わせても、十分に近い音を再現することが可能です。
まずギターについては、Fender USA Mustangのヴィンテージは高額ですが、現行のMustangシリーズやSquier by Fenderの廉価版で十分に雰囲気を掴むことができます。ショートスケールとシングルコイルという仕様を押さえれば、音色のキャラクターは近づけやすいでしょう。
歪み系ペダルについては、Jan Rayの代替としてBOSS SD-1 Super OverDriveやBD-2 Blues Driverが最適です。これらはミドルレンジに特徴があり、クリーンアンプをベースにしたブーストや軽いドライブを実現できます。さらにBig Muffの代替にはBOSS DS-1 DistortionやElectro-HarmonixのNano Big Muffを選ぶと、分厚い歪みを安価に再現できます。
空間系では、TC Electronic Flashback X4は高価ですが、同社のFlashback MiniやBOSS DD-7/DD-8などで代用可能です。タップテンポ機能も搭載されており、ライブや練習でも柔軟に対応できます。モジュレーション系は、Small Stoneの代替としてBOSS PH-3 Phaserを選べば、揺らぎのあるサウンドを簡単に再現できます。
また、EQやコンプレッサーに関しては、Source AudioのEQ2やCarl Martinのコンプは高価なので、BOSS GE-7(グラフィックEQ)やBOSS CS-3(コンプレッサー)といったスタンダードな機材を導入すれば十分です。これらは長年にわたって定番として使われてきた信頼性の高いペダルであり、初心者が橋本薫のように音色を整える練習をするには最適といえます。
総じて、彼の音を追いかける上で重要なのは「高級機材そのもの」ではなく、「ショートスケールのシングルコイルギター」「クリーンを軸としたフェンダー系アンプ」「オーバードライブ+空間系の組み合わせ」という3点です。これを理解して安価な代替機材を選べば、初心者でも十分に近い雰囲気を作り出せるといえるでしょう。
| 種類 | 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギター | Squier Classic Vibe Mustang | Squier by Fender | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | USAヴィンテージの代替として最適。ショートスケール特性を再現。 |
| オーバードライブ | SD-1 Super OverDrive | BOSS | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | Jan Rayの代用。中域を強調し抜けの良いドライブを再現可能。 |
| ディストーション/ファズ | Nano Big Muff | Electro-Harmonix | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | OP-AMP Big Muffの廉価版。分厚い歪みを再現。 |
| ディレイ | DD-8 Digital Delay | BOSS | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | Flashback X4の代替。タップテンポ搭載でライブにも対応。 |
| フェイザー | PH-3 Phaser | BOSS | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | Small Stoneの代替。サイケな揺らぎを表現可能。 |
| イコライザー | GE-7 Equalizer | BOSS | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | Source Audio EQ2の代替。7バンドEQで音作りを簡単に補正可能。 |
| コンプレッサー | CS-3 Compression Sustainer | BOSS | Amazonで探す | Helsinki Lambda Club | 橋本薫 | Carl Martinのコンプの代替。粒立ちを整え、クリーンを安定化。 |
総括まとめ【Helsinki Lambda Club・橋本薫】

橋本薫の音作りの本質は、単なる「機材の豪華さ」や「特殊なプレイスタイル」ではなく、シンプルな土台を徹底的に磨き上げ、必要な場面で的確に彩りを加えることにあります。フェンダー系アンプのクリーンを基盤に、Mustang特有のショートスケールならではの軽快さ、そして歪みや空間系エフェクトを繊細に積み重ねていくことで、オルタナティブかつサイケデリックな世界観を構築しています。
特に印象的なのは、EQとコンプレッサーの使い方です。多くのギタリストが「歪み」や「ディレイ」に注目しがちですが、橋本薫は中域の補強や粒立ちの調整を大切にしており、バンド全体の音の中でギターが埋もれず存在感を保つ工夫をしています。これにより、シンプルなコードストロークでも楽曲を支配する厚みを持たせることができるのです。
また、歪みのレイヤー構築も大きな特徴です。クランチの基盤をJan Rayで作り、Micro AmpやSpark Boosterで押し上げる。そして必要な場面でBig Muffを重ねることで、一気に音の壁を作り出す。このように「段階的に音を育てていく」発想が、橋本薫の音作りをユニークなものにしています。
空間系やモジュレーションの使い方も楽曲の世界観に直結しています。Small Stoneによるフェイズ感やFlashback X4によるディレイの奥行きは、バンドのサイケデリックな側面を強調し、聴き手を没入させます。これらは単なる装飾ではなく、曲のテーマを支える重要な要素です。
初心者が彼の音を目指す場合、必ずしも高価な機材を揃える必要はありません。むしろ大切なのは「クリーン基盤」「シンプルなオーバードライブ」「EQとコンプの活用」「空間系のセンスある使い方」の4つです。このポイントを意識すれば、比較的安価な代替機材でも十分に橋本薫の世界観を再現することが可能です。
総じて、橋本薫の音作りは「引き算と足し算のバランス」に優れています。音を足すことで厚みを生みつつ、不要な帯域を引いて整理する。そうすることで、楽曲全体に調和しながらも、自身のギターが存在感を放ち続けるのです。これはHelsinki Lambda Clubのサウンドを支える大黒柱であり、彼のギタリストとしての最大の魅力といえるでしょう。
あなたが彼の音に憧れて機材を揃えるとき、ただ同じペダルをコピーするだけでなく、「なぜその機材を選んでいるのか」「どの帯域を強調したいのか」という意識を持つことが重要です。その視点こそが、橋本薫の音作りに最も近づくための第一歩になるはずです。
“`
下記恐らく使用(所持)している機材のまとめです。参考までに!
ギター
Fender USA Mustang(1978年製/SSピックアップ、トレモロ搭載)
エフェクター(ボード)
KORG / pitchblack(チューナー)
Source Audio / EQ2 Programmable Equalizer(グラフィックEQ)
Carl Martin / Classic Opto Compressor(コンプレッサー)
MXR / Micro Amp(クリーンブースター)
VEMURAM / Jan Ray(オーバードライブ)
メーカー不明 / ディストーション(借り物と記載あり)
Electro-Harmonix / OP-AMP Big Muff(ファズ)
TC Electronic / Spark Booster(ブースター)
Electro-Harmonix / Small Stone(フェイザー)
TC Electronic / Flashback X4 Delay(ディレイ/タップ付き)
アンプ
Fender / HOT ROD DEVILLE 410 III(コンボ/10インチ×4)
その他
Kemper Profiling Amp(tone.book告知投稿より。ペダルと併用との記載)