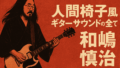始めに(特徴紹介)
19(ジューク)のギタリスト・岡平健治は、90年代後半から2000年代にかけてストリート発のアコースティックサウンドを全国に届けた存在として知られています。彼のプレイは、フォークをベースにしながらも、バンド的な厚みを持たせたストロークや、シンプルながらも情熱的なコードワークが特徴です。
代表曲である「あの紙ヒコーキ くもり空わって」や「卒業の歌、友達の歌。」では、厚みのあるアコースティックサウンドが楽曲の核を担っています。Ovationのリーフ型サウンドホールを持つギターによるクリアなアタック感は、岡平サウンドの大きな要素と言えるでしょう。また、初期の路上時代にはYAMAHA FGシリーズに多くのステッカーを貼り、リアルな青春感を放っていました。
彼の音は、派手なエフェクトに頼ることなく、ギター本来の響きをPAを通して観客に届けるスタイルにあります。ライブでもストリートでも、歌とアコースティックギターの響きがダイレクトに伝わるよう工夫されており、この潔さこそが多くのファンの心を掴んできました。
この後のセクションでは、岡平健治が実際に使用してきたギターやアンプ、エフェクターについて詳しく掘り下げ、彼の音作りをどのように再現できるかを解説していきます。
使用アンプ一覧と特徴【19・岡平健治】
岡平健治(19)のアンプ環境は、ロックバンドのような大型アンプを積極的に使うスタイルではなく、アコースティックギターの特性をそのまま観客に届ける「DI直」の運用が中心と考えられます。特にOvationやMartinといったエレアコには高性能プリアンプが内蔵されており、その出力を会場のPAに直接送ることで、クリーンかつナチュラルなサウンドを実現していました。
初期の路上ライブや小規模ステージでは、YAMAHA FGシリーズのようなノンエレアコをマイク録りしていた時期もあると推測されます。しかし、メジャーデビュー以降のツアーやテレビ出演では、Ovation EliteやAdamasなどのエレアコを使用し、Ovation純正のOPシリーズ・プリアンプを搭載したモデルを中心にPAに送るスタイルが主流でした。この方法により、ハウリングを抑えつつ、音量を確保できる点が大きなメリットとなっています。
一方で、完全なアンプ未使用というわけではなく、ステージ規模や音響環境によっては、アコースティック専用アンプをモニター的に利用していた可能性も考えられます。一般的にOvationユーザーが併用するアンプとしては、Roland AC-60やFishman Loudbox、あるいはMarshallのアコースティック用プリアンプ(JMP-1)+パワーアンプ(EL34 100/100)のような構成が参考例として挙げられます。岡平自身の機材に関する明確な証拠は少ないですが、当時のアコースティックギタリストが採用していたシステムに近い運用をしていたと推測されます。
また、会場PA側ではリバーブを軽く加え、アコースティック特有のドライさを補う調整が行われていたようです。これにより「紙ヒコーキ」のような爽やかな広がりや、「卒業の歌」のような温かい響きを実現していたと考えられます。結果として、岡平の音作りは「PA直結+最小限の空間処理」という極めてシンプルな構成で成り立っていた、と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蔵プリアンプ(Ovation OPシリーズ等)+DI直 | Ovation | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | Ovation搭載プリアンプからPA直送。ライブでの標準的な運用。 |
| Roland AC-60(参考) | Roland | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | 本人使用確定ではないが、Ovation系ユーザーが好んで使用する小型アコギアンプ。 |
| Marshall JMP-1 | Marshall | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | プリアンプ。本人使用の明確証拠はないが、アコースティック系にも使われる例あり。 |
| Marshall EL34 100/100 | Marshall | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | ステレオ・パワーアンプ。PA直結の補強的に導入可能性ありと推定。 |
使用ギターの種類と特徴【19・岡平健治】

岡平健治の音作りの中心にあるのは、Ovationをはじめとしたエレアコの数々です。19(ジューク)の楽曲は、アコースティックギターの生々しさを前面に押し出したスタイルで知られており、ギターの選択がそのままサウンドのキャラクターに直結していました。
まず最も有名なのが、Ovation Elite 1868-7QAです。リーフ型サウンドホールを持つこのモデルは、薄胴設計でライブパフォーマンスに最適化されており、岡平のストロークスタイルに非常にマッチしています。2000年代のテレビ出演やツアーでもたびたび確認され、19サウンドの代名詞的存在といえるでしょう。
さらに上位機種として、限定生産の希少モデルOvation Adamas III 1591-BCBも使用されています。ブルーカーボンの独特なルックスと高い耐久性、そして繊細な高音の再現力により、代表曲での透明感のある響きを支えました。1997年にリリースされたこのモデルは、ファンの間でも「岡平モデル」として話題になりました。
他にも、Ovation N868-7QMの同型モデル使用が中古市場で語られており、本人同型とされる個体がオークションに出回った記録があります。信憑性には限界があるものの、同時期の岡平がこうしたOvation群を複数本使い分けていたことを示唆しています。
また、初期の路上時代にはYAMAHA FGシリーズを使用。ボディにはステッカーを多数貼り付け、まさに「青春の象徴」とも言える存在でした。このギターはアンプやDIを通さず、マイク録りで使われていたと推測されます。ほかにも、Epiphoneのヴィンテージ系モデル、そして愛称「光二号」「光三号」と呼ばれるMartin製エレアコが確認されています。Martinはツアー後期のライブで活躍し、Ovationに比べて柔らかく温かみのあるトーンを響かせました。
このように、岡平健治のギター選びは「ステージでの耐久性と音抜け」「アコースティックの響きを最大限生かすナチュラルさ」という2つの軸で構成されており、OvationとMartinを使い分けることで多彩なサウンドを実現していたと想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | ギターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovation Elite 1868-7QA | Ovation | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | エレアコ | リーフ型サウンドホール、薄胴仕様。ライブ使用多数確認。 |
| Ovation Adamas III 1591-BCB | Ovation | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | エレアコ | 限定生産・希少モデル。高音域の抜けと耐久性が魅力。 |
| Ovation N868-7QM(同型情報) | Ovation | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | エレアコ | 本人同型とされる中古出品あり。信憑性は限定的。 |
| YAMAHA FGシリーズ | YAMAHA | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | アコースティックギター | 路上ライブ時代に使用。ステッカー多数貼付。 |
| Epiphone ヴィンテージ系 | Epiphone | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | アコースティックギター | 型番不詳。メインではないが使用言及あり。 |
| Martin エレアコ(光二号/光三号) | Martin | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | エレアコ | ライブで使用。Ovationより柔らかく温かい音色。 |
使用エフェクターとボード構成【19・岡平健治】
岡平健治(19)の音作りにおいて、エフェクターは大きな役割を担っていたわけではありません。彼のスタイルは「アコースティックギター+歌」を中心とするため、歪み系やモジュレーション系といった派手なエフェクターは使用せず、必要最小限の機材でサウンドをまとめていました。
基本的なシグナルフローは、チューナー → DI(ダイレクトボックス/プリアンプ) → 会場PA というシンプルなものです。チューナーはライブ演奏に必須で、BOSS TUシリーズなど堅実な定番機種を使っていた可能性が高いでしょう。これにより安定したピッチでの演奏を支えていました。
アコースティック用のDIとしては、L.R.Baggs Para Acoustic DI のようなプリアンプ内蔵モデルが想定されます。これはOvationなどのエレアコと組み合わせることで、会場環境に合わせてEQ補正やゲイン調整を行うことができ、岡平のようにPA直結で音を届けるスタイルには必須の存在です。
ライブ現場では、PA卓側でリバーブや軽いコンプレッションが加えられていたと考えられます。本人が足元にリバーブを置く必要はなく、むしろPAエンジニアが楽曲に合わせて最適な空間処理を施していたというケースが一般的です。代表曲「あの紙ヒコーキ くもり空わって」では広がりを意識したリバーブ、「卒業の歌」では残響を控えめにして歌のメッセージ性を際立たせる、といった調整がされていた可能性があります。
また、エフェクトというよりは「ライン信号を整える周辺機材」の使用が中心で、ノイズ対策や安定した電源供給のために、パワーサプライやバッファーを組み込んだボード構成を組んでいたと考えられます。ただし、派手なペダルボード写真や本人発言は残っていないため、あくまで「アコースティック系ギタリストの一般的な運用」として推定されます。
総じて、岡平健治のエフェクターボードは「チューナー+DI+最小限の補助」という極めてシンプルな構成で、ギター本来の音をダイレクトに届けることを最優先にしていた、と想定されます。
| 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | エフェクターの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS TUシリーズ(TU-2/TU-3等) | BOSS | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | チューナー | ステージ必須機材。本人使用確定情報は不明だが、アコギ奏者に定番。 |
| L.R.Baggs Para Acoustic DI | L.R.Baggs | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | ダイレクトボックス | EQ補正とゲイン調整可能。Ovationとの相性が良いとされる。 |
| 会場PAリバーブ | —(PA側処理) | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | リバーブ | 足元に設置ではなくPA卓で付加。残響量は楽曲ごとに調整。 |
| アコースティック用パワーサプライ/バッファー | Voodoo Lab など | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | パワーサプライ/バッファー | 安定した電源供給・ノイズ対策用。一般的なアコギ奏者のボード構成例。 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【19・岡平健治】

岡平健治の音作りは、ロックギタリストのようにアンプやエフェクターでサウンドを構築するというよりも、アコースティックギター本来の響きを活かしつつ、会場PAで最適化するスタイルが基本です。そのため、エンジニア的な観点から見ると「ライン直+EQ調整+リバーブ補正」という非常にシンプルな構成で成り立っていると言えます。
まずEQ設定について。Ovation EliteやAdamasなどのエレアコは、低域が膨らみやすく、中域から高域のアタックが強調されやすい特徴を持っています。そのため、PAでのセッティングでは以下のような調整が想定されます。
- 低域(80Hz〜120Hz):ハウリング防止のため軽くカット。不要な「ボワつき」を抑える。
- 中域(500Hz〜1.5kHz):歌声と被る帯域を避け、ギターのストローク感を前に出す。場合によってはややカット。
- 高域(4kHz〜8kHz):ピックのアタック感を強調し、ストロークの勢いを伝える。ブライト感を出すと楽曲に爽快さが増す。
また、曲ごとの使い分けも重要です。「あの紙ヒコーキ くもり空わって」では、爽やかで広がりのある音像を作るために高域をしっかり出し、リバーブを深めに設定。逆に「卒業の歌」や「三分間日記」のようなメッセージ性の強い楽曲では、リバーブを抑え、ボーカルとギターが近く感じられるようなタイトなミックスが意識されたと考えられます。
プリアンプやDIでの調整も大きな役割を果たしています。L.R.Baggs Para DIのような機材を用いることで、会場ごとに異なるアコースティック特有のハウリング周波数を制御でき、安定した音響を保つことが可能です。特に中域の微調整や位相スイッチによる調整は、アコースティックライブの成功を左右するポイントでした。
ミックス段階では、岡平のギターは「歌を邪魔せずに、リズムとコード感を支える」役割を果たしていました。バンドサウンドではなくデュオ編成であったため、ギターの存在感は非常に大きく、ストロークの強弱や右手のニュアンスを丁寧に拾うマイキング/ライン調整が必要とされました。EQやコンプレッションのかけ方次第で、楽曲全体の雰囲気が変わってしまうため、PAエンジニアは細心の注意を払っていたはずです。
さらに、ライブではギターを複数本使い分けていたため(OvationとMartinの切り替えなど)、その都度EQやゲインの再調整が求められたと考えられます。Ovationでは明るくシャープなサウンド、Martinでは柔らかく温かみのあるサウンドを意識的に作り分けていた、と推測できます。
結論として、岡平健治の音作りは「ギター本来の音を最大限に活かし、PAで最小限の補正を行う」というシンプルかつ高度なアプローチで成り立っており、これは彼の楽曲の透明感や真っ直ぐなメッセージ性を支える大きな要因となっていた、と想定されます。
比較的安価に音を近づける機材【19・岡平健治】
岡平健治(19)のサウンドは、エレアコを中心にDIを通してPAへ直結するというシンプルな構成です。そのため、派手なハイゲインアンプや多彩なエフェクトを揃える必要はなく、比較的安価な機材でも再現が可能です。ここでは初心者〜中級者向けに、岡平サウンドへ近づけるためのおすすめ機材を紹介します。
まず最重要となるのがエレアコです。本人が使用していたOvation EliteやAdamasは中古市場でも高額ですが、手頃に入手できる代替品としてはOvation Celebrityシリーズがあります。トップ材や装飾の違いはあるものの、リーフ型サウンドホールや薄胴ボディを備えており、ライブでも扱いやすいモデルです。
加えて、初期の岡平サウンドを意識するならYAMAHA FGシリーズもおすすめです。路上時代に多用されたこのシリーズは、低価格ながら音量感と安定感があり、初心者でも扱いやすい万能モデルです。ステッカーを貼って「自分仕様」にするのも当時の雰囲気を再現できます。
次に、PAやアンプにつなぐためのアコースティック用DI/プリアンプが重要です。代表的なものにL.R.Baggs Para Acoustic DIがありますが、やや高価なため、より手頃な選択肢としてBOSS AD-2 Acoustic PreampやZoom AC-2が挙げられます。これらは1〜3万円程度で入手でき、ハウリング対策やEQ補正、リバーブの付加など、岡平サウンドに必要な機能をしっかり備えています。
チューナーについては、シンプルにBOSS TU-3を導入すれば十分です。耐久性が高く、ステージでも視認性がよいため、多くのプロアコギ奏者に愛用されています。
最後にリバーブですが、足元でコントロールするならTC Electronic Hall of Fame 2のようなコンパクトリバーブがおすすめです。ライブ会場ではPA卓で処理されることが多いですが、自宅練習や小規模ライブではリバーブペダルを活用することで「紙ヒコーキ」のような広がりのあるサウンドを再現できます。
総じて、岡平健治の音を近づけるポイントは「エレアコ+DI+リバーブ」という最小限のセットを整えることです。これらの機材は初心者にも扱いやすく、5万円以内でも十分に岡平サウンドの核心部分を体感できる、と言えるでしょう。
| 種類 | 機材名 | メーカー | Amazon最安値URL | アーティスト | ギタリスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エレアコ | Ovation Celebrity Elite | Ovation | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | 本人使用Ovationの廉価版。リーフ型サウンドホールを備えた実用的モデル。 |
| アコースティックギター | YAMAHA FG800 | YAMAHA | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | 路上時代を再現するなら最適。安価かつ定番の入門モデル。 |
| プリアンプ/DI | BOSS AD-2 Acoustic Preamp | BOSS | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | コンパクトで安価。リバーブ機能付きでストリートにも最適。 |
| プリアンプ/DI | Zoom AC-2 | Zoom | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | 複数のアコースティックモードを搭載し、低価格帯で実用的。 |
| チューナー | BOSS TU-3 | BOSS | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | 定番ステージチューナー。耐久性・視認性ともに優秀。 |
| リバーブ | TC Electronic Hall of Fame 2 | TC Electronic | Amazonで探す | 19 | 岡平健治 | 多彩なリバーブタイプを搭載。小規模ライブや宅録に有効。 |
総括まとめ【19・岡平健治】

岡平健治(19)の音作りは、派手なアンプや複雑なエフェクトではなく、「アコースティックギターの生音をいかにダイレクトに伝えるか」という一点に集約されます。彼のサウンドの本質は、OvationやMartinといったエレアコの持つ個性を最大限に引き出し、PAやDIを通じて観客へストレートに届けるスタイルにありました。
初期の路上時代には、ステッカーだらけのYAMAHA FGシリーズを抱えて歌い、デビュー後はOvation EliteやAdamasといったハイエンドモデルを駆使。さらに「光二号」「光三号」と呼ばれるMartinエレアコも使い分け、楽曲ごとに最適な響きを選択していました。このように、ギターそのものが彼の「音色の表現手段」であり、機材の数ではなく選び抜いた一本で勝負する姿勢が見えてきます。
また、エフェクターに頼らずシンプルなDI直結スタイルを貫いた点も特徴的です。チューナーとDI、そして会場のリバーブ処理のみで完成するサウンドは、シンプルであるがゆえに演奏者の技量と表現力がそのまま音に反映されます。だからこそ、岡平の力強いストロークや歌心のこもったコードワークが、観客にダイレクトに届いていたのでしょう。
再現を目指すうえで大切なのは、Ovation系やYAMAHA FG系のアコースティックを用意し、プリアンプ/DIで最低限の補正を行うこと。そしてEQやリバーブは「引き算の音作り」を意識することです。派手に加工するよりも、ギター本来の響きを活かすほうが岡平らしさに近づきます。
つまり、岡平健治の音作りの核心とは「シンプルさ」と「真っ直ぐさ」にあります。楽曲の持つメッセージを邪魔せず、アコースティックギターと声の調和を最大限に生かす。その思想こそが19のサウンドを唯一無二のものにしていると言えるでしょう。読者の皆さんも、彼の音を再現する際には「足すより削る」「作り込むよりも響きを信じる」という視点を大切にしてみてください。
下記恐らく使用(所持)している機材のまとめです。参考までに!
ギター
Ovation Elite 1868-7QA
備考:19期を含む使用例の言及あり。リーフ型サウンドホール/薄胴でライブ向き。
教えて!goo
Ovation Adamas III 1591-BCB
備考:上位機・限定生産系の愛用情報。1997年リリースの希少個体としても知られる。
教えて!goo
デジマート
Ovation N868-7QM(同型使用情報)
備考:中古市場で「本人同型」説明のある個体(証拠性は限定的)。
Yahoo!オークション
YAMAHA FGシリーズ(ステッカー多数貼付)
備考:路上~初期ライブでの使用言及。
教えて!goo
Epiphone(型番不詳のヴィンテージ系)
備考:メインではないが使用言及あり。
教えて!goo
Martin エレアコ(愛称「光二号/光三号」)
備考:型番未特定。ライヴ用エレアコとしての使用言及。
教えて!goo
アンプ
想定:専用ギターアンプは未確認。Ovation 等の内蔵プリアンプ → DI 直で会場PAに送る運用が主と推定。
備考:公開情報で具体モデル不明のため“想定”扱い。
教えて!goo
エフェクター/周辺(足元・ライン)
想定:
チューナー(例:BOSS TU系)、
アコースティック用DI/プリアンプ(例:L.R.Baggs Para DI 等の同等機能)、
会場側のリバーブ/軽いコンプ処理。
備考:本人固有モデルは未確認。アコギ直系シグナルフローの一般解として“想定”。